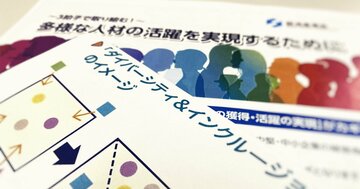記事一覧
企業向けの「アンコンシャスバイアス研修」を受けて、私がわかったこと
「アンコンシャスバイアスへの気づきは、 ひとりひとりがイキイキと活躍する社会への第一歩」――これは、内閣府男女共同参画局の広報誌「共同参画」の昨年2021年5月号の特集タイトルだ。「無意識の偏見・思い込み」を意味する「アンコンシャスバイアス」。「文系出身の社員は計算が苦手だから…」「女性社員は子育てがたいへんだから…」といった思い込みが円滑な対人関係に水を差すこともあるが、はたして、そうしたアンコンシャスバイアスを企業内の組織において減らす方法はあるのだろうか? 管理職・マネージャー向けの「アンコンシャスバイアス研修」を受けて、考えてみた。

上司と部下の「タテ」関係から、「ヨコ」「ナナメ」へと広がった対話がもたらした驚くべき成果――1on1先進企業に学ぶ(2)日清食品ホールディングス
「1on1×企業内大学」で、内省と学びを加速!日清食品ホールディングスが実現したタテ・ヨコ・ナナメの対話の驚くべき成果とは?
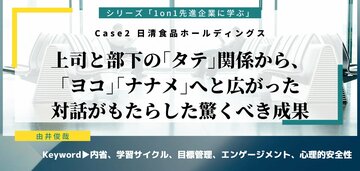
第7回
M&A後の組織づくりで「対話の場」をどうデザインするか?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した(レコフデータ調べ)。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くはM&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳 編著、東南裕美・柴井伶太・佐藤聖 著、ダイヤモンド社刊)の中から、人と組織を統合する際の課題やアクションについて紹介していく。今回のテーマは、M&A後の組織づくりで「対話の場」をどうデザインするか?

自律型人材の育成につながる“パーパス・ドリブンな組織”の作り方
近年、「パーパス」は、ビジネスシーンで耳にするようになったキーワードだ。コロナ禍による社会変容やSDGsが提示されたことで、会社の軸となり、方向性を決める「パーパス」の重要度はいっそう高まっている。『パーパス・ドリブンな組織のつくり方』(共著/日本能率協会マネジメントセンター)を刊行したアイディール・リーダーズ株式会社の後藤照典氏(COO)は、パーパス・ドリブンな組織となることでエンゲージメントの向上や自律型人材育成、ダイバーシティの実現などにおいて大きなメリットがあると語る。いま、なぜ、「パーパス」が求められているのか、そして、その効果について聞いた。
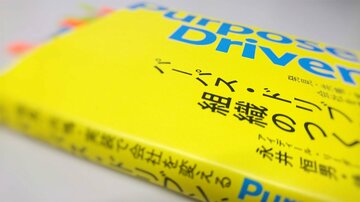
23卒採用の選考で、経営者や人事担当者がハマりがちな落とし穴
2023年3月卒業予定者(以下、23卒生)をメインにした、企業における採用選考が進んでいる。すでに同時期の就職内定(内々定)率が前年を上回っているという民間調査のデータもあるが、これから6月頃までが採用選考のピークで、対面やオンラインによる最終面接が行われていくだろう。そうした一連の採用活動の過程で、企業の経営者や人事担当者がハマりがちな落とし穴は何か? 多業種の企業と深くかかわり、インターンシップのプロデュースをはじめ、人材採用から育成までのコンサルティングを手がけている福重敦士氏(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース HD首都圏営業局・局長)に話を聞いた。

“部下とどんな話をすればいいのか”悩むリーダーの意識を180度変えた研修の正体――1on1先進企業に学ぶ(1)パナソニック ソリューションテクノロジー
“部下とどんな話をすればいいのか”と悩む上司の意識が180度が変わった!パナソニック子会社が導入した研修の正体とは?
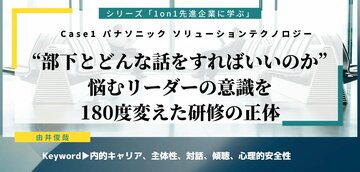
第6回
M&A後の組織・職場づくりに、なぜ「対話」が効果的なのか?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した(レコフデータ調べ)。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くは、M&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳 編著、東南裕美・柴井伶太・佐藤聖 著、ダイヤモンド社刊)の中から、人と組織を統合する際の課題や具体的なアクションについて紹介していく。今回のテーマは、M&A後の統合プロセスで「対話」の機会を持つことがなぜ効果的なのか?

アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第3回をお届けする。

第5回
M&Aの目的とビジョンを社員にどのように伝えるか?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した(レコフデータ調べ)。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くはM&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳 編著、東南裕美・柴井伶太・佐藤聖 著、ダイヤモンド社刊)の中から、人と組織を統合する際の課題やアクションについて紹介していく。今回のテーマは、M&Aの目的とビジョンを、M&A後の統合(PMI)プロセスで社員にどのように伝えるか?

第4回
M&Aの目的とビジョンを統合前に改めて明確にする理由とは?
人と組織を統合する際の課題やアクションについて紹介していく本連載。今回は、M&A前夜に取り組むアクションの一つとして、「目的とビジョンの明確化」について解説する。

制作のプロフェッショナルが教えてくれた、「研修動画」に絶対欠かせないもの
コロナ禍で、オンラインによる研修やセミナーが増え続けている。テレワーク中の従業員が、eラーニングの「動画」をオンデマンドで提供されることも多いようだ。そうしたなか、創業から18年で、世界・日本を代表する2000社以上の、計5万本を超えるBtoB動画を制作し、配信支援を行っている企業がある――株式会社ヒューマンセントリックス。起業時のエピソードとともに、BtoB動画に特化する理由や動画制作のテクニックなどを代表取締役の中村寛治さんに語っていただいた。

心理的安全性の高い組織とは?「うちの会社は変わらない」を変える組織文化のつくり方
心理的安全性の重要性が叫ばれるが、そもそも組織文化とはつくれるものなのだろうか?心理的安全性の専門家、デジタル庁の人事担当らが集い、その方法論について議論する。

第3回
M&A後の組織・職場づくりの視点とは?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くは、M&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳ほか著、ダイヤモンド社)の中から、人と組織を統合する際の課題やアクションについて紹介していく。今回のテーマは、M&A後の統合プロセスに「組織づくり」の視点をいかに取り入れるか。

人的資本経営のカギとなる “アルムナイ”の可能性と“辞め方改革”
近年、企業経営において急速に注目されているキーワードが「人的資本」だ。人材を「資本」としてとらえ、その価値を最大限に引き出すことで、中・長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方は「人的資本経営」と呼ばれる。この「人的資本経営」にはさまざまなアプローチがあるが、なかでもカギを握るのが「アルムナイ」との関係である。「アルムナイ」は、退職者の再入社・再雇用との関係で考えられがちだが、その効果は人事戦略全体に及ぶ。2017年からアルムナイ専用のクラウドシステムを提供している株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員の鈴木仁志さんに、「アルムナイ」の本質と可能性について話を聞いた。
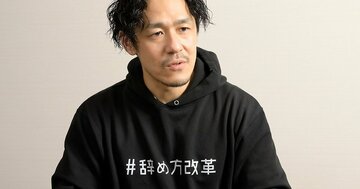
第2回
M&Aはなぜ社員に葛藤をもたらすのか?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した(レコフデータ調べ)。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くは、M&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳 編著、東南裕美・柴井伶太・佐藤聖 著、ダイヤモンド社刊)の中から、人と組織を統合する際の課題やアクションについて紹介していく。今回のテーマは、M&Aに伴うトランジション(移行)をどのようにマネジメントするか。

第1回
M&Aを失敗させる「人と組織」の問題とは?
日本企業のM&Aが急増しており、2021年は過去最多の4280件を記録した。しかし、M&Aの成功率は思いのほか低く、その原因の多くは、M&A後の統合プロセスにおける「人と組織」の問題にあると言われている。この連載では、人材開発・組織開発の専門家が著した最新刊『M&A後の組織・職場づくり入門』(齊藤光弘・中原淳 編著)の中から、人と組織を統合する際の課題や具体的なアクションについて紹介していく。

ジェンダーギャップを乗り越えるために今すべきこととは――資生堂と日本IBMが取り組むD&I
資生堂と日本IBMはいかにして女性リーダーの活躍を促進したのか? 企業が本気でダイバーシティ&インクルージョンに取り組む方法を、岡島悦子氏と浜田敬子氏が解説。

ブラック企業対応、管理職の利用……「退職代行」に人事部はどう向き合っているか
企業における従業員の「退職」の意思を、従業員本人に代わって企業側に伝える「退職代行」。近年、その請負業者とサービスの利用者が増えている。「退職代行」の背景にある労働環境は? 企業の人事担当者はどのように「退職代行」の通知に向き合っているのか? 現在の問題点は何か?――退職希望者のさまざまな相談を受け、「退職代行」の豊富な経験を持つ弁護士の竹内瑞穂さん(第一東京弁護士会)に話を聞いた。

「優秀さの罠」から抜け出したマネジャーが、組織の中で見つけたもの
自分の視点や考え方を変えることはなかなか難しい。特に、幼少期に無自覚に獲得した物事の見方や感じ方・行為のあり方は、知らず知らずのうちに仕事にも影響を与えていく。多様な人材が一堂に会する時代――偏った経験による価値観を変容させながら“個と集団の成長”を促すためには、誰がどうすればよいのか? 米国の社会学者ジャック・メジローが提唱した「変容的学習論」をもとに考えてみよう。
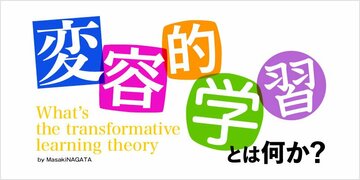
なぜ、企業はダイバーシティ&インクルージョンを推進しているのか?
2010年代の半ばから、“ダイバーシティ推進室”を設置する企業が増えている。「ダイバーシティ&インクルージョン」「ダイバーシティ・マネジメント」……そもそも“ダイバーシティ”とは何か? なぜ、人事施策のキーワードになっているのか? 経済産業省が推し進める「ダイバーシティ経営」の実践は、誰がどう行うべきなのか? ダイバーシティ&インクルージョンやリーダーシップ開発をテーマに研究・教育活動を行っている酒井之子さん(桃山学院大学ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科 特任准教授)に話を聞いた。