記事一覧
就活生たちが、“就活で使いたい手帳”を、制作のプロと一緒に創った!
今年も残り1カ月を切り、新しいスケジュール帳に来年2022年の予定を書き込んでいる人も多いだろう。デジタルツール全盛でも、アナログな“紙の手帳”は廃れることがなく、多岐にわたるスケジュールを一覧でき、通話中に書き込むことのできる“紙の手帳”は、就職活動における学生の必須アイテムでもある。そうしたなか、“就活を行う学生による、就活生のための手帳”が誕生した――「シン・就活手帳」。その企画から完成までの模様を「HRオンライン」がレポートする。

ウィズコロナの状況であらためて浮き彫りになった「1on1ミーティング」の真価
リモートワークの常態化に伴い、社内コミュニケーションが課題となる企業が急増している。100社に1on1を導入してきた由井俊哉氏が語る、ウィズコロナ時代にこそ必要な1on1の5つのポイントとは?

すべてを「粉々」にする覚悟はあるか?DXで国と企業が身につけるべき考え方とは
「世界デジタル競争力ランキング」において27位と低迷する日本において、DX推進のために国や企業は何をすべきなのか? ヤフーCSOの安宅和人氏、デジタル庁デジタル監の石倉洋子氏らが集ったONE JAPAN CONFERENCE 2021での議論をお届けする。

生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか
学生をはじめとした若者たちはダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はD&Iを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第1回をお届けする。

問題は「意思決定力の圧倒的不足」!これからの管理職が生き残るための学びの形
変化を起こせない組織に共通するのは、「意思決定力」の圧倒的不足!震災や新型コロナウイルスなど危機が続き、VUCAと呼ばれる時代で生き残るため、組織が求める管理職の要件とは?

男性社員の「育休」取得は、組織や企業をこれからどう変えていくのか
「“1割(10%)の壁”は高い」と言われ続けた男性の育児休業取得率が、昨年2020年の調査でついにその壁を越え、過去最高数値を記録した。政府のすすめる働き方改革が企業に浸透しつつあること、また、コロナ禍によって多くのビジネスパーソンが仕事と家庭のバランスを顧みるようになったことなどがその要因だろう。また、今年2021年6月には「育児・介護休業法」が改正され、「男性育休」を取り巻く状況は大きく変化しているようにも思えるが、育休取得を歓迎しない職場の雰囲気や取得する本人のうしろめたさ、平均取得日数の短さなど、課題は多いようだ。「男性育休」についての論考がある、ニッセイ基礎研究所の久我尚子さんにお話をうかがった。
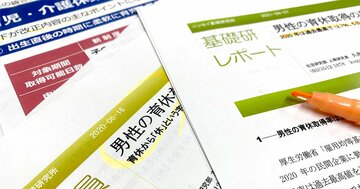
留職、価値観ババ抜き……有志活動と人事のコラボが切り拓く新しい可能性とは
1on1、越境、ティール組織……「変わらなきゃ」という気持ちばかり先行して、「外」ばかり見ていないか?本当の変革のタネはどこにあるのか、人事と連携して留職や価値観ババ抜きといった施策を「掘り起こして」きた東京海上の有志団体が明かす。

オープンイノベーションの成功確率をグンと上げる「スイッチの入れ方」
本業をこなしながら新規事業なんてムリ!と悩む人にこそ試してほしい「オープンイノベーション」成功のコツとは?

「社内文化」に染まらず客観的思考力を養成するための「3つの円」とは?
社内文化を重視するあまり「社内文化至上主義」に陥っていませんか? 社員一人ひとりが社内外を広く見渡せる「客観的思考力」を養成するための必須スキル、「社会と個人の直結回路」とは?

55社3000人が実証!なぜ大企業の若手中堅のスキルが“大企業病”に効くのか?
大企業55社の若手中堅3000人が集う実践コミュニティ、ONE JAPAN。入山章栄氏や篠田真貴子氏、中原淳氏ら各界のオピニオンリーダーもこぞって注目する彼らが何を成し遂げてきたのか、熱い想いとともに迫る。

株式会社TOKIO城島茂社長が語る、事業承継と会社にとって大切なこと
日本の企業の99.7%を占める中小企業だが、いま、全国各地で、その後継者不足が問題になっている。経営者の高齢化が進み、およそ半数の事業者が“後継者未定”という調査データもある。後継者が見つからない理由から休廃業・解散の道を選ぶ企業も多く、然るべき「事業承継」が望まれる状況だ。先月(2021年10月)スタートした番組「社長、城島茂と学ぶ事業承継~その企業の熱意と決意~」(BSフジ)でナビゲーター役を務める株式会社TOKIOの城島茂社長に、事業承継と株式会社TOKIOについての話を聞いた。

早期離職の防止にもなる、「経験学習」での新人教育のノウハウ
「経験学習」による人材育成方法において、総合物流企業・センコー株式会社を核とするセンコーグループホールディングス株式会社(本社・東京都江東区)の取り組みは他社の大きな指針になるだろう。経験学習の肝となる「内省」は従業員にどのような気づきを与えるのか。また、経験学習のサイクルをまわす「経験学習ノート」の仕組み、新人教育でのOJTリーダーの役割、1on1ミーティングのサーベイとそのフィードバックとは? 同社人材教育部・秋山政泰部長に話を聞いた。

ウィズコロナで価値を高める新横浜の“大型研修施設”――その魅力を探る
2020年初頭から続く新型コロナウイルス感染症の拡大で、企業・団体の新入社員・管理職をはじめとした従業員向け研修もオンラインが主流になりつつある。人と人がリアルな空間で対面しづらい時代に、企業が持つ大型研修施設はどうなっているのだろう。グループ売り上げ11兆448億円(2021年2月期)、約13万5000人の従業員(グループ連結)が就労するセブン&アイグループ――その伊藤研修センターを訪ね、高木剛センター長に話を聞いた。

採用面接では「自己肯定感」と「自己効力感」のどちらに注目するべきか?
「自己肯定感」「自己効力感」という言葉をよく耳にするようになった。しかし、「肯定」も「効力」もその尺度が分かりづらく、「自己肯定感」や「自己効力感」が「高い」ことにどのような意味を見出すかは人それぞれのようだ。たとえば、新入社員の面接試験における「自己肯定感」の判断は? たとえば、企業・団体の人材育成における「自己効力感」の価値は? 教育再生実行会議における言葉の定義などから、いま改めて、「自己肯定感」と「自己効力感」について考えてみよう。

定年年齢になったシニアが、仕事の“適性検査”を受けて気づいたこと
超高齢化社会のニッポン――2013年の「高年齢者雇用安定法」の改正で、65歳までの雇用確保が義務化(65歳定年制)され、2025年4月からは65歳定年制が全企業に適用される。再雇用を含めて、65歳以上でも働けるような令和の時代に、シニアが仕事の“適性検査”を受けて、「自分のパーソナリティを知り、自分に合った職を見つけること」は一般的になるかもしれない。そもそも、新卒などの採用時に行われる“適性検査”とはどういうものなのか? それをシニアが受検することで、企業の人事部と本人に生まれる気づきは何か?
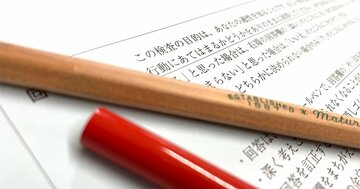
「オンライン読書会」で内定者同士のつながりと連帯感を強める
集まれない時代の内定者フォローの一環として、内定者向けにオンライン読書会を開催する企業が増えつつある。なぜ、オンライン読書会が、対面での懇親会や食事会に代わるコミュニケーション手段となり得るのか。どのようなメリットが見込めるのか。昨年度からオンライン読書会を企画・実施している武蔵野銀行 人事部キャリア開発室の柿島秀之氏にお話をうかがった。

「健康経営」の落とし穴は?企業が忘れてはいけない3つのポイント
コロナ禍では、多くの企業が、事業所での感染対策はじめ、リモート勤務やワクチン接種などさまざまな取り組みを通して従業員の健康確保の重要性を再認識している。今後も「従業員の健康」をどのように守るかが各方面から問われることは間違いない。しかし、企業による「従業員の健康確保」は、法律や規制への対応に終始し、医師や保健師といった専門家に任せるだけといったケースも少なくない。産業医・労働衛生コンサルタントとして就労者の現場の声に精通し、ITを活用した健康管理クラウドサービスを提供する株式会社iCAREの山田洋太氏(代表取締役CEO)に、人事戦略としての「健康経営」の課題について話を聞いた。

人事部も働く人も幸せになる「ハイスキル人材の時短派遣」とは?
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大が私たちの働き方のスタイルをその価値観とともに変えつつあるなか、 “派遣スタッフ”を積極的に受け入れる企業が増えている。なかでも、専門的な知識やスキルを持つ人材の活躍が目立っているようだ。そうした“派遣”の就労スタイルのひとつである「ZIP WORK」とはいったいどのようなものか――運営元である株式会社リクルートスタッフィングの路川千晴さんをインタビューした。
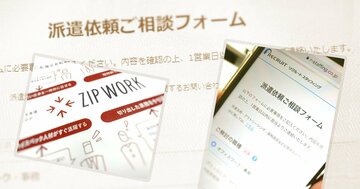
いま、企業の人事部が知っておきたい“コロナ禍の大学生の悩みと不安”
毎年、約65万人が入学し、現在、全国で約250万人の大学生がいる。「キャンパスライフ」という言葉が明るいイメージを持ち、大学に進学し、キャンパスに通うことは前向きな人生のワンシーンに思えるが、新型コロナウイルス感染症による「暮らし方・学び方の変化」が、若年層のメンタルや就学・就職観に波及している。大学生活への不満、将来に対する不安――書籍『大学生活、大丈夫? 家族が読む、大学生のメンタルヘルス講座』の著者である梶谷康介さん(九州大学 キャンパスライフ・健康支援センター 准教授)に、コロナ禍にある大学生たちの実状を聞いた。
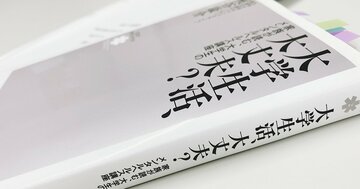
就活生の「内定辞退」をなくすため、面接官の誰もができるシンプルなこと
22卒(2022年3月卒)の大学院生・大学生の採用活動が9月以降も続いている。すでに学生への内定を出し終え、10月1日の「内定式」を迎える企業も多いが、「秋採用」はこれからが本番だ。特に、知名度の低い中小企業は、採用面接の方法やその後の「内定者フォロー」が、人材獲得の生命線になる。先月配信記事の『さまざまな「内定者フォロー」で、企業の採用担当者が必ず心がけたいこと』に続き、採用コンサルタント/採用アナリストの谷出正直氏に、中小企業が良い人材を獲得するための方法を聞いた。

