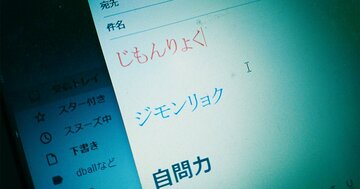記事一覧
誰もが明日から実践できる「辞め方改革」が、あなたと企業を幸せにする理由
「人的資本経営」のカギを握る「アルムナイ」。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性がますます高まるこれからの時代において重要だ。アルムナイ専用のクラウドシステムを提供するなど、アルムナイに関する専門家である鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)が、企業の「辞められ方」、従業員の「辞め方」を語る連載「アルムナイを考える」――その第2回をお届けする。
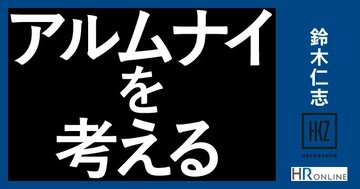
いまとこれから、大学と企業ができる“インクルージョン”は何か?
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第5回をお届けする。

“就職人気企業ランキング”の変遷で知る、学生の動きと採用活動のヒント
毎年、新聞系のメディアや人材紹介会社によって“就職人気企業ランキング”が発表されている。なかでも、株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソースの“就職人気企業ランキング”は、文系男子・理系男子は1978年から、文系女子・理系女子は1999年から続き、最も長い歴史を持っている。同社・経営企画室長の高村太朗さんへのインタビューを通して、ランキングの変遷から浮かび上がる学生の動向と採用活動のヒントをまとめてみた。

企業の“両立支援”を実現する、産業医と総務・人事部のチームワーク
今年2022年4月に「育児・介護休業法」が改正され、従業員が仕事と家庭生活を無理なく両立できるように、企業にはよりいっそうの努力が求められるようになった。しかし実際のところ、 “両立支援”がなかなか行き届かず、不満を持つ従業員も少なくない。ビジネスパーソンの心身の健康をサポートする産業医から見て、企業の“両立支援”の本質や課題はどこにあるのだろうか。大企業から中小企業まで、さまざまな総務・人事部との接点がある心療内科医・産業医の内田さやか先生(ビジョンデザインルーム株式会社・代表)に話を聞いた。

「プレゼンテーション研修」で、“相手を動かす”テクニックを学んでみた
相手に、正しく分かりやすく伝えること――コロナ禍の“オンラインコミュニケーション”で、その大切さを多くの人が知った。プレゼンテーションやセールスプロモーションを行うビジネスシーンでも、「正しく分かりやすく伝えること」が仕事の結果を左右する。しかし、オンラインコミュニケーションのテクニックは、あまり語られることがなく、人から学ぶことも多くないだろう。書籍『プレゼンは「目線」で決まる』の著者・西脇資哲さん(日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員/エバンジェリスト)による「プレゼンテーション研修」を受けてみた。
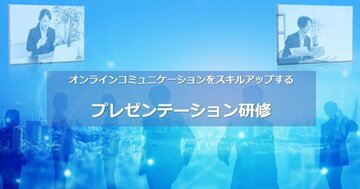
「教え上手」と「学び上手」の社員が組織をどんどん変えていく
2022年4月の新卒社員の入社から3カ月以上が経った。配属先も決まり、すでに組織の一員として活躍している新人も多いだろう。そうしたなか、「部下をどう教育したらいいのか分からない」「テレワークではなく、出社して、背中を見て覚えてほしい」といった管理職や「先輩社員や上司とのコミュニケーションの取り方がうまくできない」という新入社員の声を聞く。仕事は“教え方と学び方”が何よりも大切――企業・団体への数多くの研修を通じて、そのことを伝え続けている関根雅泰さん(株式会社ラーンウェル 代表取締役)に話を聞いた。

「報酬は、成果給ではなく“期待給”」、稀代の経営者が掲げる異色の人事改革「7つの施策」
「人事改革は、企業再生の要」――そう語るのは、大胆な経営改革によって寺田倉庫を復活へと導き、経営者のファンも多い中野善壽さんだ。2021年8月には、赤字経営に苦しむ熱海の老舗リゾート、ACAO SPA & RESORT(旧:ホテルニューアカオ)代表取締役会長CEOに就任し、「ACAO SPA & RESORT」としてリバイバルに挑む。いったいどんな人事改革を構想しているのか。すでに着手を始めたという「7つの施策」について聞いた。

ミレニアル世代の働きやすさのために、いま、企業は何をすればよいのか
女性活躍やダイバーシティマネジメント、仕事と生活の両立推進など……雇用環境の整備から経済社会発展への寄与を目的とする公益財団法人21世紀職業財団が、「子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究」を今春に発表した。ミレニアル世代は、現在27~41歳(1980~1995年生まれ)の年齢層で、男女雇用均等法の第1回改正(1999年施行)後に就職した、法規上における“男女平等”で働き始めた世代だ。調査研究から見えた、 子どものいるミレニアル世代などの動向について、同財団の山谷真名さん(上席主任・主任研究員)に話を聞いた。
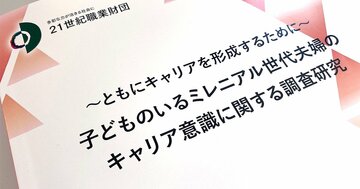
「退職したら関係ない!」はあり得ない――適切な「辞められ方」「辞め方」を考える
「人的資本経営」のカギを握る「アルムナイ」。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性がますます高まるこれからの時代においてとても重要だ。アルムナイ専用のクラウドシステムを提供するなど、アルムナイに関する専門家である鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)が、企業とビジネスパーソンの間に起こる「辞められ方」「辞め方」を語る。
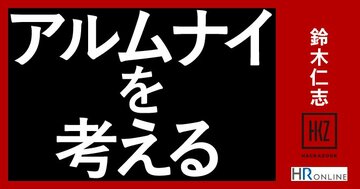
“1on1を実りある場にするには?”組織風土を変えるために必要なのは、マネジャー同士の「ヨコ」のつながり――1on1先進企業に学ぶ(3)リクルート
マネジャー同士のヨコのつながりなくして、組織風土改革なし!?リクルートの絶えざる実践が教えてくれる、1on1の最新活用法とは?
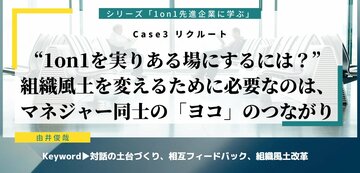
JTBは、さまざまな研修を社員の“行動変容”にどうつなげているのか
オンラインでのサービスはもちろんのこと、国内で300店舗以上の窓口を持ち、さまざまな「旅行体験」をそれぞれの消費者に提供している、国内ツーリズム産業最大手の株式会社JTB。「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する。」を経営理念とし、その数多(あまた)の事業を支えているのは、社員一人ひとりが持つ「人間の力」だという。グループ従業員約2万名にも及ぶ人材の育成はどのようになされているのか? グループ本社 人財開発チーム 人財開発担当部長 中村彰秀さんに話を聞いた。

別企業の新入社員たちが、ひとつの研修で一緒に学ぶことの価値
今年2022年の4月も学校卒業者の多くが社会に飛び立った。就職した大卒者は約43万人――「22卒」である彼ら彼女たちのほとんどは、2020年の夏に企業のインターンシップを経験し、2021年に採用面接を受けた「コロナ就活」の経験者たちだ。新入社員として企業に入り、どのような研修を受けて、社会人の心得を身につけていくのか。都内で2日間にわたって対面で行われた、“公開型”新入社員研修の様子を「HRオンライン」がレポートする。
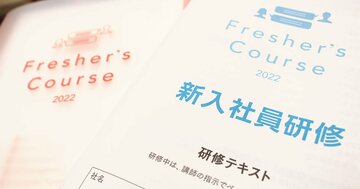
学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第4回をお届けする。
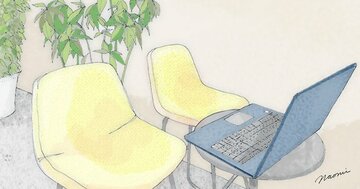
“24卒採用”に向けたインターンシップで、企業が気をつけたいこと
企業による、来年2023年3月卒業予定者(現在、主に大学4年生)の採用選考が続くなか、2024年3月卒業予定者(現在、主に大学3年生)を対象としたインターンシップが始まる。新卒採用におけるインターンシップの重要性が高まるとともに、コロナ禍によるオンライン化や短縮化など、その形式や内容も変化してきており、インターンシップの方法や運用の巧拙が各企業の採用活動全体に影響を与えかねない――多業種の人事担当者と深くかかわり、インターンシップのプロデュースをはじめ、人材採用から育成までのコンサルティングを手がけている福重敦士さん(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース HD首都圏営業局・局長)に話を聞いた。

「経験学習」とは何か?新入社員が“仕事上の直接経験”で成長する方法
4月入社の新入社員が、それぞれの組織に配属されていく季節だ。人事部の手を離れ、各部門に飛び立った彼ら彼女たちをしっかり成長させていくために、人材育成の手法のひとつである「経験学習」を回していく組織も多いだろう。そこで改めて、「経験学習とは何か? 新人をはじめとしたビジネスパーソンが、経験学習を身につけるために教育担当者や管理職はどうするべきか?」を考えてみる。

組織の意思決定に「真善美」の3ステップが効く理由
ルールを設計するだけでは「組織の意思決定」は損なわれる!?1万人の経営者と対話を繰り返し、高エンゲージメント・低ストレスの組織を実現した注目の社長が明かすよりよい意思決定のための3ステップとは。
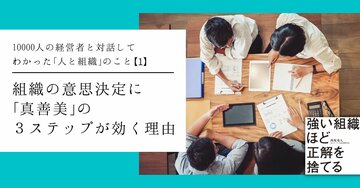
地方の“創業100年企業”で、なぜ、外国人が生き生きと働き続けるのか?
現在、日本では約170万人の外国人が働いている。街なかの店舗、建築現場、工場、企業のオフィス……外国人の就労がダイバーシティ社会をかたちづくり、企業経営者や管理職には、その適切なマネジメントが必要とされている。多人数の外国人の雇用で躍進している老舗企業が山形県の山形市内にある――スズキハイテック株式会社。「新・ダイバーシティ経営企業100選」(令和2年度・経済産業省)にも選ばれた同社は、どのように外国人の従業員に向き合っているのか。「HRオンライン」が現地を取材し、代表取締役の鈴木一徳さん(5代目社長)に話を聞いた。

“フルリモートワーク”という働き方で、チームが最大の成果を得る方法
働き方改革やダイバーシティ&インクルージョンの実現が社会課題となっているいま、国内だけではなく、世界各地に在住するメンバーがチームになり、“フルリモートワーク”で業務に取り組んでいる企業がある。2015年にオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」の提供を始めた、株式会社ニットだ。同社は、新型コロナウイルス感染症拡大のずっと前からフルリモートワークを取り入れ、個々のメンバーに応じた就労を実現させている。企業理念は「『働く』を通じて、みんなを幸せに」――広報チームリーダーの小澤美佳さんに話を聞いた。

体制づくりと必然性と……企業の「研修内製化」に、いま必要なものは何か?
「研修内製化」――企業・団体が、外部の研修提供会社に委託して自社の従業員に「研修」を行うのではなく、自社内で研修コンテンツを作り、人事部などが企画・運営するというもの。しかし、「内製」に明確な定義はなく、研修提供会社が作ったコンテンツを、自社用にカスタマイズする方法などもある。内製と外注、オンラインと対面……コロナ禍において、企業の研修はどう変わってきているのか? オンラインでの研修は、「内製」にどう影響しているのか? 「社内講師養成コンサルタント」として活動中の鈴木英智佳さん(株式会社ラーニング・クリエイト 代表取締役)に話を聞いた。
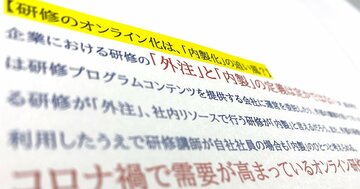
リモートワークでの「自問」習慣が、自分自身とチームを成長させていく理由
内閣府の調査では、コロナ禍におけるテレワークのデメリットとして「気軽な相談・報告が困難になった」という就業者が目立っている。自室において、ひとりで仕事に向き合っていれば、「何のために働いているのか?」「どうしてこんなに忙しいのか?」と「自問」することもあるだろう。新入社員研修や管理職対象のリーダーシップ研修などで、さまざまな悩みやリアルな声を聞いている、講師ビジョン株式会社・代表取締役の島村公俊さんは、そうした「自問」こそが自分自身と組織(チーム)を成長させていくと説く。