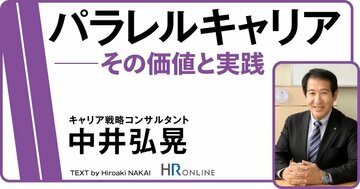記事一覧
【ミュージカル研修(前編)】入社3年目社員が、チームで物語を創り、歌って踊って、気づいたことは何か?
自動車に関する複合的なサービス(カーライフのトータルサポート)を行うプレミアグループは、2007年の創業からわずか10年で東証二部に上場(翌2018年12月に東証一部へ市場変更、現在はプライム市場へ移行)し、躍進を続けている。同グループのエンジンとなっているのが「人」だ。2020年には、グループ役職員を対象とした研修を企画・実施する会社として、株式会社VALUEを設立。「常に前向きに、一生懸命プロセスを積み上げることのできる、心豊かな人財を育成します」というMISSIONを掲げて、“人財”を輩出している。そのユニークな研修のひとつ“バリューミュージカル研修”を「HRオンライン」がレポートする。

適切な“管理職コーチング”で、上司と部下はどう変わっていくか?
コロナ禍を経てのリモートワークの一般化、さまざまなハラスメントが生じるリスク――管理職やマネジャー、上司が、部下を育成しづらい時代になっている。一方で、人的資本経営が重視され、人を育て、就労者のワークエンゲージメントを上げ、離職率を下げていくことが組織に課せられた重要なミッションになっている。どうすれば、上司と部下の幸せな関係がつくれるのか? “教え上手なマネジャー”たちへのインタビューを実践し、定性&定量データから導き出した「管理職コーチング」の手法とは? 書籍『管理職コーチング論 上司と部下の幸せな関係づくりのために』の著者である永田正樹さんが説いていく。
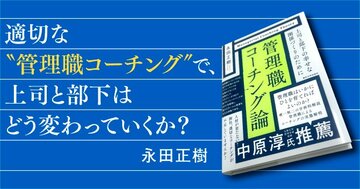
人と人の信頼関係をつくる“フィードバック”――その6つのポイント
元NHKキャスターとして「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」などに出演し、現在はフリーアナウンサーとして多方面で活躍する牛窪万里子さん(株式会社メリディアンプロモーション代表取締役)。牛窪さんは、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』をはじめ、多くのビジネス書も執筆するなど、言葉と表現によるコミュニケーションのプロフェッショナルだ。そんな牛窪さんによる連載「いま必要な“組織を活性化する”コミュニケーション」の第2回をお届けする。
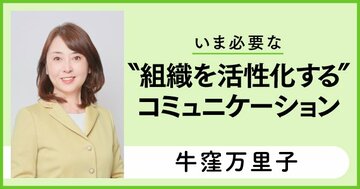
いま、企業が、“ITエンジニア・DX人材の求人募集”で知っておきたい重要なこと
かつて、日本の企業の多くは、システムの開発をSIerなどに発注していたが、昨今は「内製化」の傾向が高まっている。一方で、ITエンジニアやDX人材は超売り手市場で「思うような人材を獲得できない」という人事担当者の悩みを聞く。自身が元エンジニアであり、人材エージェント会社で2000名以上のエンジニアの転職をサポートし、現在、HRコンサルティングサービスや採用業務代行(RPO)サービスを提供する芦川由香さん(株式会社レイン CEO)が「ITエンジニア・DX人材のキャリアと採用事情」について筆を執る。その第1回は、「ITエンジニア・DX人材の転職の実態に関するアンケート」から見えたこと。

韓国の大手企業が知的障がい者の劇団と取り組んだ研修――その目的とは?
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっているとい言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第17回をお届けする。

新入社員を成長させる、日本光電の“エルダー制度”と“経験学習”の仕組み
医療機器の開発・製造・販売を行う日本光電工業株式会社は、1951年の創業以来、「エレクトロニクスで病魔に挑戦」をモットーに、さまざまな医療機器を世界各地の医療現場に提供している。人に寄り添った“モノづくり”を行う同社は、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出すことを念頭に、「人材」を「人財」とし、その育成に力を注いでいる。新人1人に対し、1名の育成指導担当者がつく「エルダー制度」はどのようなものか? 人財育成の根幹をなす経験学習のサイクルをどう回しているのか? 同社グローバル経営管理本部フェニックス・アカデミー副所長の茂木順子さんと人財開発本部フェニックス・アカデミー研修チームリーダーの髙木綾香さんに話を聞いた。

メンバーシップ型の日本企業こそ、アルムナイ・リレーションシップをつくる意味がある
「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が注目されている。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係(アルムナイ・リレーションシップ)を築いていくかは、人材の流動性が高まっている時代でことさら重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続き、昨年(2024年)には著書も発表した、「アルムナイ」知見についての第一人者・鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)による、「HRオンライン」連載=「アルムナイを考える」の第9回をお届けする。
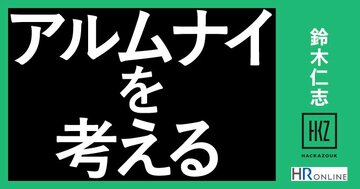
“副業”ではない、 “活私奉公型のパラレルキャリア”が、個人と組織の未来を創っていく
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、パラレルキャリアを改めてタイプ分けし、副業との違いを考えたうえで、個人と組織にもたらす効果を考える。
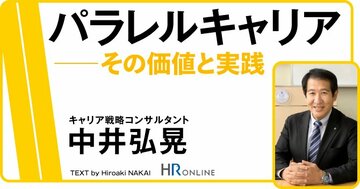
学生たちの「長所」を伸ばしていく、埼玉大学の「VSAT」とキャリア支援
学生のキャリア教育と就職支援において、国公立大学は人員や予算が不足しがちである。そうしたなか、独自のアセスメントテストを開発したり、地域のさまざまな企業が参加する産学連携のプログラムを設けたり、と意欲的な取り組みを行っているのが埼玉大学だ。同大学はさいたま市にある埼玉県内唯一の国立大学で、ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏や作家・詩人である池澤夏樹氏の出身大学でもある。そんな埼玉大学のキャリア支援を先頭に立ってリードしている石阪督規教授(キャリアセンター長)に意欲的な取り組みの内容を伺った。

2024~2025年の“トレンドワード”に見る、いま、人事担当者が行うべきこと
企業の人事担当者に向けて、意思決定に役立つ情報発信を続けるパーソル総合研究所では、2022年から毎年12月に「人事トレンドワード」を発表している。過去2回は、パンデミックの影響を受けた働き方や価値観の変化、デジタルトランスフォーメーション(DX)や生成AIなどに関連したワードが並んだが、3回目となる2024~2025年のトレンドワードには「カスハラ対策」「スキマバイト」「オフボーディング」の3つが選ばれた。こうしたトレンドワードが生まれた背景は何か? そして、人事担当者はどのように受け止め、施策に活かすべきか? 「人事トレンドワード」企画の発案者でワード選考の責任者を務める同研究所の上席主任研究員・小林祐児さんに話を聞いた。

人事部が自社に合ったIT人材を採用し、会社全体のITリテラシーを高める方法
経済産業省が2018年に「2025年の崖」という表現で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性を説いてから7年。コロナ禍で多くの企業のIT化は進んだものの、民間企業の最新調査によれば、DXに関して、「十分な成果が出ている」と答えた企業は10%程度にとどまっている。その理由のひとつに、各企業における、IT・DX人材の不足があるだろう。そもそも、IT人材とDXを行う者は異なるのか? なぜ、自社でエンジニアを含むIT人材を雇用する必要があるのか? DXを推進する企業は、どのような人を採用し、どう向き合っていけばよいのか? エンジニアとして社会人生活をスタートし、人材エージェントの大手で2000名以上のエンジニアの転職をサポート――その後、起業し、現在は、HRコンサルティングサービスなどを展開している、株式会社レイン(LeIN) CEOの芦川由香さんに話を聞いた。

若手・中堅・シニアの“ジョブ・クラフティング”を、企業はどう支援すればよいか
人的資本経営の推進が求められるなか、多くの企業でエンゲージメントの向上が重要課題となっている。その解決手段として、従業員が働きがいを自ら高める“ジョブ・クラフティング”への注目度が高まっている。ジョブ・クラフティングとは何か、企業はジョブ・クラフティングをどのように支援するべきか――2024年6月刊行の書籍『50代からの幸せな働き方 働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』の著者であり、ジョブ・クラフティング研究で著名な高尾義明さん(東京都立大学大学院経営学研究科 教授)に話を聞いた。

売り手有利&早期化が進む就活戦線――“新卒採用の課題”は何か?
2025年3月卒業予定者(以下、25卒)の新卒採用市場では、売り手有利の状況や内定(内々定)出しなどの早期化がさらに進んだ。このトレンドは今後も続くと思われるが、昨年度(24卒採用)からの微妙な変化も伺える。各企業の採用担当者は26卒採用に向けて、25卒採用をどのように振り返っているのだろうか。例年、独自のアンケート調査に基づき、『学生の就職活動総括』『企業の採用活動総括』を公表している株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソースの高村太朗さん(同社・経営企画室長)のインタビューを通して、採用戦略のポイントと課題について考えてみる。

“学び”での、「自分を成長させたい」思いと、「学習者に寄り沿う」大切さ
神戸大学には、文部科学省の委託を受けた実践研究の場として、全国の大学機関では珍しい授業がある。2019年からスタートした「神戸大学・学ぶ楽しみ発見プログラム」(KUPI=Kobe University Program for Inclusion)だ。これは、大学教育を知的障がいのある人に開いていく試みで、今秋、「HRオンライン」は、その授業の様子を見てきた。そして、「学ぶこと」「教えること」の大切さを実感し、「KUPI」の統括責任者であり、授業を受け持つ津田英二教授(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科)に話を聞いた。自分を成長させたい思いと、学習者に寄り沿うことの大切さとは?

“データドリブン人事”とは何か?外部に丸投げせず、自前で実現する方法――早稲田大学・村瀬俊朗さんに聞く
近年、企業内に蓄積されたさまざまなデータを活用し、より客観的な意思決定を目指すピープルアナリティクスなど、「データドリブンな人事施策」への注目が高まっている。ただし、その実践には課題も指摘されている。たとえば、人事チーム内に「データ分析の専門家」がいなければ、多くの企業はその作業を“外注”することになる。しかし、業者が提供するサーベイや分析ツールを活用しても、「分析結果を眺めて終わり」になってしまうケースも少なくないのだ。「本当に意味のある分析をしたいのなら、日本企業は“データドリブン人事の内製化”を目指したほうがいい」──そう指摘するのは、さまざまな企業とコラボレーションしながら、リーダーシップやチームワークの研究を日米で行ってきた早稲田大学准教授の村瀬俊朗さん。データに基づいた人事施策を「素人集団」が自前で実現するにあたっては、いったいどんな思考法が必要になるのか──? 具体的な成功事例とともに、そのコツを聞いた。

人事パーソンのリアルな悩みが表れた、『シン・人事の大研究』読書会
書籍『シン・人事の大研究 人事パーソンの学びとキャリアを科学する』が多くのHR関係者に読まれ、読者レビューでも好評だ。当書籍は、人事部門で働くビジネスパーソンたちの仕事・学び・キャリアを調査するプロジェクト『シン・人事の大研究』をまとめたもので、令和時代の人事パーソンの悩みや考え方がわかり、課題解決の気づきを読者にもたらしてくれる。そして、著者3人をゲストに招いた読書会にはさまざまな企業の人事担当者が集い、“人事仕事の現在”を共有した。「HRオンライン」が、その様子をつぶさにレポートする。

手軽になった動画ツールや情報は、私たちの学びにどのような影響を与えるか
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第15回をお届けする。

スマイリーキクチさんが語る、SNSのコミュニケーションで最も大切なこと
「スマイリーキクチ 人殺し ぶっ殺してやる」――タレントのスマイリーキクチさんは、10年以上にわたって、インターネット上で誹謗中傷され、当時の仕事をすべて失い、人生が一変した。現在、そんなスマイリーさんは、笑顔を絶やすことなく、メディアリテラシーの大切さやSNSのマナーを世の中に伝え続けている。コミュニケーションの齟齬が生じがちな人間関係において大切なものは何か? コロナ禍で学生時代を過ごしたフレッシャーズたちに、上司や先輩社員はどう接すればよいか? 姿の見えない相手と対峙した経験があるからこそ語れる“ネット社会の怖さ”、スマイリーさんならではの “他者を尊重する思い”に、「HRオンライン」が耳を澄ました。

報道現場から学ぶ、チーム活性化のための“3つのコミュニケーションスキル”
元NHKキャスターとして「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」などに出演し、現在はフリーアナウンサーとして多方面で活躍する牛窪万里子さん(株式会社メリディアンプロモーション代表取締役)。牛窪さんは、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』など、多くのビジネス書も執筆するなど、言葉と表現によるコミュニケーションのプロフェッショナルだ。そんな牛窪さん執筆の連載「報道現場から学び取る“組織を活性化する”コミュニケーション」をお届けする。
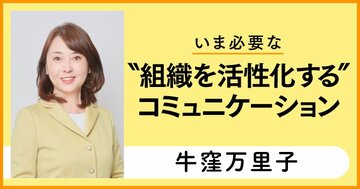
不本意な異動や出向……職場環境の急な変化で、キャリアを豊かにする方法
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、職場で起こりがちな不本意な異動が、キャリアにどう影響するかを考える。