記事一覧
形だけの「女性活躍推進」から脱却し、いまこそ「多様性」を戦力に変えるとき
「女性活躍推進」という言葉が世間に広がって久しいものの、管理職に占める女性の割合や男女の賃金格差には、いまだに大きな開きがある。数値目標を追うだけの登用ではなく、女性一人ひとりの能力を引き出し、組織の成長につなげるためには何が必要なのか。2008年から“女性のためのリカレント教育”を先駆けて実践し、長年にわたり、“女性のキャリア形成”について研究している関西学院大学の大内章子教授に、企業がいま向き合うべき「女性活躍推進」の本質について話を聞いた。

「アンコンシャスバイアス」のセルフラーニング動画を見て、私が気づいたこと
「あの人は育児中だから地方出張は嫌がるだろう」「外国籍の彼は日本人のマナーを理解しづらいにちがいない」――そんな思い込みで、対人関係にフィルターをかけてしまうことが職場で見受けられる。「無意識の偏見や思い込み」を「アンコンシャスバイアス」と呼び、企業・団体においては、「アンコンシャスバイアス」を研修によって理解し、減らしていく動きを進めている。そもそも、「アンコンシャスバイアス」とは何か? 働きやすい職場をつくるために心がけたいことは? 「アンコンシャスバイアス」のセルフラーニング動画から学んでみよう。
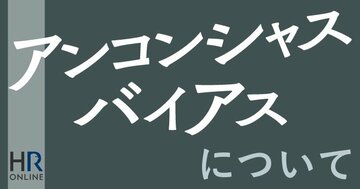
アナウンサーの武田真一さんが働くなかで見つけた“チーム”の理想のかたち
NHKでの“サラリーマン”生活に終止符を打ち、55歳でフリーランスとなったアナウンサーの武田真一さん。NHK時代から、「情報を正確に、安定して届ける」ことを自らのミッションに据え、派手さや自己主張よりもチームとしての成果を優先してきたが、新境地にあってもその姿勢は変わらない。「過去の経験から導いた“理想のチーム”にこだわるより、想像もつかなかった人材との出会いを楽しみ、チャンスととらえたい」――そう語る武田さんに、組織における自らの在り方や、チームビルディングのヒントについて聞いた。

職場につくられた「子ども図書館」が、働くみんなを幸せにする理由
コロナ禍を経た、2020年代半ばのいま、人事・総務といったバックヤード系の業務は多忙を極めている。従業員の勤怠管理から福利厚生に至るまで、積み重なる案件に追われ、時間を効率的に使うことを余儀なくされながら、従業員の「働きやすい職場」づくりに腐心する人事・総務パーソンが多いようだ。そうしたなか、働く人の心と体を休める「リフレッシュルーム」に「子ども図書館」を設置した職場がある。弥生株式会社の大阪オフィス(大阪カスタマーセンター/大阪支社)だ。いま、なぜ、「子ども図書館」なのか? その企画・運営をおこなう森嶋綾子さん(人事本部・人事総務部)を訪ねた。
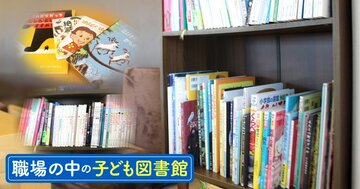
守島基博教授インタビュー【後編】「ジョブ型雇用、キャリア自律」で、人事担当者が目指すべきこと
これからの時代における“新しい「全員戦力化」”の手段として注目されているのが「ジョブ型雇用」だ。また、「全員戦力化」を社員の視点で見たときに欠かせないのが「キャリア自律」である。そうした意味で、「キャリア自律」は「ジョブ型雇用」と表裏一体のものといえるだろう。前回に続き、守島基博教授(学習院大学経済学部教授/一橋大学名誉教授)に、「ジョブ型雇用」と「キャリア自律」の関係について、さらに、“新しい「全員戦力化」”を実現するための人事部門の役割について、話を聞いた。

守島基博教授インタビュー【前編】人材不足時代における、“新しい「全員戦力化」”の方法とは?
VUCAが巷間に流布して久しいが、国内では出生数が70万人を切り、海外ではトランプ関税に加え、地政学リスクが高まるなど、不確実性がいっそう深まっている。こうした状況は企業の人事戦略にも大きなインパクトをもたらし、黒字ながらも人員整理に着手したり、新卒採用数を見直したりする動きがある。これは、人事部門が、「人事制度の管理者」から「人材戦略の司令塔」への役割転換を迫られていることに通じるだろう。その役割転換について、人的資源管理論を専門とし、政府の各種審議会委員なども歴任してきた守島基博教授(学習院大学経済学部教授/一橋大学名誉教授)へのインタビューを通して考えてみる。

著名タレントの事例から学ぶ、パラレルキャリアがもたらす“現代を生き抜く力”
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア,~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所,代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、3人の著名タレントが実践しているパラレルキャリアの事例を解説していく。
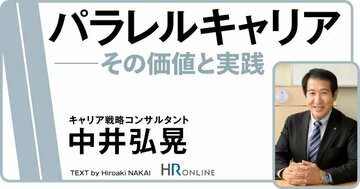
考え、迷い、また考え、また迷う――働き始めた新卒社会人に伝えたいこと
新卒者の就職活動における、早期化・長期化の傾向が強まり、多くの学生が、将来の就職先や仕事を意識して学業に向き合うなか、関西の総合大学に、雇用や労働について専門に学ぶ学科がある――同志社大学社会学部産業関係学科。「働くこと」をさまざまな角度から研究するユニークな学科として、企業や行政機関からも注目され、卒業生は人事企画部門をはじめ、さまざまなフィールドで活躍している。企業の入社内定者向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」にも出演し、雇用や労働にかかわるテーマに取り組む浦坂純子教授(同志社大学社会学部産業関係学科)に、同志社大学・新町キャンパスで話を聞いた。

自然人類学者・長谷川眞理子さんが考える、“違いを力に変える”組織のつくり方
「なぜ、この人はそう考えるのか?」——自分と異なる意見や価値観に触れたとき、相手の言葉の背景を想像する力があれば、対立は対話へと変わる。自然人類学者・長谷川眞理子さんは、霊長類のフィールド研究を出発点に、大学教育現場での人材育成や文化行政に携わりながら、人間社会の進化と可能性を探求してきた。「“違い”を面白がることが、相手を理解する第一歩」――異なる価値観と向き合い続けてきた長谷川さんの語りには、職場での多様性の受け入れ方や議論の深め方、新人の挑戦を支える環境づくりについての貴重なヒントが詰まっている。新卒社員(2026年4月入社予定者)向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」にも出演している長谷川さんの言葉に耳をすまそう。

俳優の小林涼子さんが、もがきながらたどり着いた“新たなキャリア”の見つけ方
4歳で芸能界にデビューして以来、多くの話題作に出演し続けている俳優の小林涼子さん。20代の頃、自分の将来に悩み続けるが、そんななかで出合った「農業」がきっかけとなり、2021年、持続可能な農業を目指して起業。俳優業と農業とのパラレルキャリアをスタートさせた。就職したばかりのフレッシャーズはもちろん、彼・彼女らを迎え入れる上司や先輩社員にとっても、「キャリア形成」は正解を見つけにくい難しいテーマだ。新卒社員(2026年4月入社予定者)向け媒体「フレッシャーズ・コース2026」にも出演している小林さんに、自身のキャリアの見つけ方について語ってもらった。

会社の“カルチャー”や新制度を、社員が意識し、仕事に反映させるために
多くの企業が、ミッション・ビジョン・バリューや経営理念を掲げているが、社員への浸透に腐心している経営層も少なくない。スポーツ競技におけるチームは、「勝利」という目標をメンバーが常に意識することで強くなる。そして、共通する思いがチームの雰囲気をつくり、チーム特有の“カルチャー”を醸し出していく。企業内の組織も同じだ。そうしたなか、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念で、多種多様なウエディング情報サービス事業を行っている株式会社ウエディングパークは、社員が醸し出す“カルチャー”が事業推進の源泉になり、ワークエンゲージメントを高めている。執行役員であり、コーポレートデザイン本部・本部長の戸田朱美さんに話を聞いた。

「キャリア自律」のジレンマを超えて、イマドキの若手社員に企業はどう向き合うか
グローバル化の進展や産業構造の変化、少子高齢化などによって目まぐるしく変わる社会情勢を背景に、働く人一人ひとりが自らの生き方を問い、主体的にキャリア形成をしていく「キャリア自律」や「キャリアオーナーシップ」に注目が集まっている。その大きな流れのなか、大学では、2000年代半ば頃から「キャリア教育」がさかんに行われるようになり、学生たちに早いうちから将来の働き方を考えさせる取り組みが広がってきた。これまでの間で、大学や学生たちの意識はどう変化してきたのだろうか。また、大学を出て間もない若手社員を迎える企業には、どのような対応が求められているのか。法政大学キャリアデザイン学部の児美川孝一郎教授に聞いた。

志望度を上げていく、ITエンジニア・DX人材の心を掴む“魅力的な面接”とは?
かつて、日本の企業の多くは、システムの開発をSIerなどに発注していたが、昨今は「内製化」傾向が高まっている。一方で、ITエンジニアやDX人材は超売り手市場で、「思うような人材を獲得できない」という人事担当者の悩みを聞く。自身が元エンジニアであり、人材エージェント会社で2000名以上のエンジニアの転職をサポートし、現在、HRコンサルティングサービスや採用業務代行(PRO)サービスを提供する芦川由香さん(株式会社レイン,CEO)が「ITエンジニア・DX人材の就活&採用事情」について筆を執る。その第2回は、前回に続き、「ITエンジニア・DX人材の転職の実態に関するアンケート」から見えたこと。

世代間コミュニケーションのギャップをなくすために、私たちはどうすればよいか
元NHKキャスターとして「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」などに出演し、現在はフリーアナウンサーとして多方面で活躍する牛窪万里子さん(株式会社メリディアンプロモーション代表取締役)。牛窪さんは、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』など、多くのビジネス書も執筆するなど、言葉と表現によるコミュニケーションのプロフェッショナルだ。そんな牛窪さんによる連載「いま必要な“組織を活性化する”コミュニケーション」の第3回をお届けする。
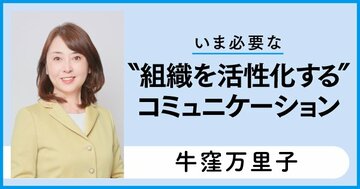
大学から力強く巣立っていく外国人留学生が、企業で活躍するために…
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第18回をお届けする。

院生(修士・博士)とポスドクの採用で、人事担当者と経営層が心がけたいこと
多くの企業において、次代の人材確保が大きな経営課題になりつつあるなか、大学院生(修士・博士)や、任期付き研究員であるポストドクター(ポスドク)の存在が注目されている。従来、大学院生――特に理系学生の場合は大手企業が研究室のルートなどで採用を進めてきたが、近年は、むしろ、学部生と同じように幅広い職種で受け入れるケースが増えている。そこで今回は、大学院生に特化したキャリア支援を展開している株式会社アカリクの山田諒さん(代表取締役)に、採用を巡る現状と課題、高度専門人材としての大学院生の魅力、人事担当者と経営層が心がけたいことについて話を聞いた。

目的が「再雇用だけ」ではNG!――人事部からアルムナイへのアプローチ方法は?
「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が注目されている。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係(アルムナイ・リレーションシップ)を築いていくかは、人材の流動性が高まっている時代でことさら重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続き、昨年(2024年)には著書も発表した、「アルムナイ」知見についての第一人者・鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)による、「HRオンライン」連載=「アルムナイを考える」の第10回をお届けする。
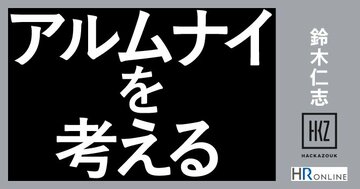
令和の時代に、“人を大切にして、地域に貢献する企業”が輝く理由
2030年での達成を目指すSDGs――そのゴール8「働きがいも経済成長も(Decent Work and Economic Growth)」、ゴール11「住み続けられるまちづくりを(Sustainable Cities and Communities)」を継続している企業がある。収益不動産の再生・売買事業、賃貸管理事業(プロパティマネジメント)を行う武蔵コーポレーション(さいたま市大宮区)だ。昨年(令和6年/2024年)には、埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰で埼玉県知事賞を受賞するなど、地元にも欠かせない存在だ。“人を大切にして、地域に貢献する”ことを目指す企業は多いが、実現はなかなか難しい――同社を創業した大谷義武さん(代表取締役)に、その実現までの道のりと「住まいで人を笑顔に」する方法を聞いた。

“活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか?
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、いま、この時代に心がけたい“活私奉公”の働き方について考える。
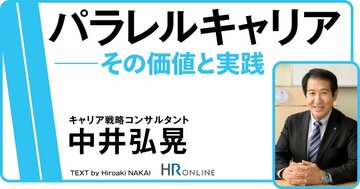
【ミュージカル研修(後編)】若手社員は、変化し続ける組織の中で、変化し続けられる人であってほしい
自動車に関する複合的なサービス(カーライフのトータルサポート)を行うプレミアグループは、2007年の創業からわずか10年で東証二部に上場(翌2018年12月に東証一部へ市場変更、現在はプライム市場へ移行)し、躍進を続けている。同グループのエンジンとなっているのが「人」だ。2020年には、グループ役職員を対象とした研修を企画・実施する会社として、株式会社VALUEを設立。「常に前向きに、一生懸命プロセスを積み上げることのできる、心豊かな人財を育成します」というMISSIONを掲げ、“人財”を輩出している。そのユニークな研修のひとつ“バリューミュージカル研修”は、なぜ、どのようにつくられたのか?

