記事一覧
上司と部下、知り合い、友人……対人関係を劇的に変える“すごい傾聴”とは?
いまや、多くの企業で1on1が導入され、管理職や上司には、マネジメントスキルのひとつとして「傾聴する力」が求められている。しかし実際のところ、部下と心を通わせることができずに困っていたり、“いい上司”だと思われたくて言動が空回りしてしまったりと、ビジネスパーソンの“1on1にまつわる悩み”は絶えない。心理学に裏付けられ、カウンセリングの場では必須とされる「傾聴」が、ビジネスの場では、「オウム返しをしながら、ただ頷いているだけのもの」と誤解されている側面もある。今回は、企業研修講師であり、心理療法家でもある小倉広さんに、聞き手自身のマインドも豊かにしていく傾聴の方法について教えていただいた。

いま、このタイミングで、“アルムナイ”の書籍を執筆して気づいたこと
「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が目立つようになった。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性が高まっている、この時代でことさら重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続く、「アルムナイ」についての第一人者として知られる鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)。その、鈴木さんによる、「HRオンライン」連載「アルムナイを考える」の第8回をお届けする。
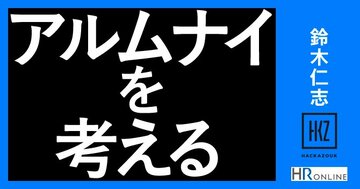
【オフィス変革の潮流(後編)】3社の実例でわかる、これからのオフィスのあり方と“働き方変革”の深化
コロナ禍を経て、「人が集まることの価値」が再発見されている現在(いま)、「オフィス回帰」の流れが強くなっている。そうしたなか、「人が集まる場所」としてオフィスに求められるものは、どう変わっているのだろうか。企業の知的生産性向上を目指す「働き方変革」、教育現場における主体的な学びを目指す「学び方変革」をパーパスに、来年、創業115年を迎える株式会社内田洋行は、変わりゆくオフィスニーズにソリューションを提示する存在として多くの企業から信頼を得ている。同社グループの売上高は、約65%がICT関連ビジネス、35%が環境構築ビジネスで構成されている。環境構築ビジネスに携わる「オフィスエンタープライズ事業部」の髙橋善浩さん、もうひとつの柱=ICT関連ビジネスに携わる「エンタープライズエンジニアリング事業部」の村田義篤さんのお2人に、昨今のオフィス構築の潮流について話をうかがった。

【オフィス変革の潮流(前編)】ICTの活用と快適なオフィス空間が、一人ひとりの働き方を変革していく
コロナ禍を経て、「人が集まることの価値」が再発見されている現在(いま)、「オフィス回帰」の流れが強くなっている。そうしたなか、「人が集まる場所」としてオフィスに求められるものは、どう変わっているのだろうか。企業の知的生産性向上を目指す「働き方変革」、教育現場における主体的な学びを目指す「学び方変革」をパーパスに、来年、創業115年を迎える株式会社内田洋行は、変わりゆくオフィスニーズにソリューションを提示する存在として多くの企業から信頼を得ている。同社グループの売上高は、約65%がICT関連ビジネス、約35%が環境構築ビジネスで構成されている。環境構築ビジネスに携わる「オフィスエンタープライズ事業部」の髙橋善浩さん、もうひとつの柱=ICT関連ビジネスに携わる「エンタープライズエンジニアリング事業部」の村田義篤さんのお2人に、昨今のオフィス構築の潮流について話をうかがった。

人材育成としての「内定者フォロー」が、内定辞退と早期離職を減らしていく
来春(2025年4月)に企業に入社する「25卒生」は、ストレートで大学に進学し、学部生としての4年間で卒業予定であれば、高校3年時に、“夏の甲子園”が唯一なかった学年(2002年4月生まれ~2003年3月生まれ)だ。つまり、新型コロナウイルスの影響を大学受験時にまともに受けた世代である。そんな彼・彼女たちが企業から入社の内定を受け、あと半年あまりで社会に飛び立とうとしている。自分たちが置かれる環境の変化に敏感な彼・彼女たちに対して、受け入れ側の企業は、いま、この時期に、どのようなフォローを行えばよいか。「内定者フォロー」のセミナーを開催し、さまざまな企業の人事担当者と接点を持つ有識者(御明宏章さん)に、「HRオンライン」が話を聞いた。
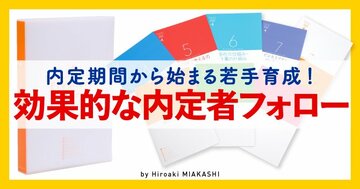
企業は、いまどきの新入社員たちにどう向き合い、何をしていけばよいか
24卒の新入社員が各企業に入社して約半年が過ぎた。人事部では、25卒の内定者フォローに切り替えている採用・教育担当者が多いだろう。そうしたなか、キャリア志向のある、昨今の新入社員は、職場の不満を口にしないまま、入社1年も経たないうちに離職してしまうケースがある。企業の人事部は新入社員にどう向き合うべきか――「『フレッシャーズ・コース(FC)』を活用した自律型新入社員研修」のプログラム設計を手がけるほか、新入社員の入社後フォロー研修の講師としても活躍する内山厳さんに話を聞いた。

“スーパー利己的”な新入社員が、アルムナイとうまく付き合うための方法
集団生活を営んだり、企業・団体の中で働いたりするときに、自分の利益を優先する「利己的な姿勢」は軋轢や諍いを生むことが多い。そのため、「誰かのため」という利他的な姿勢が美徳とされ、仕事においては、「組織のため、会社のため」という滅私奉公のスタイルが昭和の時代は重んじられた。しかし、時代は変わり、「スーパー利己的になって、会社での自分の目的を達成してください!」と新入社員にメッセージする経営者もいる。令和のビジネス界に「アルムナイ」という言葉を広め、浸透させた鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク 代表取締役CEO)だ。“スーパー利己的”とは、どういうことか? 「HRオンライン」で連載執筆中の鈴木さんのオフィスを訪ね、その真意を聞いた。

「ウェルビーイング」を高めるために個人が行えること、組織が取り組むべきこと
近年、さまざまなところで注目されている「ウェルビーイング」。それは、個人レベルの生き方や心の持ちようだけではなく、企業や社会の課題としての意味を持つ。ウェルビーイングとは何か? なぜ、ウェルビーイングが注目されているのか? 個人や組織はどのように向き合えばよいのか? 今年(2024年)4月、世界で初めてウェルビーイングを冠した武蔵野大学ウェルビーイング学部が発足。その初代の学部長であり、日本におけるウェルビーイング研究の第一人者である前野隆司さん(武蔵野大学ウェルビーイング学部学部長/教授 兼 慶應義塾大学大学院教授)に話を伺った。

たそがれ研修、役職定年……いま考えたい、50代ミドルシニアのリアルな働き方
65歳までの雇用確保措置が企業に義務化されているいま(2024年8月現在)、再雇用か勤務延長(定年退職せずに雇用される勤務)で、少なくとも65歳まで働き続ける人が増えている。そうしたなか、50代半ばで役職定年を迎え、仕事のモチベーションの低下とともに「失われていく10年(55~65歳)」に思い悩む人が多いようだ。雇用する側の企業にとっては、定年退職を控えたミドルシニア世代にどう向き合っていくかが喫緊の課題となる。これまでに、1500社以上・約13万人の人材を育成し、「コンサルタント・オブ・ザ・イヤー」(全能連マネジメント・アワード2023)を受賞した田原祐子さん(株式会社ベーシック 代表取締役/社会構想大学院大学教授)に、最新著書『55歳からのリアルな働き方』をもとに“企業とミドルシニアのこれからの在り方”を聞いた。

ミュージシャン東野純直さんが考える“ジェネレーション・ギャップ”の解消法
1993年に、澄んだ歌声と親しみやすいメロディでCDデビューし、人気を博した、シンガーソングライターの東野純直(あずまのすみただ)さん。プロのミュージシャンでありながら、ラーメン職人という、もうひとつの顔を持つ東野さんは、“パラレルキャリア”の実践者でもあり、新卒社員(2025年4月入社予定者)向け媒体「フレッシャーズ・コース2025」にも出演している。アルバイトの雇用など、若者たちとの関わりも多い東野さんに、異なる世代が誤解なく対話し、付き合いを深めることの大切さについて語ってもらった。

なぜ、学生たちは“ボランティア”をするのか?――その背景を知っておくことが大切
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第15回をお届けする。

“偶然の出来事”をキャリアに活かす!――そのために必要なことは何か?
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、個人のキャリア形成に影響を及ぼす「計画された偶発性理論」について一考する。
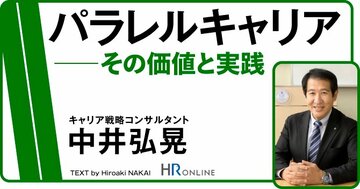
大学生のアクティブ・ラーニングの「学び」を、企業は生かすことができるか
学校教員はじめ、教育関係者にとっては、耳なじみのフレーズである「主体的・対話的な深い学び」――文部科学省によれば、これは、アクティブ・ラーニングから生まれる学びのあり方だが、企業経営層や人事担当者は、昨今の大学生がどのような学び(アクティブ・ラーニング)を経て社会に出ているのかをあまり把握していないのではないか。アクティブ・ラーニングのひとつであるPBLを授業科目にしている大学が増加傾向にあるが、その授業内容や目的・成果はどうなっているのか? 産学協働に長らく取り組み、“グローバルなPBL”を展開している万浪靖司さん(静岡産業大学経営学部准教授)に話を聞いた。

上司も部下も知っておきたい、“海外リモートワーク”でチームが元気になる方法
コロナ禍ですっかり一般化した“リモートワーク”だが、海外在住で日本の企業にリモートワークすることは、時差の問題などもあって、未だハードルが高いようだ。「HRオンライン」の執筆でもお馴染みの東加菜さんは、ベトナムのホーチミンに住みながら、日本の企業(michinaru株式会社)の広報担当として、フルリモートワークを続けている。“海外リモートワーク”のメリットとデメリットは何か? また、リモートワークの多い社員に人事担当者や管理職はどう接すればよいか?――HR業界に深い知見を持つ東さんならではの就労観を「HRオンライン」が聞いた。

大学での学びやキャリア支援を、社会に出る学生が役立てていくために……
アフター・コロナの景気回復と人手不足を背景に、就活市場が「売り手優位」になっている。文部科学省・厚生労働省の発表によると、24卒(2024年3月卒の学生)の就職率は4月1日時点で98.1%となり、過去最高を記録した。また、リクルート就職みらい研究所の調査では、25卒(2025年3月卒の学生)の就職内定率は5月1日時点ですでに72.4%と前年を7.3ポイント上回っている。そうした一方で、就職活動の早期化・長期化による弊害も目立ち始めている。今回は、立教大学経済学部教授で同大学キャリアセンター部長の首藤若菜さんに、大学側から見た就活市場の実態と課題、キャリアへの考え方、企業内の人材定着の必要性といった話を伺った。

【対談 村瀬俊朗×篠田真貴子(後編)】なぜ“人の話が聞けないリーダー”が職場に増えるのか?
ここ数年のうちで、最も注目を集めた人事関連のキーワードである「心理的安全性」――。実際のところ、この考え方は日本企業にどんなインパクトを与えたのだろうか? この問題意識の下、このたび村瀬俊朗さん(早稲田大学 准教授)と篠田真貴子さん(エール株式会社 取締役)による特別対談が行われた(*)。この概念の第一人者でもある村瀬さんは、2021年より富士通の「心理的安全性プロジェクト」でアドバイザーを務めてきた。3年間にわたるそのプロジェクトの集大成『Fujitsu心理的安全性Playbook』を振り返りつつ、篠田さんが抱いてきたさまざまな疑問を、村瀬さんにぶつけてもらった。

【対談 村瀬俊朗×篠田真貴子(前編)】優秀なリーダーほどハマる“心理的安全性のジレンマ”とは?
ここ数年のうちで、最も注目を集めた人事関連のキーワードである「心理的安全性」――。実際のところ、この考え方は日本企業にどんなインパクトを与えたのだろうか? この問題意識の下、村瀬俊朗さん(早稲田大学 准教授)と篠田真貴子さん(エール株式会社 取締役)による特別対談が行われた。この概念の第一人者でもある村瀬さんは、2021年より富士通の「心理的安全性プロジェクト」でアドバイザーを務めてきた。3年間にわたるそのプロジェクトの集大成『Fujitsu心理的安全性Playbook』を振り返りつつ、篠田さんが抱いてきたさまざまな疑問を、村瀬さんにぶつけてもらった。

ビジネスで、日常で、相手を受け入れる、“牛窪流”「聞く」「話す」メソッドとは?
世代間コミュニケーションの難しさを感じているビジネスパーソンに読まれている良書がある。書名は、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』『難しい相手もなぜか本音を話し始めるたった2つの法則 入門・油田掘メソッド』――著者は、どちらも、元NHKキャスターの牛窪万里子さんだ。25卒内定者向けメディア「フレッシャーズ・コース2025」にも出演している牛窪さんは、これまでに5000人以上をインタビューしてきた「聞く」「話す」ことのスペシャリストであり、フリーアナウンサーが所属する企業の経営者でもある。「HRオンライン」が、そんな牛窪さん自身の発する言葉に耳を傾けた。

仕事のキャリアをよい方向に導く“緩やかなつながり(弱い紐帯)”を考える
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』(*)の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、 “パラレルキャリア”の効果の一つである「弱い紐帯」について、中井さんが解説する。
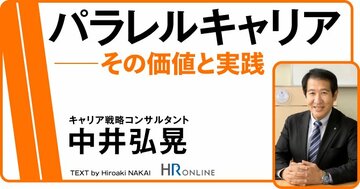
研修で学んだことをどうすれば仕事に活かせるか――“研修転移”の実践方法
2018年6月に発売された書籍『研修開発入門 「研修転移」の理論と実践』が、ウィズコロナの時代に、人事(研修)担当者のバイブルになっている。企業の経営・人事側からすれば、時間と労力をかけて行った研修での学びを、受講者には日々の仕事で少しでも役立ててほしいはず。しかし、実際は、研修を「やりっぱなし」で終わるケースも多いだろう。書籍の共著者であり、昨年(2023年)9月に「“研修の転移と評価”実践会」を立ち上げた、株式会社ラーンウェル 代表取締役の関根雅泰さんに話を聞いた。

