記事一覧
児童養護施設出身モデルの田中れいかさんが、みんなと働きながら気づいたこと
企業に新入社員が入社して2カ月が過ぎた。学生生活からの環境の変化に戸惑い、相談する相手もなく、孤独感を覚えている新人も多いことだろう。人事担当者や先輩社員は、そんな彼・彼女たちにどのような言葉を送り、手を差し伸べればよいか。人間関係やコミュニケーションが希薄になりがちなウィズコロナの時代――他者に寄り添ってもらい、自分が誰かに寄り添うことの大切さを伝え続ける人がいる。児童養護施設出身モデルの田中れいかさんだ。25卒内定者向け「フレッシャーズ・コース2025」にも出演している田中さんが語る“理想的な職場”とは?

「いかに生きるか」という問いと、思いを語り合える職場がキャリアをつくる
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第14回をお届けする。
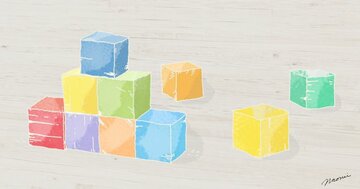
従業員目線の“健康経営”こそが、これからの時代に不可欠な理由
経済産業省は、“従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること”を「健康経営」と定義し、企業が、“従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながる”とメッセージしている。コロナ禍を経て、働く誰もが自分の「健康」に留意するなか、はたして、それぞれの企業は従業員一人ひとりの「健康」に適切に向き合っているだろうか? 健康管理ソリューションサービス「Carely(ケアリィ)」を運営する株式会社iCAREの山田洋太代表取締役CEOに、再度、「HRオンライン」にご登場いただき、話を聞いた。

“メンター”との出会いと気づきが、これからの女性リーダーをつくる
労働力人口が減少していくなか、女性活躍推進の成否は経済成長の明暗を分けると言っても過言ではない。しかし、そこには、“女性管理職の登用に腐心する経営層・人事部”と“管理職に就くことを望まない女性”の溝といった、さまざまな課題が横たわっている。メンターの育成など、企業における女性活躍を支援する池原真佐子さん(株式会社Mentor For 代表取締役)に、2021年・夏にインタビューを行った「HRオンライン」が、コロナ禍が落ち着いた2024年――改めて、“現在進行形”の話をうかがった。

この4月に入社2年目を迎えた新入社員は、“フォロー研修”で何を得たか?
コロナ禍での就職活動を経て、昨年2023年4月に企業・団体に就職した新入社員――「『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修」の一環として、入社3カ月後と入社6カ月後に行われた“新入社員フォロー研修”の総決算として、今年2月に、“最後のフォロー研修”が行われた。「経験学習」を繰り返しながら、自分の「強み」や「良さ」を仕事にどう生かしていけばよいか――これまで同様に、研修会場を訪れた「HRオンライン」が、その学びの様子をレポートする。

人事担当者の“孤独感”を解消していく「外部プロ人事」とは何か?
人的資本経営、社員のメンタルヘルス、新卒採用の早期化&長期化、アルムナイ対応、社員研修、テレワーク管理……働き方改革やコロナ禍を経て、企業・団体の多くの“人事”担当者は、自分の有給休暇の取得がままならないほど、日々、多忙な業務に追われている。総務・経理・人事といったバックヤード部門は専門性が求められるものの、力量のある正社員をなかなか補充できないこともその要因のひとつだ。そうしたなか、自社組織外の即戦力のプロフェッショナル人事専門家を「外部プロ人事」と呼び、事業を展開している企業がある。その代表者・門馬貴裕さん(株式会社コーナー 代表取締役)の「HRオンライン」への寄稿を送る。
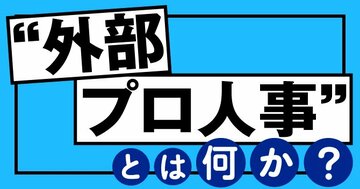
<“選ばれる企業”になるための採用戦略>企業サイトの「ウェブアクセシビリティ」に、いま注目が集まり始めている理由
「ウェブアクセシビリティ」という言葉を耳にする機会が増えてきた。2024年4月施行の「改正障害者差別解消法」の影響もあり、自社サイトのウェブアクセシビリティを見直す企業も多いだろう。これは採用サイトについても例外ではない。そこで今回は、ウェブアクセシビリティ対応のサイト制作を多数手掛けるWeb制作会社・デザインファームである株式会社トルク代表取締役の本田一幸氏と、CTOの堀江哲郎氏に、いま、採用サイトでウェブアクセシビリティを向上させる意義を聞いた。

特別支援学校の校長を務めた私が考える、“教え方”と“働き方”の理想像
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第13回をお届けする。
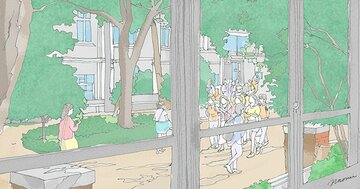
「プレゼンがうまい」「雑談力がある」と言われる人に共通する「情報編集」のスキルが、これからのビジネスパーソンにとって欠かせぬ力になっていく
世の中には無数の情報があふれかえっている。その真贋を見分けて必要なものを抽出・整理し、自分なりの分析や見解を加えたうえでアウトプットするのが「情報編集」と呼ばれる作業だ。編集と聞くと、出版社の編集者を連想するかもしれないが、情報編集が必要なのは編集者に限らない。「メディアとまったく関係のない業種に携わっている人にとっても、情報編集は役立つスキルだ」と、元『週刊ダイヤモンド』編集長の田中博氏は指摘する。そこで今回は、情報編集のプロフェッショナルである田中氏に、情報編集の重要性や活用の仕方、身に付けるためのヒントを聞いた。

「アルムナイ」の広がりに伴う“さまざまな声”について、私がいま思うこと
「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が目立つようになった。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性が高まっている昨今でことさら重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続く、「アルムナイ」についての第一人者として知られる鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)。その鈴木さんによる、「HRオンライン」連載「アルムナイを考える」の第7回をお届けする。
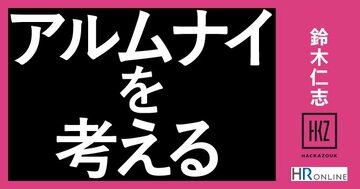
“自律”と“能動”――いま、大学の教育と、企業の人材育成で必要なこと
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第12回をお届けする。

“パラレルキャリア”の効果と効果最大化のために個人と組織に必要な姿勢
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、ひとつの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所・代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。前回「価値ある“パラレルキャリア”とは?広義の5タイプから考える副業との違い」に続く、中井さんの寄稿をお届けする。
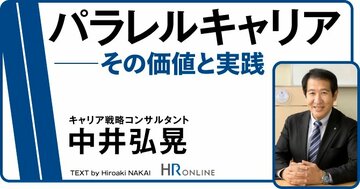
カスハラ対応にも欠かせない、“アンガーマネジメント”の知識と実践
価値観やコミュニケーションの手段が多様化するなかで、「怒り」の感情をコントロールしながら良好な人間関係を築いていくにはどうしたらよいのだろうか――日本アンガーマネジメント協会・代表理事の安藤俊介さんからそんな問いの答えを得てから2年あまり。その間、新型コロナウイルスが5類感染症に移行し、多くの企業がリモートワークを出社勤務に戻すといった対応に追われている。また、昨今は、カスハラ(カスタマーハラスメント)対策やオンラインコミュニケーション世代の入社・育成に忙しい企業も多いようだ。そんないまだからこそ必要な「アンガーマネジメント」は、どのようなものか。安藤さんにお話を再び伺った。

新卒採用の成否は、学生への“フィードバック”の良し悪しで決まる!
24卒(2023年度卒業・修了予定者)の入社内定式が行われた、昨年(2023年)10月1日時点で、大学生の就職内定率は74.8%と、前年同期を0.7ポイント上回った。コロナ禍が落ち着き、労働力人口の減少に伴って、新卒採用は「売り手市場」になっている。しかし、応募学生の母集団形成がうまくいかず、良い人材になかなかめぐり逢えない企業も多い。そうしたなか、25卒採用に向けて、『志望度は面談で決まる~学生に選ばれる企業になるために~』というウェビナーが昨年(2023年)11月と12月に開催された。そのウェビナーの内容とともに、最新の“採用市場戦線”を「HRオンライン」が追いかける。
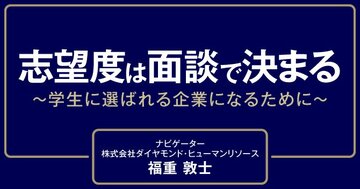
入社から6カ月時点の “23卒新入社員の成長”を研修から読み取る
コロナ禍で就職活動を行い、昨年2023年4月にさまざまな企業・団体に就職した新入社員たち――「『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修」の一環として、入社3カ月後に行われた“新入社員フォロー研修”に続き、昨秋、都内某所で、入社6カ月後の研修が実施された。彼ら彼女らは、それぞれの職場でどう働き、何を学んでいるのか。そして、今回の研修で自分たちの仕事をどう表現したのか――前回同様に、研修会場を訪れた「HRオンライン」が、その様子を詳細にレポートする。
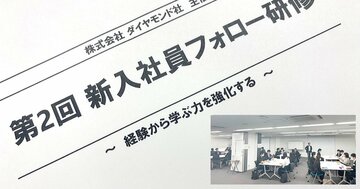
人も職場も社会も変わる“ダイバーシティコミュニケーション”とは何か?
“多様性”“ダイバーシティ”という言葉が人口に膾炙(かいしゃ)し、「人的資本経営」というキーワードも重要視されている現在(いま)、企業経営層や管理職、人事担当者は、「ダイバーシティ&インクルージョン」や従業員の「キャリア自律」にどう向き合えばよいのだろう。「個人が自分のキャリアを自分事としてとらえ、変化を恐れずに、自分を磨きつづける。組織は多様性と向き合い、一人一人の価値を最大限に引き出す経営を目指す」――株式会社キャリアンサンブル代表の垂水菊美さんはそう語る。「ダイバーシティ」について、「キャリア」について、そして、垂水さんが提唱する「ダイバーシティコミュニケーション」について、話を聞いた。

経験学習において、人事担当者が行える“リフレクション”支援を考える
人材育成の手法のひとつとして知られる「経験学習」で、ことさら重要なのが「内省的観察」のステップだろう。“リフレクション”と呼ばれるこの行動は、研究者によって多くのとらえ方(解釈)があり、正しい実践はなかなか難しいようだ。効果的な“リフレクション”を実現するために、マネジャーは部下をどう支援すべきか――それを説いた前回記事に続き、今回は人事担当者が行える“リフレクション”支援を考える。
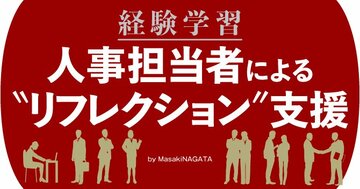
「急がば回れ」の姿勢が、“アルムナイ採用”をしっかり成功させていく
「人的資本経営」のカギを握る「アルムナイ」。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性がますます高まるこれからの時代において重要だ。アルムナイ専用のクラウドシステムを提供するなど、アルムナイに関する専門家である鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)が、企業の「辞められ方」、従業員の「辞め方」を語る連載「アルムナイを考える」――その第6回をお届けする。
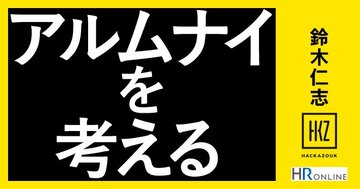
新卒採用の現在と未来――24卒の振り返りと25卒の課題を考える
2024年3月卒業予定者(以下、24卒)の採用活動がほぼ終了した。総じて、新卒採用活動のスケジュールは早期化しているようだ。2025年3月卒業予定者(以下、25卒)からは新しいインターンシップ制度もスタートし、採用担当者は、いままさに“冬インターン”などの対応に多忙な日々を送っていることだろう。例年、独自のアンケートに基づき、『学生の就職活動総括』と『企業の採用活動総括』を公表しているダイヤモンド・ヒューマンリソースの高村太朗さん(経営企画室・室長)へのインタビューから、24卒の結果と25卒採用に向けた課題を考える。

立教大学・中原淳教授の書籍が、“オンライン読書会”の参加者に伝えたこと
今年(2023年)6月に刊行された書籍『人材開発・組織開発コンサルティング 人と組織の「課題解決」入門』(立教大学経営学部教授 中原淳 著/ダイヤモンド社刊)が、企業の経営層や人事担当者に広く読まれている。A5判・464ぺージの大著だが、多くの図版とともに展開されるページは、読みやすく、とても丁寧なつくりで、誰もが理解できる内容だ。その「オンライン読書会」が、参加費無料で、9月の2夜にわたって行われた。各回200名以上の参加者でにぎわったイベントの様子を「HRオンライン」がレポートする。

