記事一覧
ダイバーシティを実現する、ハウス食品グループの“組織風土改革”とは?
ハウス食品グループはカレーやシチューの素などの商品がおなじみだが、国内外に43の連結子会社を持ち、グローバルに価値を創造する企業グループへの変革に取り組んでいる。従業員の「属性」「経験」「適性」も多種多様になっており、成長を実現するために多様な個性の発揮と融合を促進している。「全員参加の職場の改革サイクル」と「会社の風土改革サイクル」を回して目指すものは、「一人ひとりが働きがい(成長実感・チャレンジ)を感じながら変革に向けて挑戦する組織」だという。ハウス食品グループ本社株式会社・人材戦略部の根耒伸至さん(人材・組織開発課長)と井ノ上友美さん(学習機会開発課 学習機会開発チーム チームマネージャー)に話を聞いた。

どうすれば、成熟企業で事業創造人材「イントレプレナー」が生まれるか
会社から独立し、起業する「アントレプレナー(Entrepreneur)」と対比され、「イントレプレナー(Intorepreneur)」とも呼ばれる社内起業家。新規事業や新サービスの開拓など成熟化・多様化するマーケットにおいて貴重な存在となる、このイントレプレナーが、大企業で育ちにくいと言われるのはなぜか? どのようにすればイントレプレナーを育(はぐく)めるのか?―—「挑戦と応援が循環する社会を創る」をミッションに成熟企業の新規事業に伴走するmichinaru株式会社の東加菜さんが、ボトムアップ型事業創造やイントレプレナーの育成の方法を語る。
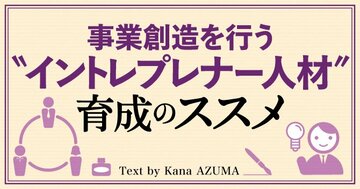
価値ある“パラレルキャリア”とは?広義の5タイプから考える副業との違い
終身雇用・年功序列という日本型雇用があたり前ではなくなり、働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、ひとつの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者であり、キャリア戦略コンサルタントの中井弘晃さんは“パラレルキャリア”が、個人と組織を成長させると説く。中井さんの「HRオンライン」への寄稿から、“パラレルキャリア”の価値を考えたい。
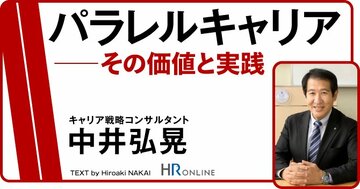
「自由時間の充実」が仕事への活力を生み、個人と企業を成長させていく
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第11回をお届けする。

“メンバーの持ち味をとらえ、事業につなげる”リクルートの1on1活用法
1on1によって、マネジャーとメンバーの関係性がよくなったり、コミュニケーションが活性化したという事例をしばしば耳にします。企業としては、それをさらに進化させて、メンバーの成長、ひいては成果や価値創造につなげていきたいところでしょう。この課題に対して、リクルートHRエージェントDivision首都圏統括部では、「1on1を通してメンバーの持ち味を把握し、その力を十分に引き出すべく仕事の機会を提供する」ことをテーマに、取り組んできました。いま、同社で何が起こっているのか、『部下が自ら成長し、チームが回り出す1on1戦術』の著者である人材・組織開発コンサルタントの由井俊哉氏が、同社のキーパーソンにインタビューし、深層に迫りました。
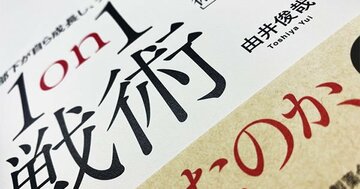
Hondaの人材育成施策に見る、「エンゲージメント」を高めるキャリア支援
「私はいつも、会社のためにばかり働くな、ということを言っている。自分のために働くことが絶対条件だ」――これは、本田宗一郎氏(本田技研工業創業者)が1969年(昭和44年)に同社の従業員に向けて発信した言葉だ。激動の自動車業界のなか、「人や社会の役に立ちたい」「人々の生活の可能性を拡げたい」という想いを原点にするHonda(本田技研工業株式会社)は、人事関連領域でも変革と挑戦を続けている。従来の「階層別研修」から「新たな研修体系」への転換など、新たな人材育成施策と現況を人事部のキーパーソンたちに尋ねた。

“社内広報活動”で、社員のコミュニケーションを活性化させるには…
健康経営に注力する企業が増えているなか、法人向けに健康管理ソリューション「Carely(ケアリィ)」を開発・提供する株式会社iCAREが、今年(2023年)2月、これまでマーケティング部門にあった広報チームを人事部門に移した。人的資本経営の時代、社内情報を広報メンバーがしっかり汲み取り、“人を起点とした情報”を社内と社外に発信していくことに価値を見出しているという。前職や異動前のキャリアを生かしながら、3人の育児と仕事を両立させる、同社People Experience部(人事総務部)の呉美里氏(広報PRチーム リーダー)に話をうかがった。

24卒生の“秋採用”で、企業が良い学生と巡り合うためのいくつかの方法
新卒採用支援を行っているダイヤモンド・ヒューマンリソース社の調査によれば、今年(2023年)のゴールデンウイーク明けの時点で、企業の内定を獲得した学生(24卒生)の比率は昨年(23卒生)を大きく上回った。しかし一方で、夏を過ぎ、秋になって、まだ内定を受けていない学生、採用枠を満たしていない企業も多くある。そうしたなか、10月から12月にかけて行われる「秋採用」は、企業にとっても、学生にとっても、お互いの活路を見出す大きなチャンスになるだろう。採用コンサルタント・採用アナリストの谷出正直さんに、企業(採用担当者)と学生(就活生)の良い出会い方を「HRオンライン」が聞いた。

23卒の新入社員が入社後3カ月の“フォロー研修”で学んだことは…
マスクを着けた人も減り、昨年2022年とは社会の景色がすっかり変わった2023年の夏――4月に入社した新入社員たちも、それぞれの職場や仕事に慣れつつあった。そうした複数の企業のフレッシャーズを対象に、入社3カ月後(2023年7月時点)の“新入社員フォロー研修”が行われると聞き、「HRオンライン」は都内の研修会場を訪ねた。“配属後の自分自身の変化を振り返る”というワークから始まった研修、はたして、その内容は……。
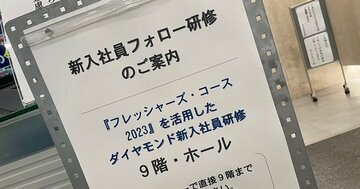
年収の壁、非正規雇用、昇進拒否……“女性活躍推進”を阻む壁は何か?
ダイバーシティ&インクルージョンの礎である「女性活躍推進」――2016年4月に施行された「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」は、「働きたい女性が活躍できる労働環境の整備を企業に義務付けることで、女性が働きやすい社会を実現すること」を目的として、10年間の時限立法として施行されたものだ。しかし、年収の壁、マミートラック、アンコンシャスバイアスといった問題もあり、企業における女性の働き方は順風満帆とは言い難い。元『日経WOMAN』の編集長であり、『女性リーダーが生まれるとき』(光文社)など、多数の著書がある野村浩子さんに、企業・団体における「女性活躍推進」の現状と課題、これからの道行きを聞いた。

“ナナメウエ”のアウトプットが、組織と個人のこれからを成長させていく
「“ナナメウエの”ユニークな仕掛けのある場」を提供し、「一人ひとりの、個性ある“ナナメウエの”面白いアウトプット」を促進し、「組織・個人・ビジネスの“ナナメウエの”成長」をもたらすことを生業にしている研修講師がいる。八住敦之さん(ピラミッド計画・代表)――ヴィレッジヴァンガードの店舗でのマネジメント経験やイベント、ワークショップなどの場づくりの経験を生かし、オリジナルな発想とプログラムで「アイデア創発」や「リフレクション」研修などを行い、企業の注目を集めている。八住さんがメッセージする“ナナメウエ”とは何か? 「HRオンライン」が話を聞いた。

企業が、海外在住の人材を継続雇用&新規採用するときに心がけること
ある調査によれば、海外赴任時の帯同家族の就労について、6割の企業が「希望があれば認めるが、支援はしていない」と回答している。働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、時間と場所を選ばない「リモートワーク」は一般化したものの、海外在住者が日本企業で働くことのハードルはまだ高いようだ。ホーチミン(ベトナム)に在住し、フルリモートで日本企業の広報・マーケティング業務を担う東加菜さん(michinaru株式会社 マーケティング・広報担当)が、関係者の取材などから“越境リモートワーカー”の価値を語る。
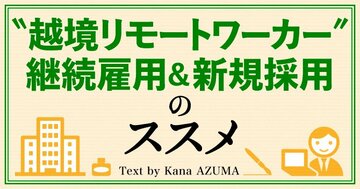
「あたりまえ」が「あたりまえではない」時代の、学生と大学と企業の姿勢
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第10回をお届けする。
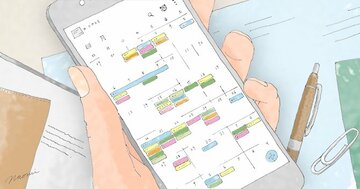
人的資本開示は、企業の“物差し”であり、組織の“健康診断結果”になる
近年、多くの企業・団体で注目度を高めているのが「人的資本」への取り組みだ。人的資本経営の施策が急速に進むなか、人事担当者をはじめとしたバックヤード部門のとまどいの声もあるが、その流れは止められそうにない。各企業・団体は、「人的資本」を戦略的に考えて、積極的に対応する必要があるだろう。さまざまな企業・団体の人事部門と関わりがあり、「人的資本経営」の本質を伝え続ける伊藤裕之さん(WHI総研シニアマネージャー)に、昨年2022年10月のインタビューに続き、いま、経営層や人事部門に求められる「人的資本開示」との向き合い方を訊いた。

内定辞退者や早期退職者に対する“負の感情”が減る「辞め方改革」とは?
「人的資本経営」のカギを握る「アルムナイ」。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性がますます高まるこれからの時代において重要だ。アルムナイ専用のクラウドシステムを提供するなど、アルムナイに関する専門家である鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)が、企業の「辞められ方」、従業員の「辞め方」を語る連載「アルムナイを考える」――その第5回をお届けする。
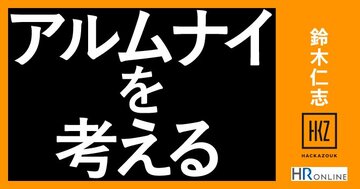
経験学習での、マネジャーから部下への“リフレクション”支援を考える
人材育成の手法のひとつとして知られる「経験学習」において、重要なのが「内省的観察」のステップだ。“リフレクション”と呼ばれるこの行動は、研究者によって多くのとらえ方(解釈)があり、正しい実践がなかなか難しい。組織における効果的な“リフレクション”を実現するために、マネジャーは部下をどう支援すべきか――人事担当者向けのセミナーなどに多数登壇している永田正樹さんが解説する。
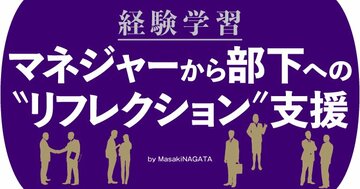
あらゆる人が働く職場で、それぞれ認め合い、自信と誇りを持つために
性別・年齢といった違いだけではなく、仕事の現場ではさまざまな価値観やキャリアを持つ人が働いている。いまや、企業・団体が「ダイバーシティ&インクルージョン」を目指すのは当たり前だが、スローガンが一人歩きして実現がうまくなされない組織も多いようだ。福井県鯖江市に、あらゆる人が集い、働きやすさと働きがいを感じている職場がある――株式会社メガネトップのキングスター工場。世界一の品質を生むのは、機械ではなく、そこで働く人たちの志だ。「HRオンライン」が現地を訪れ、工場長の吉田和弘さん(株式会社メガネトップ 商品開発部 部長)に話を聞いた。

採用担当者が絶対に知っておきたい、就活生への“フィードバック”の重要性
昨年2022年に産学協議会が示した“新しいインターンシップ制度”が、企業・団体によって、今夏(2023年・夏)、主に25卒生(2025年3月までに卒業予定の学部3年生、修士1年生)を対象にスタートする。タイプ3・タイプ4(本文中の図表参照)で呼称される「インターンシップ」は、その実施後に、企業の担当者が学生(就活生)に「フィードバック」を行うことを条件とするが、他のタイプにおいても、優秀な人材を自社に確保するためにフィードバックの重要性が高まりそうだ。就職市場の動向に詳しいダイヤモンド・ヒューマンリソースの福重敦士さん(HD営業局 局長)に、なぜ、就活生への“フィードバック”が採用活動の鍵になっていくのかを聞いた。

いまどきの新卒社員がオンラインでの“新入社員研修”で学んだこと
ウィズコロナの時代が新たなステージを迎えるなか、4月からスタートした2023年度も第1Qの終盤を迎えている。4月入社の新卒社員はそれぞれの職場に配属されて、仕事を覚えている毎日だろう。今年4月、「HRオンライン」は、オンラインで行われた、2日間にわたる新入社員研修(『フレッシャーズ・コース2023』を活用した自律型新入社員研修)を取材した。Z世代の新入社員たちは、オンラインで、何をどう学び、それぞれの職場に戻ったのか? その研修内容を詳細にレポートする。
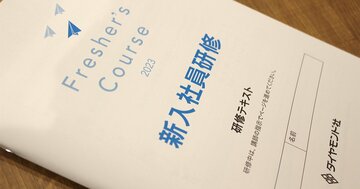
「人が集まる会社」「心が温まる会社」を生み出す「就業規則」の作り方
「就業規則」は、各企業・団体における雇用の“基本ルール”であり、その中身は法定の必要記載事項を中心にしたもので、どの企業もほとんど同じものと思いがちだ。しかし、「就業規則」は四角四面にとらわれることなく、可能な範囲で自由に作ることができる。さらに、取り組み方の工夫次第では、「就業規則」が人事戦略を示唆したり、社内の雰囲気を変えたり、人材採用や組織作りのツールになったりすることもあり得るのだ。社会保険労務士として、多くの企業の労務管理や人事制度、組織作りのコンサルティングを行い、多数の書籍の著者として知られる、株式会社エスパシオの下田直人さんに、「人が集まる会社」となる「就業規則」の作り方や生かし方を聞いた。

