資格・学校(11) サブカテゴリ
第12回
誰にとっても『いい会社』などというものはなくて、大事なのは、自分と会社との関係。感じた雰囲気とか第一印象を大事にして、自分との関係を整理しておくこと。
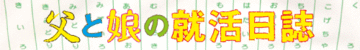
第11回
娘は、この12月の段階で、仮エントリーする会社をどう絞ってよいか分からずに少し焦っているようだった。こういう時は、まず目的をはっきりさせて、そこに至る過程を時間軸に沿って考えることが大切だ。
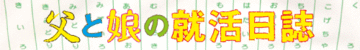
第6回
『司法試験』編の最終回。前回は、法科大学院について「どうやってやり過ごすか」というような観点からの意見を書いてみた。今回は、具体的な学校=法科大学院選びの方針について考えていこう。
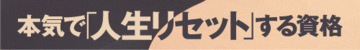
第10回
9年ぶりに総合商社M社が一般職の採用を復活させた新聞記事を読んだ。面白かったのは、その応募者の中に、数十人の男子学生がいたらしい。
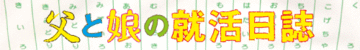
第9回
サービス業を中心に長時間労働や早朝、夜間勤務の職場も昔より増えており、仕事と生活をどう調整するかは、ビジネスパーソンにとって大切な課題である。
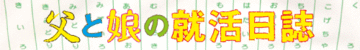
第5回
『司法試験』編の第2回。司法試験をキャリアプランに組み込むための戦略を述べ始める。おそらくこの連載の読者の多くは有職の社会人だろう。それを前提に考えていく。
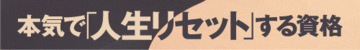
第7回
先日来、どの銘柄でもよいから最低単位の株式を購入することを娘に薦めていた。企業研究に役立つと考えたからだ。
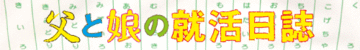
第6回
「えっ!こんなものまで入ってるの?」裕美宛に送付されてきた就職資料の中に、色鉛筆やメモ帳などが入っていた。「それは、企業のホームページの『採用情報』に呼び込むためのものだよ」
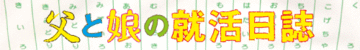
第4回
今回は社会科学系の最難関資格、『司法試験』について考えてみよう。司法試験改革に対する最近の報道では、弁護士過剰時代と合格者の質の低下といった面が強調されている。こんな報道に、惑わされてはいけない。
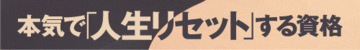
第5回
読者の方から「娘とよくコミュニケーションがとれるなぁ」「小さい頃から話していたの?」などと聞かれる。今後、就活が佳境に入る前に、少し私と娘の関係について触れておきたい。
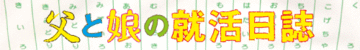
第4回
親は、もっと迷った方がよい、と私は考えている。組織で働く意味に悩みながらも、それを正面から受け止めようとする姿勢は、若者に語れる力を生み出すはずである。
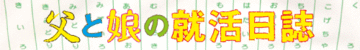
第3回
「医師」の次に紹介する2つめの資格は「歯科医師」。医師資格よりは、バーが低い。ルートに一度乗ってしまえば、よほど怠けたりしくじったりしなければ、資格取得の確実性は高いのだ。
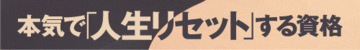
第3回
「石の上にも3年」には深いものがあると、今改めて感じている。学生から社会人への切り替えにも、この程度の時間が必要だ。勉強して身につける知識だけではなく、組織にいること自体も力になるのだ。
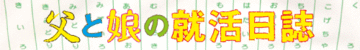
第2回
たしかに子供に、仕事は辛いものだとか、我慢が必要と教えるより、楽しい仕事に出会えることを強調するのは賛成だ。しかし「好きな仕事」を求めて、本当にそれにたどり着けるのか?
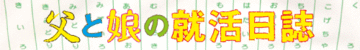
第2回
第2回は「医師資格」の後編。社会人の医学部受験事情について、気になる傾向がひとつ。それは、医学部の「編入」もしくは「学士入学」の合格者に、東大出身者が顕著に見られる点である。
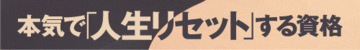
第1回
今年7月のこと。大学3年生の長女が、鉄鋼系商社の会社説明会に参加して帰ってきた。妻が「裕美は、どんな会社を希望しているの?」と食卓で切り出した。
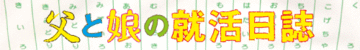
第1回
第1回は「医師資格」。絶対に人生がリセットされる資格の代表格。実際のところ、非常に「門戸の広い」資格なのである。
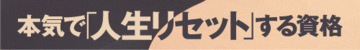
第3回
みずからの強みを知り機会をつかむ
「最高のキャリアは、あらかじめ計画して手にできるものではない。 みずからの強み、仕事の仕方、価値観を知り、機会をつかむよう用意をした者だけが手にできる。
