
野口悠紀雄
生涯現役で活躍できる人と、仕事がなくなる人の「決定的な違い」
人生100年時代、生涯現役で働き、心身ともに元気でいたいと思っている人は多い。しかし、高齢者になってから、どのように働き、どう生きるかは容易に答えがでない。経済学者・野口悠紀雄氏は、「自分を正しく位置づけよ」と語り、技術革新の中で高齢者が持つ強みや可能性、そして求められるリスキリングの在り方を提言する。※本稿は、野口悠紀雄『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』(角川新書)を一部抜粋・編集したものです。

高齢化社会に本当に必要な「2つの課税方法」とは、現実と“真逆”の政策が求められるワケ
高齢化社会に突入している日本は、これまでの社会の仕組みを改革することが求められている。特に介護保険の財源は大きな課題だ。野口悠紀雄氏が考える実現可能な解決策とは。※本稿は、野口悠紀雄『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』(角川新書)を一部抜粋・編集したものです。

新NISAブームに流された人におすすめしたい、最も確実な「たった1つの投資」
新NISAが開始され、それまでより多くの国民が投資に興味を持つようになった。政府も「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと、個人投資家の積極的な市場参加を促進している。しかし、野口悠紀雄氏はそのブームを冷ややかに分析する。※本稿は、野口悠紀雄『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』(角川新書)を一部抜粋・編集したものです。

関税引き上げなどのトランプ政策が世界経済の最大リスクの状況だが、株価急落にはひるまなかったトランプ政権はアメリカ国債の暴落に見舞われると、「相互関税」の上乗せ課税の発動猶予のように即座に反応した。トランプ政策にストップをかけられるのは株式市場ではなく債券市場だ。

トランプ大統領はスマートフォンやPCについて相互関税の対象から外し個別の半導体関税を課すことを発表した。中国からの輸入が主で高率の対中関税によって国内価格が急騰するのを回避する狙いのようだ。だが半導体課税自体がファブレス製造業というアメリカ経済の最も重要な部分に重大な影響を与える。

3月の消費者物価上昇率が4カ月連続で3%台になった要因がコメ価格の高騰であることは間違いないが、より重要な要因は賃上げなどによる価格転嫁の広がりだ。輸入物価上昇への対応が主だった物価対策は便乗値上げの監視や生産性向上の支援などに変え、ガソリン代補助などはやめるべきだ。

「物価と賃金の好循環」は大ウソ、今の賃上げは日本を不幸にする納得の理由
春闘の平均賃上げ率が5.46%となり、景気回復への期待が高まっている。しかし実態は、大企業が強い立場を利用して価格を引き上げ、消費者から利益を得ているに過ぎない。賃上げされない中小企業の労働者がその負担を担っており、これは「好循環」ではなく負の循環である。※本稿は野口悠紀雄『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
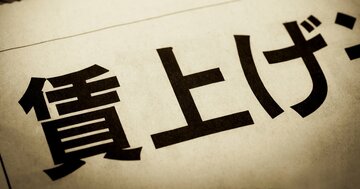
「34年ぶりの高賃上げ率」でも喜べないワケ、大企業がカネを巻き上げる「強欲インフレ」のメカニズム
今年の春闘の平均賃上げ率は5.46%と、34年ぶりの高水準である。しかし恩恵を受けるのは主に大企業の社員に限られる。賃上げ分の原資は価格上昇による利益であり、中小企業に勤める多くの消費者がその負担を強いられている。大企業の賃上げのカラクリを暴く。※本稿は野口悠紀雄『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
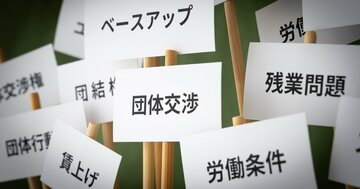
日本を低成長に陥れ、企業をぬるま湯につけた主犯は誰か?
円安や低成長など日本経済は、急激に貧しくなった。この大きな原因は金融緩和政策だったと野口悠紀雄氏は語る。日本企業をぬるま湯につけ、生産性を落とさせた大失敗を解説する。※本稿は野口悠紀雄『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

トランプ政権が打ち出した「相互関税」の税率は極めていい加減だ。これには貿易先国との損得を貿易収支の赤字・黒字で判断するトランプ大統領の反知性的性格が如実に表れている。「90日の発動停止」の間に日本を含め各国は見直しの交渉を進めようとしているが、事態を改善するのは簡単ではない。

トランプ政権の「相互関税」は自由貿易への挑戦でありアメリカを含め世界経済に悪影響を及ぼす。日本政府は正面から問題を指摘すべきだが、日本政府がコメに高い関税障壁を設け国内のコメ市場を操作しているのは事実だ。相互関税に反論するにはコメ政策の抜本的改革が大前提だ。

若年人口減少の下、人材確保から初任給の上昇率が顕著だが、大企業の「45~49歳」や中企業の「30~34歳」や45歳以上の賃金上昇率はこれより高い。中高年者の転職マーケットが成長し始めている結果かもしれないが、転職情報拡充やリスキリング支援が一段と重要だ。

今春闘は連合の第2回集計でも5.40%と前年同期に比べて高い賃上げ率だが、2022年以降を見ても大企業と中小企業など企業規模による賃金格差は拡大している。賃上げが売上価格への転嫁によって行われ、取引上強い立場にいる大企業の賃上げ率が高いからで今年も懸念は残る。

トランプ大統領は、「相互関税」発動に当たって非課税障壁も考慮の対象になるとして、日本の消費税を輸出奨励策だと批判している。しかしその考えには誤解が多い。そもそも世界の大勢が採っている国際課税の原則からいえば、アメリカが売上税を変更するべきなのだ。

日本がAI(人工知能)で立ち遅れているのは基礎研究や教育に十分な人材や資源を配分できていないからだ。米スタンフォード大学はAI関連学科の学生が大きな比重だが、東京大学では農学部の学生が農林業就業者数の割合に比べても高い。経済成長率が低下すると学問分野間の配分の変更が難しくなる深刻な問題だ。

AI(人工知能)分野での大学ランキングを見ると中国の大学が上位を占め、100位以内に49校が入る。在米のトップクラスの研究者も半分近くが中国の大学を卒業した人々だ。これに対して日本の大学はゼロ。製造業の人材育成が中心で国の予算の配分も大幅に立ち遅れている。
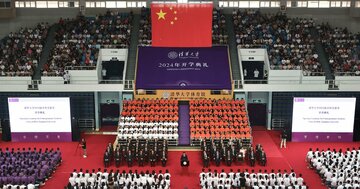
老朽化した社会資本の維持補修は「事前改修、予防保全」を行えば、事後保全の7割程度の費用で保全必要施設の9割程度を補修することができる。ただし最も重要なのは予算を増やすことで、リニアや先端半導体への助成などと社会資本保全の予算配分の優先度をきちんと判断する必要がある。

2024年の実質経済成長率はほぼゼロ成長になった。賃上げという望ましい事態が進行しているのに、なぜ成長率が低下するのか? それは賃上げが生産性の上昇でなく転嫁によって行われているからだ。このため実質賃金が上昇せず、実質消費が減少する。

GDPに対する投資割合の推移や国交省の試算によると、現存する社会資本のうち維持更新が可能なものは7割から8割程度と推計される。人口減少の下でコミュニティーの核である社会資本の全てを維持するのは不可能という厳しい現実を認識する必要がある。

埼玉県八潮市で下水道が破損し道路が陥没する事故が起きたが、2020年で耐用年数を超えた道路橋は30%、トンネルや港湾施設でも2割を占める。成長期に急速に整備された社会資本が今後、集中して加速度的に耐用年数を迎える。この維持補修は今後の日本で極めて重要で困難な課題だ。
