
野口悠紀雄
埼玉県八潮市で下水道が破損し道路が陥没する事故が起きたが、2020年で耐用年数を超えた道路橋は30%、トンネルや港湾施設でも2割を占める。成長期に急速に整備された社会資本が今後、集中して加速度的に耐用年数を迎える。この維持補修は今後の日本で極めて重要で困難な課題だ。

ソフトウエアエンジニアの平均報酬を見ると、日本はトップのアメリカ西海岸地域の3分の1以下だ。企業の時価総額ランキングや大学ランキングも同様で日本が世界最先端の経済活動から取り残されていることが分かる。追いつくには高等教育への投資が重要だが、現実には予算が削減されている。

「物価が上がれば経済が良くなる」と日本銀行は金融緩和を続け、高賃上げの波及を物価目標達成の重要なメルクマールとしてきた。しかし、高齢者などの無職世帯は物価高騰の影響だけを受けて実所得が減少し消費を切り詰めている。物価上昇を金科玉条のごとく目指す政策が誤っていることを示すものだ。

春闘などでの高賃上げの下でも実質賃金は4カ月連続マイナスとなっているのは、賃上げが生産性の上昇を伴わず価格転嫁によって行なわれているからだ。賃金が上がっても物価はさらに上がる「悪循環」であり、日本銀行がいまの状況を「物価と賃金の好循環」として肯定する限り、石破政権が掲げる実質賃金引き上げは実現できない。

日本製鉄によるUSスチール買収計画での日米の対応には不可解なことが多い。バイデン大統領の禁止命令は政治的な思惑による不合理な決定だと思うが、日本製鉄が生産量の拡大にこだわっているように見えるのも時代遅れの発想のように思われる。なぜ買収を進めようとするのか、理解できない。

2%物価目標」を掲げて金融政策が続けられてきたが、2022年以降、消費者物価上昇率は日銀が目的としてきた2%を超えているにもかかわらず、日本は異常な低成長から脱却できない。これは物価上昇率引き上げを目標とする金融政策が根本的に誤っていたことを意味する。

「高賃上げ」や「物価と賃金の好循環」が掲げられる中で名目賃金の伸びは著しいが、実質賃金はほとんど不変だ。賃上げ分が価格に転嫁され物価を上昇させているためだ。実質消費は増えず、むしろ「悪循環」が懸念される。この事態を避けるには生産性を上昇させるか、企業利益を圧縮するかしか方法がない。

日本人の英語能力は直近の国際機関の調査では世界92位だ。この言葉のギャップが国際競争力低下や経済の低生産性の一因になっていることは間違いない。これを克服する強力な手段として期待できるのがChatGPTだ。英語の勉強を進め、外国語文献の要約翻訳を簡単に手に入れることができる。

日本経済停滞の最大の要因は「近視眼的思考」による政策の失敗にある。生産性が向上しないことが経済低迷の一番の原因とわかっていながら、金融緩和や円安誘導など当面当座の対応で糊塗(こと)してきた。「103万円の壁」見直しもその典型だ。生産性向上には高度人材の育成が急務だ。

9月勤労統計調査でも現金給与総額は前年比2.6%と堅調だが、最近の賃金と物価の上昇は望ましい変化だと一般に考えられている。しかしいまの賃上げは消費者物価への転嫁、つまり消費者の負担で実現している。生産性上昇が伴わない賃上げは物価と賃金の悪循環をもたらす危険がある。

所得税の基礎控除引き上げの議論が本格化するが、所得税の負担率はこの数年間に急上昇したものの、長期的に見ると1990年代から2010年ごろまでは低下している。このところ必要性が希薄なバラマキ減税が実施されてきたことなども考えると、いまの時点で所得税の調整が必要なのかは検討の余地がある。

石破政権との政策協力で、国民民主党が「手取り収入を増やす」として求める所得税の基礎控除引き上げの主張は正しいのか。ここ数年、賃金上昇などによって「自動増税」になっていることを考えると調整は必要だが、問題は所得税制のどの部分について何を基準にどれだけの減税を行なうかだ。

米国はなぜ日本より豊かなのか?コロナワクチン開発の速さを見れば納得するしかない
コロナワクチン開発で示されたアメリカの「強さ」の理由は、世界各国から優秀な人材を受け入れ、能力を発揮できる機会を与えてきたことにある。その背景のひとつに、ナチの劣等民族根絶政策を受け、優れた科学者がドイツや近隣諸国から逃げ出した過去があった――。本稿は、野口悠紀雄『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

日本を破綻に導く「英国病」の再来か?平均賃上げ率5%超えも手放しで喜べないワケ
生産性が上がって付加価値が増えれば、賃金が上昇して消費が増加し、結果として経済成長率が高くなるというのが本来のセオリーだが、日本はそのちょうど逆の状態に落ち込んでいる。日本労働組合総連合会の2024年第1回集計における平均賃上げ率は5%を超え、一見喜ばしいことのようにも思えるが、じつは決して無視できない“ある危険”をはらんでいるという――。本稿は、野口悠紀雄『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
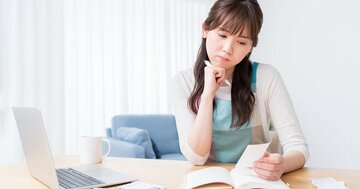
予算や税制で与野党の政策協力を打ち出した石破政権だが「部分連合」でさまざまな案を取り入れ総花的な政策になる結果、財政赤字が拡大しインフレになるリスクが生まれた。政権運営の安定化を図る思惑とは逆にインフレによって政治への不信や不満が強まり社会が不安定化しかねない。

日本が今よりもっと円安だった40年前と比べて、ずっと貧しくなった深刻な事情
今の異常な円安の原因は、世界の中央銀行が金融引き締めに転じたなか、日銀だけが過度な金融緩和を継続したことの結果といえる。日本経済にさまざまな問題を引き起こしているこの惨状を、どう立て直していくかが、日銀に課された大きな課題だ。はたして、その打開策とは?本稿は、野口悠紀雄『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

石破政権は緊急経済対策としてガソリン代や電気・ガス代の補助を延長する可能性が強いが、物価高対策は技術革新促進や労働生産性引き上げなどで実質賃金を引き上げる環境整備に重点を置くべきだ。補正予算についても規模ありきで中身が吟味されないのでは効果は期待できない。

今回の総選挙では実質賃金の引き上げを公約などに掲げる政党が目立つが、実現は価格転嫁によってできるほど簡単なものではない。王道は生産性の向上でありサービス業の中で新たなビジネスを生み出すなどによって産業構造を転換する大改革が必要だ。

総選挙が公示されたが、石破茂首相は自民党総裁選で語っていた利上げ支持や金融所得課税強化などの経済政策の主張を地方創成を除けばほぼ全て“否定”してしまった。しかし方向転換が選挙対策として適切だったとは考えられない。改革を望んで石破氏が率いる自民党に投票したであろう人の票を逃したことにならないか?

石破新政権はアベノミクスの徹底的な検証を行なうべきだ。これが誤った政策で成功するはずがなかったことは、異次元緩和などが続けられた約10年の日本経済を見ても明らかだ。新しい経済政策体系への移行や自らが掲げる防衛力強化や格差縮小の実現で正しい政策を実行するためにも、アベノミクスからの決別が必要だ。
