
山崎 元
政府は「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」を発表した。働き方改革の大きな柱として、特に非正規雇用労働者の総合的な待遇改善を目指したものと受け取ることができる。意欲的な試みといえるが、その目指すところが達成されるかどうか、さらに、どのような影響が出るのかについては、予断を許さない。
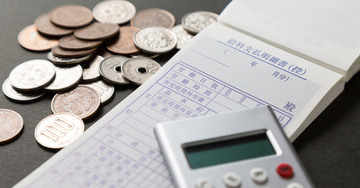
今、GPIFも日銀もインデックス運用(公表されている株価指数=インデックスと同じ銘柄と投資ウェイトで株式等を保有する運用方法)を拡大させている。インデックス運用が拡大すること、さらにインデックス運用を行う商品に個人や機関投資家が投資することの影響と可否について考える。

統合型リゾート施設、通称「カジノ法案」が今、国会を通過しそうな情勢だ。カジノ法案が成立する場合、次に大事なのは、日本にカジノをどのように位置づけて、どう活用するかだ。成人に達した息子や娘を親が連れて行き、ギャンブルの仕組みや作法を教えながら、一緒に楽しむような場所になるといいと、筆者は期待する。

「週刊ダイヤモンド」の直近発売号(12月10日号)に、「日銀“大株主化”のいびつ 1年後を初試算! 保有率上位30社」という記事があり、1年後の株主比率上位30銘柄の表が載っている。筆者も、日銀はETFによる株式購入をもう止めた方がいいのではないかと考えている。

11月25日、札幌にいた筆者の父が、90歳の誕生日を目前に亡くなった。近年、お墓やお葬式の方法、さらにはお寺との付き合いになどに悩む人が多いようだが、家族だけで、お坊さんなしで行なった我が家の弔いの様子を書く。

第453回
日本の「男子」は、生きにくいのではないか。東京大学が遠隔地出身の女子学生に月3万円の家賃補助を行うことを決めた、というニュースを見て、「本当に、そうかもしれない」と考えた。「男女平等」の理想を追求するに当たって、一時的にではあっても「女性優遇」を手段として使うことは不純であり、弊害を生む。

第452回
『ライフ・シフト』という本が話題になっている。著者達はロンドン・ビジネススクールの教授だが、長寿化が進行する前提の下で、個人及び社会がこれにどう対処したらいいのかを論じている。著者達は、現在の長寿化のペースが続くことを前提とすると、現在の子ども世代は自分の寿命が100歳を超える可能性を十分視野に入れて人生の計画を立てる必要があるという。

第451回
金融庁が先月発表した「金融行政方針(平成28事務年度版)」からは、従来の政策方針から、金融業の顧客の視点に立つ方向に転換しようとする姿勢が伝わってくる。金融機関の監督官庁である金融庁が、これから何をしようとしていて、それが金融機関の顧客である個人、特に投資家にとってどのような意味を持つことになりそうなのかを検討してみよう。

第450回
ヤフーが、同社が「ポテンシャル採用」と名付けた、いわゆる通年採用の仕組みを導入すると発表した。理念として、通年採用には好ましい面があることが理解されつつも、現実には、今ひとつ拡がりを見せていない。今後、通年採用が拡がる可能性と、そのメリットにはどのようなものがあるのだろうか。

第449回
高齢者は日本の金融資産の圧倒的に大きな部分を持っており、金融機関のリテール・ビジネスのターゲットとなっている。そんな高齢者には高齢者特有の判断ミスの癖が幾つかあるように思われる。そこで、高齢者がお金を運用する上で特に気をつけておきたいポイントを3つご説明する。

第448回
最新号の『週刊ダイヤモンド』(2016年10月22日号)は「退職金・年金」特集だ。特集のパート1の冒頭では、筆者とFPの岩城みずほ氏が解説する「手取り年収のうち、いくら貯蓄すべきか」を求める「人生設計の基本公式」が掲載されている。ここでは、この基本公式と資産運用の関係を解説しよう。

第447回
世の中には、その建前に対しては有効な反論が全くないのに、実現しないものがある。「歳入庁」がそのひとつだ。これまでも歳入庁の設立の構想はあったが、これが大きな流れになったことは一度もない。それは一体なぜか。

第446回
外貨建ての保険は、目下、銀行などの金融機関が販売に力を入れている商品である一方、前々回の本連載「金融庁がダメ出しする運用商品ワースト3」でも取り上げた通り、顧客の側にとって問題の多い商品だ。この、金融庁認定済みのダメ商品がどのような着眼点で売られているのかを見てみよう。

第445回
ヤフーが、全従業員約5800人を対象に週休3日制の導入を検討しているという。筆者は強く支持する。ヤフーの社員は、生産性を上げながら、自分の人生をより濃く楽しむことができるようになるだろうし、会社にとっては、望ましい刺激をより多く取り込むことにつながるだろう。

第444回
先般、金融庁から「平成27事務年度版 金融レポート」が発表された。森信親氏が長官に就任して以来、金融庁が従来のやや金融業界寄りの立ち位置を、顧客寄りに修正したこともあり、なかなか面白いレポートになっている。金融レポートの記述をよく読むと、金融庁が、この商品は投資家のためになっていないと考えていることが「滲み出てくる」ようにレポートは書かれている。

第443回
現在、築地市場の移転問題で話題を集めている小池百合子都知事が、都知事選の公約でもあった知事の報酬半減を打ち出した。公約だったのだから当然とも言えるが、ボーナスを含めた全報酬の半減であれば、年収が約1450万円となって、都議会議員の1700万円と逆転するという。

第442回
ロート製薬が、社員の副業を正式に認め、かつ後押しもするような新しい制度を導入して話題になっている。できれば、もう一歩進めて、副業が原則自由でなければならないことを法制化し、副業を禁止できる例外規定を狭い範囲で明確化するなど、公的な制度として、副業を後押ししてほしい。

第441回
現在発売号の『週刊ダイヤモンド』(9月3日号)の特集は、「金融エリートの没落」という刺激的なタイトルだ。「没落」の構図を大まかに言うと、「マイナス金利政策」と「AI・フィンテック」の2つが大きなポイントだ。AI・フィンテック絡みで、将来なくなる金融職種は何だろうか。

第440回
ドイツ連銀が、将来的に、法定定年を69歳まで延長すべきだと提言して話題になっている。日本はドイツよりもさらに平均寿命が長い国なのだから、年金支給開始年齢引き上げ、定年の引き上げは自然な政策だと思われる。

第439回
老後のお金の問題などについて、「老後にはいくら必要ですか?」と漠然と聞いて、大きな金額に不安を覚えて、むやみにリスクを取る資産運用に走る方がいるが、こうした問題について、冷静に考える方法論を持っておくといい。そのための「基本公式」を伝授しよう。
