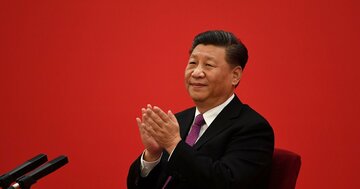加藤嘉一
今年7月、中国共産党は結党100周年を迎える。中国政治にとっての大きな節目の季節に当たって、現状を整理し、この先の中国の針路について分析を加えることは本連載の核心的課題である。今回は、強硬的な姿勢を強める中国の「国際社会での信用」がこれからどうなっていくのかを論じてみたい。

世界一の「人口大国」で高齢化が深刻な状況だ。人口減少が進めば、中国共産党の信頼性や求心力にも影響を及ぼす可能性がある。高齢化によって顕在化する3つのリスクを解説する。

中国・習近平政権が目下、最も懸念している不安要素の一つが「新疆ウイグル問題」である。これは人権問題にとどまらず、関連諸国との経済関係にも影響を及ぼし、ひいてはこの問題をきっかけに中国共産党の政策や統治能力の信用性に疑問が投げかけられかねないという大きなリスクをはらんでいる。

4月16日、菅義偉首相とジョー・バイデン米大統領が初めてホワイトハウスで会談を行った。その焦点は、終始「中国にどう対するか」であった。共同声明にも表れた中国への牽制と、その会談内容に対する中国の反応から今後の外交関係のポイントを占う。

前回のコラム『中国共産党が国内外で喧伝するプロパガンダ、「中国式民主」の正体』では、中国共産党が「中国式民主」という産物を国内外にアピールしていることを取り上げた。中国は政治、人権、発展モデルといったものが、西側諸国の価値観と比較して優位であることを宣伝し、チャイナスタンダードをグローバルスタンダードに昇華させようと試みているといえる。
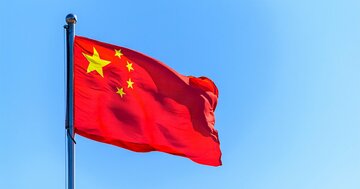
中国共産党の高官が米国閣僚と対面式での会談を行った。そこで出席した中国の楊潔篪政治局委員は、米国側を強くけん制した。このところ、中国共産党が国内外においてしきりにアピールする概念がある。それが、「中国式民主」だ。この意味するところとは何なのか。三つの要素からひも解いてみたい。

中国で全国人民代表大会(通称「全人代」)が開幕した。注目されていた点の一つが、国内総生産(GDP)の成長目標が公表されるかどうかだ。昨年は、コロナ禍の不安定な情勢を理由に公表されなかった。そうした中で李克強首相は、「+6.0%以上」と数字を公表した。この数字をどう見るか。

物議を醸してきた香港版「国家安全法」が施行されてからもうすぐ8カ月になる。香港は今、どのような状況にあるのか。筆者は自身の体験から、中国共産党の影響力が強まってきていることを感じている。香港の現状をレポートするとともに、今後、われわれが香港とどう向き合っていくべきなのかを考察したい。

ミャンマーで軍事クーデターが勃発した。同国と国境を接する中国の公式な対応は、違和感を覚えるほどシンプルなものだった。一方で、中国共産党は今回の軍事クーデターを、習近平率いる中国共産党の正統性を国内外でアピールするためにうまく利用する可能性がある。

米国でバイデン政権が発足した。トランプ政権時代に最悪の状態にまで陥った米中関係は今後どうなるのか。バイデン政権の対中政策を読み解くポイントは4つある。また、新政権の動向によっては、過去4年以上に米中関係が悪化する可能性も否定できない――。

2021年は中国共産党にとって、大きな節目の年である。中国共産党結党100周年を迎えるからだ。来秋には党の第20回大会が開かれる。習近平共産党総書記は、国内外のリスクや不確実性を封じ込め、党の正当性を死守すべく邁進するだろう。その際に課題となり得る5つのリスクについて解説しよう。

大ベストセラー書籍『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年)の著者で社会学者のエズラ・ヴォ―ゲル・ハーバード大学名誉教授が12月20日、逝去した。ヴォ―ゲル氏は日本語と中国語を自在に操り、現地の人々と交流し、研究を深めてきた。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』は、日米貿易摩擦が激化していた当時、戦後の日本が高度成長を遂げた要因について社会や企業、家庭のありかたを分析した内容で、本来の目的は「米国への戒め・参考になること」だったという。晩年、ヴォ―ゲル教授と親交が深く、共著をまとめた加藤嘉一氏に先生との思い出を寄稿してもらった。

先月25日、米大統領選挙から20日以上の時間を経て、習近平国家主席がジョー・バイデン氏に祝電を送った。その内容をひも解くと、中国共産党が抱く対米関係への「3つの本音」が透けて見えた。
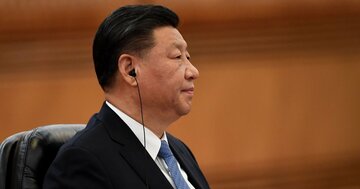
先月行われたAPEC首脳会議において、中国の習近平国家主席は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)に初めて言及し、従来の立場よりも踏み込んだ意思を見せた。この姿勢の変化にはどんな意味があるのか。中国共産党のこれまでの動きを基に考察したい。
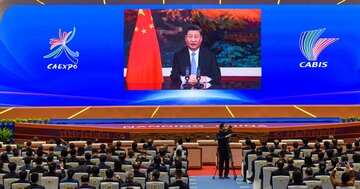
「バイデン勝利」を中国はどう受け止めているのか。中国共産党が“バイデン政権”に対して抱く期待と危機感を明らかにしてみたい。

10月26~29日に開催された、中国共産党第19期中央委員会第5回全体会議(五中全会)。2016年~20年の5年間を総括し、次の5年に向けた国家戦略や政策方針が審議・採択された。ちょうど5年前に行われた全会と今回の内容を比較してみると、習近平政権の「現在地」と向かおうとしている方向が見えてきた。

今月14日、中国共産党の最高指導者である習近平総書記は深センで行われた式典に出席した。実は、習氏は8年前、共産党総書記の座に就いたばかりのときにもその地を訪れている。そのときの訪問が世間に与えた「印象」は、今回のそれとは全く異なるものだった。

約1カ月後に迫った米大統領選。世論調査などではバイデン氏有利と見られているが、トランプ氏が逆転の切り札を持っているという推測も後を絶たない。では、中国は今回の米大統領選をどう見ているか。前回の“反省”を踏まえ、トランプ、バイデンどちらになっても希望的観測はできない状況にあるといえる。

中国国内では依然として問題が山積している。にもかかわらず、エリートや中産階級ですらなぜ自国の問題に目を向けようとしないのか。今回は、「中国人民たちは、なぜ習近平や中国共産党に反旗を翻さないのか」について考えてみたい。

硬直化する米中関係。中でも中国共産党指導部が最も警戒するトランプ政権の動向が、中国共産党と中国人民の間柄を切り裂くというものである。しかし、そうした「切り裂き策」は、本当に中国人民の意識を変えることができるのだろうか。