
加藤嘉一
ロシアがウクライナに侵攻して6週間が経過しようとしている。そうした中、4月1日、中国・EU首脳会議がオンライン上で開催された。この会議における習近平国家主席の発言は、中国のウクライナ危機への対応、そして欧州に対する立場を体現したものだった。どのような発言だったのか。詳細と、その意図について考察してみたい。

ロシアがウクライナへの侵攻を開始して、間もなく1カ月になる。停戦交渉は行われているが、依然として危機が収束する糸口は見えていない。米国、EUなど西側諸国とウクライナが一致団結しているとも言い難い。状況が“泥沼化”する中で、注目を集めるのが中国の動向だ。「中国がロシアに見切りをつけ、欧米側につくのでは」と見る専門家もいる。本当にその可能性はあるのだろうか。

ロシアがウクライナに侵攻し、もうすぐ2週間になる。国連総会でロシア非難決議案の採択を棄権した中国の今後の動向にも注目が集まっている。秋に5年に1度の党大会を控える中国では5日、全国人民代表大会(全人代)が開幕した。習近平率いる中国共産党は、ウクライナ危機をどう対処しようとしているのか。またその先に描く目標とは。

ウクライナ情勢が緊迫した状況が続いている。この危機に対して、中国はどのように対処しようとしているのか。中国当局の姿勢は極めて慎重であるといえる。しかし、その慎重に表明している立場からは、迫りくる台湾有事を見据えて“伏線”を張っている様子がうかがえる。中国のウクライナ危機に対する姿勢の特徴と、その意味することとは。

北京冬季五輪が開幕した。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続く中、厳しい対策を行っての開催となっている。2月4日に行われた開会式では、14年前の夏季五輪と同じく張芸謀監督が総監督を務めた。ただ、そこで表現されたメッセージは当時とは大きく異なるものだった。今回の開会式からは、14年の発展を経た中国の戦略と野心が垣間見えた。

中国の習近平国家主席が、1月17日に開催された世界経済フォーラム(通称「ダボス会議」)によるオンライン形式の準備会議「ダボス・アジェンダ」で、トップバッターとして基調講演を行った。2022年は習近平にとって、政権3期目の突入がかかる重要な1年だ。そんな今年、中国が長らく政治活動の場として重視してきたダボスの舞台で、習近平は何を語ったのか。注目すべき「三つのアピールポイント」について解説する。

2022年は、中国にとって最も重要で肝心な年になるだろう。2022年を通じた政治情勢の推移次第で、中国という「党国」の進路が質的に変わってくるからである。習近平一強といえる現在の中国共産党の基盤を揺るがしかねない「四つの不安要素」とは。今年、注視すべきポイントを解説する。

12月19日、香港で立法会(議会)選挙が実施された。「国家安全維持法」を強行採択、選挙制度の見直しを経て、行われた初めての選挙では、香港が“北京化”する現状が浮き彫りになった。全議席が実質親中派で埋まり、民主派は姿を消した。中国共産党指導部の支配が強まる中、国際金融センターとしての性格を持つ香港は今後どうなっていくのだろうか。

対中包囲網が強化されている。先週末に開催されたG7外相会合では、中国への対応が主要な議題となった。こうした国際社会の動きに対して、中国も静観しているわけではない。12月、中国が発表したある声明文には、この包囲網を打ち砕こうとする姿勢が示されていた。それは、「中国は民主主義国家である」とアピールするものだった。中国がそう主張する根拠とは何なのか。また国際社会はこの中国の主張にどう対峙すべきなのか。

新型コロナウイルス、電力不足、資源高……さまざまな問題が中国経済に影響を与えているが、依然として市場関係者から高い関心を集めているのが、「恒大ショック」である。中国当局は、この債務危機が不動産産業や経済全体に与える影響を最小限にとどめようと、恒大集団に緻密な指導を行っている。同社の今後の行方は、中国経済を考える上でも注目に値する。最近の動向とその背景にある習近平政権の影響を詳しく解説する。

11月8~11日、北京で第19期中央委員会第6回全体会議(6中全会)が開かれ、中国共産党にとって史上3度目となる「歴史決議」が採択された。この歴史決議は習近平体制の中国共産党においてどのような意味を持つのか。これまでの歴史、そして6中全会閉幕翌日に発表されたコミュニケを踏まえると、習近平の強い“意志”を読み取ることができる。

台湾海峡リスクが高まっている。米国、台湾は米台連携の姿勢を打ち出しているが、こうした動きに対して中国政府は反発している。では、台湾問題をめぐって中国が武力行使に出る可能性はあるのだろうか。情勢を読み解く上で重要な米中の動きと、習近平率いる中国共産党指導部の立場について整理してみたい。

企業への規制強化や恒大ショックなど、中国経済に不安を感じさせる出来事が続いている。ただ、これらはあくまで表象にすぎない。根幹にあるのは、「習近平時代」そのものだ。そうした大きな変化を感じさせる出来事があった。党中央などが制定した『綱要』で、「標準化」に関する広範囲にわたる具体的な方針が示されたのだ。日本企業を含む外国企業も無縁ではいられない、この動向について詳しく解説する。

中国の不動産大手、中国恒大集団がデフォルト(債務不履行)危機に陥っている。中国版リーマンショックとも称され、世界中からその動向には大きな注目が集まっている。とりわけ世界の政府、市場関係者が注視しているのが、「習近平率いる中国共産党は、恒大集団を救済するのか」ということだ。中国共産党の動向を読み解くには、この危機を戦略的に利用しようという当局の思惑を理解する必要がある。

中国共産党が「共同富裕」構想を掲げる中、各国の政策担当者、市場関係者からは「文化大革命」の再来ではないかという懸念の声も上がっている。こうした中で中国共産党は、民間企業や経済を尊重していく方針に変わりはないことを強く主張。中国共産党の動きに見られる「振り子の論理」について考察する。
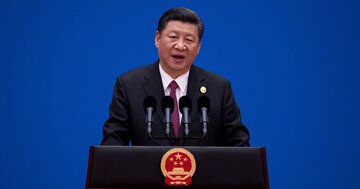
習近平総書記が党中央の重要政治会議で「共同富裕」を掲げた。これを受け、アリババやテンセントなど、中国の巨大IT企業はこぞってこの領域に資金投入を表明している。中国企業のみならず、中国でビジネスを行う日本企業にも大いに関係する中国共産党の変化について、歴史、近年の動向を踏まえて解説する。
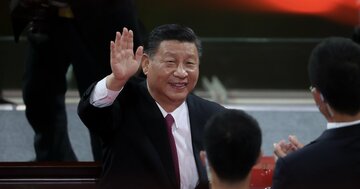
イスラム主義組織タリバンがアフガニスタンの首都カブールを占拠し、実権を掌握した。混迷するアフガン情勢は、米中関係にも影響を及ぼしそうだ。現時点での中国はアフガン情勢に対してどのような意図で、どのような戦略を描いているのか。三つのポイントについて解説する。

世界保健機関(WHO)は、中国に対して2度目の新型コロナウイルス発生源調査を実施する計画を公表した。これを中国は実質的に拒否。厳しい姿勢を見せている。背景には、米国に対する警戒とけん制の姿勢が見て取れる。バイデン政権発足から半年が経過したが、米中関係に改善の兆しは見られず、むしろ悪化の一途をたどる。今回はいくつか例を挙げながら、米中関係の実態と今後の可能性について解説する。

7月1日、中国共産党が結党100周年式典を終え、101年目に入った。百周年の全てのイベントの中で、最も重要だったのが習近平による重要談話であることは論を待たない。筆者も生中継で観た。本稿では以下、「習近平七・一談話」(以下「談話」)の内容や場面から、中国共産党率いる中国が今後何処へ向かうのかを考えてみたい。

7月1日、中国共産党は結党100周年を迎える。これに当たって、入念な式典準備が進められるとともに、メディアへの監視、統制の目が厳しくなっている。先日、共産党に批判的な報道を繰り広げてきた香港紙『リンゴ日報』は廃刊に至った。このことを中国共産党は支持、歓迎してコメントしている。大きな節目を前に「紅色」一色に突き進む中国は、これからどうなっていくのか。現状と今後の可能性を考察する。
