
加藤嘉一
香港に駐在する中国共産党のある幹部との議論を通して、日本政府が香港情勢について懸念を表明していることについて、中国共産党は日本が強硬姿勢に転じたと感じていることがわかった。しかも、日本が米国に圧力を受けて強硬になったと考えているようだった。なぜこうした理解、考えになるのだろうか。
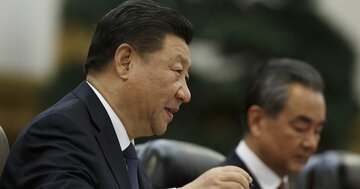
香港情勢がコロナと政治の狭間で揺れている。林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官率いる香港特別行政区政府、そしてその背後で同氏、同政府を指揮する中国共産党指導部は、コロナ禍に便乗して民主派活動家や反中、反共感情の封じ込めようとしているのだ。

米中関係が迷走している。近年、貿易戦争、科学技術や国防要素をめぐる攻防、香港、新疆ウイグル、台湾問題、そしてコロナウイルスの発生源をめぐる口論など、両国関係は複合的、構造的に緊張の一途を辿ってきた。改善の突破口を見いだせない中、ある意味これまでとは異なる次元で、米中外交関係の悪化を露呈する事態が発生した。

最近、香港の知識層の間である本が注目を集めている。それは中国寄りの学者が書いた本で、5年前に出版されたものだ。その背景を探ってみると、そこには香港版国家安全法を制定、実施し、管理強化を進める中国本土の動きが透けて見える。香港の「北京化」が着実に進んでいる。

なぜここに来て「中国問題」が山積しているのだろうか?筆者は、中国共産党が政治的に後退しているというのが、根源的な理由だと考えている。そんな中で先日、国際社会の中国共産党への不信と警戒を助長し、香港、台湾、米中を含めた「中国問題」の解決をさらに困難にさせると痛感せざるを得なかった現象に出くわした。それは中国共産党の幹部を養成する教育の重要拠点、中央党校直属の機関紙『学習時報』の掲載された論考だった。
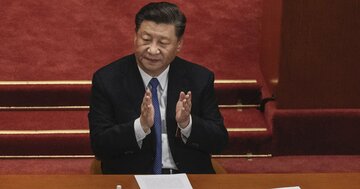
香港では「国歌法」が成立。次の焦点は香港版「国家安全法」を根拠に、どの範囲・程度の行為および活動まで取り締まるのか、そして同法の施行が引き金となり「一国二制度」「高度な自治」が有名無実化するのかどうかだ。最近の中国共産党幹部の発言から、中央政府の思惑を探ってみたい。

全国人民代表大会(全人代)が閉幕した。全人代の議題から習近平総書記率いる中国共産党の現在地を5つの問題、すなわち経済、1つ目の「百年目標」、香港問題、台湾問題、米中関係から検証してみたい。

5月24日、香港では「香港版国家安全法」に抗議するため、大規模なデモが行われた。香港社会では「一国二制度」が終焉する、香港が社会主義化されるといった懸念や恐怖が広がっている。デモの背景を解説するとともに、最前線をレポートする。

5月22日、全国人民代表大会(全人代)が北京で開幕する。新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」)の影響を受け、開幕は約2カ月半延期された。世界が依然としてコロナと戦い、決して予断を許さない状況にある中での開催にあたり、習近平総書記率いる中国共産党指導部はどのような政策目標を公表するのだろうか。

第173回
中国のコロナ対策は、海外からのウイルス逆輸入を防ぎつつ、経済復興のためにかじを切る段階に突入しているように見受けられる。そのために、共産党指導部はコロナ情勢を把握し、トップダウンで指示を出すことに奔走している。

今回欧米や日本を含めた自由民主主義、資本主義、先進国家がコロナの抑制に「失敗」した場合、中国の政治体制、発展モデル、イデオロギーはますます膨張し、正当化され、我々の前に差し迫ってくるだろう。

コロナショックは本連載の核心的テーマである中国民主化研究にも、様々な示唆を与えている。習近平率いる中国共産党が中国をどこへ導こうとしているのかが垣間見える。コロナ外交に露見される各種現象は、習近平政権の現在地を如実に物語っている。例として、最近ヒートアップしている駐在記者駆逐問題をめぐる米中の応酬にも、コロナ外交の底流にある中国共産党の姿勢が見て取れる。

170回
新型コロナウイルス対策に関する中国共産党の一連の対策を通して、中国の世論は「中国の特色ある社会主義の優位性を示した」、「中国の責任ある大国としての役割を果たした」という“いつもの論調”に帰結すると見ている。党はそのような論調で今回の危機を突破したがっているし、人民も党のそういうパフォーマンスを見るのを心待ちにしている。

第169回
習近平総書記は新型肺炎を政権発足以来、最大の統治危機として認識している。最も重要な政治会議の一つである3月の全人代を延期する予定であることからも、如何に習近平が新型肺炎対策を重視しているかが分かる。ただ、その発言や施策を観察すると、全ては中国共産党の正統性の維持と強化のためであることが透けて見えてくる。

第168回
湖北省武漢市から広がったとされる新型コロナウイルスが中国全土を襲い、世界を震撼させている。今回の事態が2003年のSARSと比べてどこまで深刻なのかに関してはもう少し状況を見ていかなければ分からないだろうが、中国と感染病というテーマからすれば、この17年で最大の危険が発生していると見るべきであろう。

第167回
20年1月11日、台湾は再び総統、立法委員ダブル選挙を迎えた。結果は蔡候補が台湾民主選挙史上最高記録となる817万票(獲票率57.13%)を獲得し、韓候補に圧勝した。今回の台湾総統選の結果を作り出した背景の根本が、北京に見いだせるのは火を見るよりも明らかである。筆者が常々指摘している、習近平新時代における「対内圧制、対外拡張」的な政策である。

第166回
12月13日、米中貿易協定の第一段階の合意に至った。2019年の米中関係はこの貿易協定だけではなく、香港問題などもあり、激動を極めた。そんな1年を経て、中国側は米中国力対比と自国の国益に関する綿密な分析と評価に基づいて、対米政策において「デカップリング」(切り離し)という戦術(戦略ではない)を取っていくと筆者は推察している。

第165回
4年に一度行われる区議会選挙では、計18の選挙区、452の議席が争われた。今回は、「逃亡犯条例」改正を引き金に、「一国二制度」のあり方、香港社会の自由と民主主義、政府や警察の市民への対応、そして中国共産党の意図や出方などをめぐって発生してきた一連の現象を経て、民主派と親中派がどうぶつかり合うかに焦点が集まっていた。

第164回
11月2日、習近平本人が公の場で「民主」に言及した。これは非常にまれなことである。少なくとも筆者にとっては非常に新鮮に映った。中国民主化研究と題する本連載にとっても、貴重な素材として検証に値するものであるといえる。そこで、中国共産党の「民主」について考えてみたい。
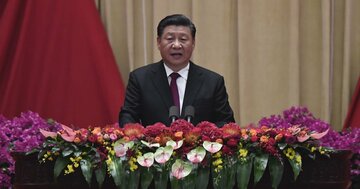
第163回
香港情勢が混乱から抜け出せずにいる。警察と市民の間の衝突は収まる気配はない。香港はどこへ向かっていくのか。前編に続き、香港で生まれ育ち、米英で教育を受けた気鋭の国際関係学者、オピニオン・リーダーである瀋旭暉(Simon Shen)氏へのインタビュー後編をお届けする。
