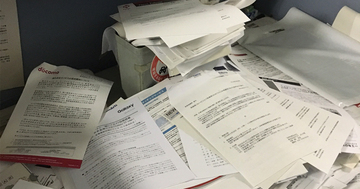山口 博
第64回
文部科学省事務次官も関与した組織的な「天下り」のあっせんは、同省人事課がご丁寧にも文書作成するというトンデモな事態である。同省に教育行政を仕切る資格はない。しかし、そのこと以上に、この組織を解散しなければならない理由がある。

第63回
わが国を代表する企業が、次々と労働基準法違反で摘発されている。そして、20時一斉消灯など強硬手段に出る企業や団体が増えている。しかし、一斉消灯は過長労働問題の解決にはならず、むしろ逆効果である。

第62回
リーダーシップ演習を実施していると、勘違いマネジメントが横行していることに気付く。部下の育成を阻害しているのは、部下の適性、努力不足と決めつけられがちだが、上司が部下の意欲を粉砕している事例が実に多いのだ。

第61回
ピコ太郎「PPAP」の勢いが止まらない。公式チャンネルの動画視聴回数は1億回を超え、世界一だ。ビジネスパーソンの表現力向上プログラムを実施しているグローバルトレーニングトレーナーとしての目で見ると、実は、それには明快な理由がある。

第60回
「働き方改革実現会議」で、「同一労働同一賃金の実現に向けた検討」が進んでいる。しかし、その検討内容は、私の目からみれば過去の失敗の二の舞を演じるように思えてならない。忘れ去られている重要な論点があるのだ。

第59回
企業のシニア層対策が効を奏していない。結局、シニア層を閑職に追いやるなどの切り捨て施策しかとられていないのだ。しかしあきらめるのはまだ早い。75%のシニア層が再生した、とても簡単な方法がある。この方法は、高い忠誠心を持つシニア層を多く抱えるビジネス構造を逆手にとった、わが国固有のビジネス発展モデルになるに違いない。

第58回
ストレスチェックの期限が到来するが、本来目的であるストレスの軽減のためには、ストレッサーからの攻撃をまともに受けないことが肝要だ。業務山積という最もストレスを受けやすい状況から脱却する、誰でもできる簡単な方法がある。
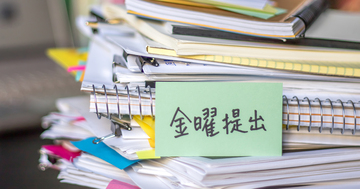
第57回
企業が実施義務を負う社員の「ストレスチェック」の期限が迫っている。社員に無理矢理実施させ、社員のストレスを増加させている企業も散見される。ストレスチェックをやれば、社員のメンタルヘルス管理ができるというものではない。特に人に関するストレッサーをなくすこと、そのための業務指示やコミュニケーションの改善が不可欠なのだ。

第56回
二刀流を実現している大谷翔平選手に対して、投手か野手かのどちらかに徹するべきだという見解が強い。ビジネスパーソンにおいても、専門性を高めるべきだという論調が依然主流派だ。しかし私は、わが国のビジネスパーソンにリアル二刀流を薦めたい。新しいビジネスモデル開発の担い手は、リアル二刀流の実践者から現れると思うからだ。

第55回
電通新入社員の自殺が労災認定されるなど、労災事故は後を絶たない。私はその原因は、間違った価値観の押し付けにあると思えてならない。なおかつ、画一主義こそチームワークであるという誤認識が悲劇を生み続けるのではないか。異なるモチベーションエリアの個々の特性を生かしてこそ、強い組織はつくれるのだ。
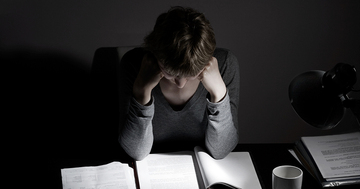
第54回
新しい取り組みを提案すると、即座に「できない理由」「してはいけない理由」を山のように探し出し、社員のチャレンジを阻止する企業がある。行き過ぎた「リスク過敏症」に冒された企業からはイノベーションが出てくるはずもなく、社内の雰囲気は停滞する一方だ。

第53回
社員の健康に留意しつつ、ビジネスの伸展を図ることはもちろん不可欠なことだが、残業時間削減キャンペーン、有給休暇取得の義務化に見られるような一律の運用は、逆にビジネスを阻害する。例外を頑として認めないトンデモ人事部のマインドは、滑稽ですらある。

第52回
採用面接で候補者に名刺すら渡さなかったり、出入りの業者だからといって、ぞんざいに扱うことについて、何の疑問も持たない会社は数多い。しかし、社外からの訪問者という意味合いでは、彼らも立派な「お客さま」。こうした人たちにまともな対応ができない会社は日々、無意識のうちに自社のイメージに泥を塗っていると思った方が良い。

第51回
さまざまな部署を経験する人がいるかと思えば、1つの部署に数十年も留まる人もいるなど、企業の人事異動のパターンはさまざまだ。しかし、どうやら同じ部署に居続けることは、本人のキャリア形成にもマイナスに働くばかりか、時として会社にも大きな損害を与えることにつながりかねないようだ。

第50回
約500人のビジネスパーソンの肉食度、草食度を測定したところ、顕著な結果が出た。草食度の高い組織に肉食度の高い自分が入ったら、やりにくいことは目に見えている。相手の肉食度、草食度に合わせたコミュニケーションも必要だ。

第49回
M&A件数は5年連続で増加し、今年も昨年を上回る、年間2,500件を超える勢いである。M&A後の統合を実現するためのアクションプラン「100日プラン」は普及しているように思えるが、たった一言でM&Aを失敗させてしまうトンデモ事例が後を絶たない。

第48回
自分にあったサイズを聞いても教えてくれないショップが増えている。その理由は、購入後に苦情が来た際の言質を与えないためだという。人事部の十八番だった責任放棄マインドが、営業部門に伝播し、ついに、現場の店舗にまで及んでしまった感がある。

第47回
キャリア形成や能力開発を望まない割合が史上最多…今年の新入社員について、衝撃的な調査結果が発表された。学校教育でヤル気を減らした彼らは、新入社員研修でさらにヤル気をそがれているのではないだろうか。

「不適切ではあるが、法律違反ではない」ので問題ない――このような論調が、しばしばまかり通っている。実は、この論調、ビジネスの世界でも、よく用いられている。そして知らず知らずのうちに、この見解をとることの違和感が麻痺してしまうケースが多発しているのだ。

第45回
企業広報担当者の主要業務ともいえる、記者クラブにおけるニュースリリース配布。これが効果を挙げていない。にもかかわらず、企業広報担当者は、配布し続ける。企業広報担当者にトンデモな思考が蔓延しているのだ。