
大江英樹
新型コロナで株価が下落している。今後を正確に予測することは誰にもできないから、不安ばかりが募ってパニックを起こしがちだが、こんなときに個人投資家がすべき最良の策はただ1つである。

昨年12月の税制改正大綱で、iDeCoの利用方法が変わる方向が示された。新しいタイプのNISAほどではないにしても、iDeCoの改正案もかなり複雑。勘違いしないように、よく理解する必要がある。

新型肺炎の蔓延で、株式市場の先行きに不安を持っている投資家は少なくないだろう。しかし、こんな時こそ考えたいのは「売るべきか否か」の判断基準。実は多くの投資家が、売るべき時に売らず、持ち続けるべき時に売っている。

公的年金にまつわる誤解はいくつもあるが、マスコミや評論家でも正しく理解していない人が多いのが「年金積立金」である。

企業型確定拠出年金に「高コスト」の投資信託が増える傾向にあると報道され、話題になっている。加入者にとって不利益なことが起きている背景には、制度の仕組みの問題がある。

「積立投資をすれば安全」といったうたい文句をしばしば目にするが、株式であれ債券であれ、投資には一定のリスクはつきもの。安易な思い込みによる投資は危険である。

こまめな消灯や交際費削減など、細かな節約を続けるとなるとかなりのストレスになる。そんなストレスを感じずに節約できる方法を考えてみよう。

この数年、退職者の人たちで投資を始めた人も多いだろう。退職者や高齢者が株式投資することについては賛否両論があるだろうが、筆者は別に悪いことではないと思っている。ただし、その目的とやり方は間違えないようにしなければならない。具体的にどういうことに気をつけて始めるべきか、考えてみたい。
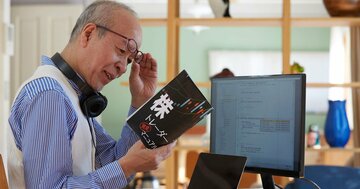
キャッシュレス決済の浸透率がまだまだ低い日本。背景には根強い現金信仰があると見られているが、現金をありがたがることは合理的ではない。貨幣の成り立ちから、その理由を考えてみよう。

差額ベッド代や食事代を賄うのは、医療保険か貯蓄か――。これを合理的に考えてみると、意外にも医療保険に入る意味はあまりないという結論になる。

軽減税率やキャッシュレス決済による還元も悪くないが、やはり家計に一番効くのは「無駄な買い物をやめる」こと。そこで今回は、心理的アプローチを利用した「買い物を慎重にする」方法をお伝えしよう。

先頃、公的年金の財政検証が発表になったが、年金について多くの人が誤解していることがある。それは、年金を老後の生活をまかなうための貯蓄だと思っていることだ。

投資の世界では、プロをしのぐ運用成績を上げるアマが大勢いる。その理由は、アマだけが持つ意外なアドバンテージにある。

実態以上にネガティブなイメージで見られがちな、日本の公的年金制度。5年に一度実施される「財政検証」の結果がこのほど発表されたので、実際どうなのか考えてみよう。

定年後の生活をイメージできないサラリーマン男性は少なくない。そして定年後に家に引きこもるのも圧倒的に男性だという。なぜ日本の男性は定年後を楽しめないのだろうか?

QRコード決済の会社の「キャッシュバックキャンペーン」が目を引くが、「一律無料」よりも、はるかに大きな効果を持つキャンペーンの方法がある。

日本で投資が増えないのは、金融リテラシーが低いから――そう考える人は多いが、実はアメリカ人と比較して、日本人の金融リテラシーはさほど低いとは言えない。むしろ、日本人に欠けているのは「税と社会保険」についての知識である。

iDeCoの加入者増加によって、今や民間企業従業員の7人に1人が確定拠出年金の加入者という時代になった。自分で自分の年金を運用する際、守らなければならないルールが1つある。

6月初めに出された、金融庁の市場ワーキング・グループがまとめた報告書が世間を騒がせている。この問題については、いろいろと残念なことが多い。そもそものメディアの取り上げ方が根本的に間違っていたし、それを政権攻撃の材料にしようとする野党、年金が問題化することを恐れて受け取り拒否などという暴挙に出た金融担当大臣、そして何よりも「年金」と聞いただけで脊髄反射的に「破綻だ」「詐欺だ」と騒ぐ一部の人たち。いずれも実に残念としか言いようがない。

「職場積立NISA」は良い商品である。しかし、これは事業主が従業員のために導入する制度で、肝心の事業主が採用してくれない限りは広まらない。そして、この事業主への営業がかなりの難所である。
