
大江英樹
「70歳までの雇用義務を努力規定化する」という方向などが打ち出されたため、公的年金の支給開始年齢を現行の原則65歳から70歳、あるいは75歳まで引き上げられるのでは?という憶測が広がっているが、これは勘違いである。

様々な情報を分析する必要がある株式投資。その心理的負担から逃れるためか、プロに「必勝銘柄」を聞きたがる投資家は少なくない。しかし、宗教のように「信ずる者は救われる」ということはなく、むしろ投資は「信ずる者は騙される」シビアな世界である。

「投資」の考え方についてはさまざまな立場の人が発言しているが、その中でよく出てくる考え方に「投資は社会の役に立つ、とてもいいことだけど、投機は単にお金を転がすマネーゲームだから決して好ましいものではない」というのがある。

業界最大手・野村證券が店舗の2割を閉鎖すると報道された。しかし、ネット証券がいかに便利になろうとも、対面型販売を好む顧客は一定数存在する。

先日、マリナーズのイチロー選手が引退した。日本で9年、米国で19年の通算28年の現役生活。その間、常に超一流の選手で居続けたことは本当に素晴らしいことだ。だが、それだけではない。報酬の受け取り方も実に素晴らしいのだ。

確定拠出年金の加入者が690万人に達し、重要な老後資産形成制度になってきた。しかし、その運用の中身を見ると、定期預金や保険商品などが半分を占めている。しかも、自分で商品を選んでいない人が多いのだ。

家計の見直しで、「格安スマホ」への変更がしばしば話題となる。料金面ではかなり安くなるのだが、なかなか容易には変更できないようだ。その理由は行動経済学でいう「現状維持バイアス」のためだ。

サラリーマンの多くは、「われわれは、しょせんサラリーマンで決まった給料しかもらえないのだから、お金持ちになれるわけがない」と思っている。ところが、“億り人”の中には意外とサラリーマンが多いのだ。

一般的に、罰金やペナルティーは、社会において犯罪や違反行為が起きないようにするための“抑止効果”として使われる。しかし、そのやり方を間違えると、抑止どころか、逆に増えてしまうことにもなりかねない。

FXの本質を正しく理解した上で、収益を上げようというのであればいいが、よく分からないままに取引を始めようとする人が少なからずいる。FXはあくまで投機。注意が必要だ。

ソフトバンクとヤフーが大株主の「PayPay」が100億円キャンペーンを実施した。金額が大きくインパクトがあったため、あっという間に終了してしまったが、その背後には、ある思惑が隠されていた。

年末ジャンボ宝くじの発売期間がまもなく終了を迎える。少しの金額で大きな夢を買えるので、買っている読者も少なくないだろう。だが、行動経済学的に見れば、宝くじと保険はいくつもの共通点がある。

10月以降、株価が世界的に弱含みで推移しているが、少し潮目が変わってきたかもしれない。そうした下落相場が続くなら、「ドルコスト平均法」を使った投資は有効な投資方法となる。

投資信託のタイプとして「インデックスファンド」と「アクティブファンド」という分類があることはよく知られている。ところが、これらの違いを正確に理解している人は意外に少なく、勘違いをしていることも多い。
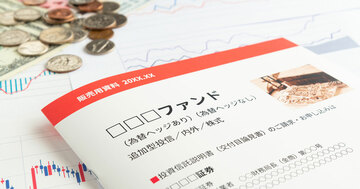
多くの企業において、日常業務とは別に、さまざまな社内プロジェクトを立ち上げることがある。しかし、放っておくと社内はプロジェクトだらけになってしまいがちだ。その理由を探るとともに、対策について見ていくことにする。

株式投資において、自分が買った値段を気にするあまり、買った後に下がってもなかなか損切りすることができず、損失を拡大させてしまうということはよくあること。なぜこういうことになってしまうのか、行動経済学の観点から考えた。

投資信託には「基準価額」という値段のようなものがある。しかし、通常のモノの値段とは大きく違うにもかかわらず、それを基準に購入するのは全くのナンセンスだ。

9月3日、安倍晋三首相は、働き方改革の第2弾として「生涯現役時代の雇用改革を断行したい」と発言した。シニア世代の働き方と年金という観点から考えると、今後の方向性を明らかに示唆している。と同時に、どうやら多くの誤解もあるようだ。

投資信託の中に「テーマ型」と言われるものがある。例えば「フィンテック」「社会貢献」「オリンピック」といったテーマを通じ、特定の業界や企業に投資をするというものだ。しかし、はやっているからといって買うべきではない。

株式投資をしていて、保有している株が下落したとき、多くの人は下がった価格でさらに買い増す「ナンピン買い」をしがちだ。だが多くの場合、失敗に終わることが多い。その理由について行動経済学の観点から考えてみる。
