沼澤典史
コロナでも右肩上がりのプロテイン市場。国内外の企業がシェアを拡大しようとしのぎを削っているが、日本における勢力図はいかなるものなのか。それぞれの特徴やプロテイン市場の展望を流通アナリストの渡辺広明氏に聞いた。

4月の発売から約1カ月で3万部を突破し、話題になっている『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ―コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)。本書では映画やドラマを早送りで見る倍速視聴の習慣にある背景を解明している。このような視聴者には、今後どんなコンテンツが受け入れられるのか。著者である稲田豊史氏に聞いた。

若い女性の間でヒットする商品には必ず「カワイイ」が含まれている。著書『カワイイエコノミー』(日経BP)でこう述べるのは、プリントシール機でヒット作を飛ばすフリュー株式会社「ガールズトレンド研究所」所長の稲垣涼子氏。そんな稲垣氏に「カワイイ」ヒット商品の開発方法や、流行の終わりの見極め方などについて聞いた。

自分でも違和感があるのに、会話でもメールでも多用してしまう「させていただく」。賛否両論あるこの言葉遣いだが、なぜこれほど使われているのか。「させていただく」増加の背景について、法政大学文学部教授の椎名美智氏に聞いた。

最近ではアニメ「鬼滅の刃」で遊廓を舞台にするシーズンに対し、「子どもに見せたくない」「説明できない」という親の意見も少なからずあったという。しかし、どんな歴史であれ、学び、語り継ぐのが大人の役目。そこで、江戸文化研究者である田中優子法政大学名誉教授・前総長に、遊廓の歴史や語り継ぎ方を聞いた。

歌舞伎町を中心に存在する「ぴえん系女子」は、10代~20代の女性の中ではファッションアイコンのような位置づけにある。日本のZ世代、もとい「ぴえん世代」の特徴やわれわれ大人に求められる彼女らとの接し方などを佐々木チワワ氏に聞いた。

ミドル世代になると管理職として、部下のマネジメントなどを行う場面に直面する。今回は、そんなリーダーシップに悩む人に向け、元エリート自衛官であり、『メンタルダウンで地獄を見た元エリート幹部自衛官が語る この世を生き抜く最強の技術』(ダイヤモンド社)を著したわび氏に、自衛隊流リーダー論を聞いた。

就職に強いとされる体育会系学生。学生はもちろん、企業の担当者にも「採用するなら体育会系」と考える人は多いかもしれない。しかし、雇用や働き方が激変する現代において“体育会系神話”はまだ機能するのか。

昨年から今年にかけて、英語学習新書が異例の売れ行きを示している。いずれも硬派な読み物であるが、なぜ今、英語学習新書が売れるのか。その理由を『英文法基礎10題ドリル』(駿台文庫)などの著者として知られる予備校講師の田中健一氏に聞いた。
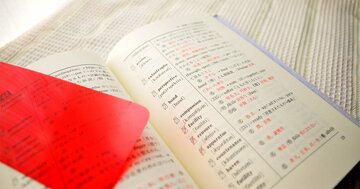
昨年は1月に『映画秘宝』の元編集長が一般の個人に向けてツイッターで恫喝(どうかつ)的な発言を含むダイレクトメール(DM)を送ったことが問題となった。また、小山田圭吾氏は過去のいじめ行為について語った雑誌記事が問題となり、東京オリンピック開会式の楽曲担当を辞任。小林賢太郎氏はホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)をコントのネタにしたことで開閉会式の演出担当を解任されるなど、かつてのサブカルシーンを牽引(けんいん)した2人が炎上の末、降板した。なぜ“サブカルおじさん”は炎上し、たたかれるのか。サブカルチャーに詳しいライターの稲田豊史氏に聞いた。

ミドル世代になると家庭や仕事などでの悩みが多くなるもの。しかし、年齢的に誰かに相談するハードルも高くなりがちだ。そこでツイッターとInstagramで絶大な人気を誇るメンタルケア情報発信サイト「ココロジー」の編集長まきしむ氏に、ミドル世代が抱えがちなメンタルの悩みや解決法について聞いた。

YouTubeを見ていれば多くの人が目にする広告。しかし、なかには真偽不明の効果をうたう商品や執拗(しつよう)に脱毛をせまる広告、陰謀論とおぼしき怪しいサイトの広告なども散見される。なぜプラットフォーム側はこのような不快かつ悪質な広告を取り締まれないのか。ITジャーナリストの三上洋氏に聞いた。

ウィズ・コロナによって会食や集団行動が規制される中、政治家による大人数での会食や会合などが相次いで報道されたことは記憶に新しい。また会社においてもおじさんたちは対面での打ち合わせや会議を熱望していることも多い。このように中高年になるほど集団行動かつ対面を重視したがる理由は何なのか。

部活動の問題点をさまざまなデータで示した『部活動の社会学』(岩波書店)が注目を集めている。同書を編集した、教育社会学者で名古屋大学准教授の内田良氏に、現代の部活の実態とあるべき姿を聞いた。

現在、幾つものベンチャー企業が参入している植物工場。効率よく野菜を生産できると注目されている一方、多くは赤字で採算が取れていない状況だという。そんな植物工場の存在意義や今後の展望を東京農業大学教授の小塩海平氏に聞いた。

『英語独習法』(岩波新書)が売れている。本書は認知科学の概念である「スキーマ」と呼ばれているものをカギに英語力向上を書いたもので、日本語と英語の認知的な違いを理解することに重点を置く。その独自メソッドを、著者であり慶應義塾大学環境情報学部教授の今井むつみ氏に聞いた。
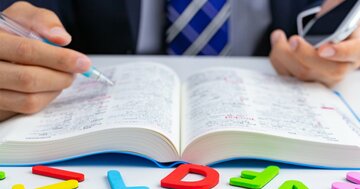
日本特有の現象として知られている同調圧力。『同調圧力の正体』(PHP新書)によると令和になりそれがタテ(秩序)ではなくヨコ(正義)から発生しているという。会社内でも同調圧力の空気に悩まされる人も多いと思うが、それにどう対処し、振る舞えばいいのか。著者であり同志社大学政策学部教授の太田肇氏に聞いた。

『妻のトリセツ』(講談社+α新書)を筆頭に「妻との接し方」「妻との溝を埋める方法」など、類似したテーマの本やネット記事が増えている。このような「妻関連コンテンツ」が話題になっている理由と、そこから見える現代の男性像、夫像を『ぼくたちの離婚』(角川新書)などの著書があるライターの稲田豊史氏に聞いた。

JR東日本の駅ナカ自販機を中心に展開する飲料総合ブランド「acure(アキュア)」。駅を利用する人の多くが一度は見かけたことがあるかもしれないが、その商品ラインアップには麻婆スープ、ふかひれスープといった異色の「スープ缶」が含まれている。なぜここまで攻めた「スープ缶」を販売するのか。

ここ数年、東京の高円寺周辺では山形料理をテーマにした飲食店が増えている。それらの多くは同じ系列店で、「株式会社どりーむずかむとぅるー」の運営によるもの。なぜ高円寺なのか。そして、地方の郷土料理をどのように東京で広めているのか。同社取締役副社長の高橋勇氏に聞いた。
