片田江康男
日本生命保険が2021年度~23年度の新中期経営計画を発表した。新型コロナや低金利、脱炭素など、営業面と運用面の両方で変化が激しい中で、今後3年をどう捉えているのかに注目が集まった。2時間を超える記者会見で清水博社長が語った内容を詳報する。

傘下のジェイコム少額短期保険を通じて2020年11月、保険業界に参入したケーブルテレビ国内最大手のジュピターテレコム(J:COM)。持ち家世帯を対象に、災害時の家財損壊や近隣トラブル対応の費用を一体的に補償する業界初の保険商品を発売する。ケーブルテレビ契約者の顧客基盤をベースに、一気に市場を席巻する戦略だ。

ライフネット生命が、家計簿アプリを開発するマネーフォワードと業務提携した。両社の目指すサービスは、いずれも既存の生保各社が一朝一夕に実現できるようなものではなく、国内大手生保が支配する市場に、風穴を開けるものとなるかもしれない。
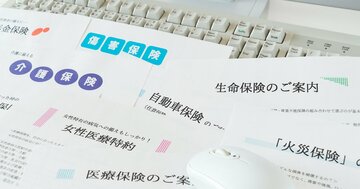
2月12日、第一生命保険は21年度役員人事と共に、元営業職員による金銭詐取事件の責任を明確にすべく、合計11人に及ぶ役員の懲戒処分と報酬減額を公表した。一連の不祥事にけじめをつけた形だが、この人事を深読みすると、いくつか疑問が浮かび上がってくる。

主要生命保険会社の第3四半期決算が発表された。2020年春の緊急事態宣言が解除されて以降、再開された営業活動の成績はどのように出たのか。3カ月ごとに数字を追うと、回復基調が鮮明になっているものの、それを吹き飛ばすような新たな要素も浮上している。

税理士・社労士・司法書士…企業が付き合うべき士業、手を切るべき士業の見分け方
企業にとって本当に役立つ士業はどう選べばいいのか。また士業をどう使えば自社の競争力向上につながるのか。『会社を救うプロ士業 会社を潰すダメ士業』の著者で、士業向け経営コンサルタントとして活躍する特定行政書士の横須賀輝尚氏に話を聞いた。

第一生命の元営業職員による金銭詐取事件が発覚してから4カ月。焦点となっていた被害者への弁済額について、2月4日に第一回調停が東京地方裁判所で開かれた。事件の現状を整理するとともに、営業現場に広がる影響をレポートする。

#10
四大会計事務所グループの一角、EYジャパングループに属するEY税理士法人には、企業から税務業務をそのままアウトソーシングするという話が舞い込み始めているという。蝦名和博統括代表社員に、ここ数年で顕著になってきた企業税務の新潮流について、話を聞いた。

#9
四大会計事務所グループの一つ、PwCジャパンに属するPwC税理士法人。四大系税理士法人の中でどのように差別化していくのか。税理士を取り巻く環境の変化をどう見ているのか。高島淳代表に話を聞いた。

#8
「弥生シリーズ」など、中小企業向けの会計ソフトウエアメーカー大手の弥生。クラウド型会計ソフトメーカーの台頭などをどう見ているのか。また、ユーザーであり事業パートナーでもある税理士業界は、どう変わっていくとみているのか。岡本浩一郎社長に話を聞いた。

#7
税理士業界にクラウドとRPAの大波が押し寄せている。この波にのまれるか、それとも乗りこなすかは、税理士にとって生死を分ける最も大きな要素だと言っていい。RPAを自社開発するなど業界最先端を行く税理士法人ベリーベストの業務改革をレポートするとともに、熾烈な競争を繰り広げるクラウド会計ソフト会社の思惑も解説する。

#6
税理士法人同士のM&Aが急増している。売り手は環境変化の波にのまれた「高齢税理士」や税務以外に注力したい税理士たち。その一方で、その状況をチャンスと捉えた30〜40代の税理士「第4世代」といわれる税理士が買い手として物色している。税理士M&A時代の最前線を追った。
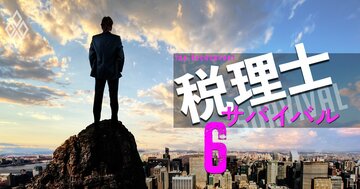
#5
顧問税理士の料金は、いまだに税理士の言い値で支払っているケースが多いといわれる。果たしてあなたの会社は、月額の顧問料に見合ったサービスを顧問税理士から受けているだろうか。企業規模別の顧問料金相場を提示するとともに、付き合うべき税理士の条件を探った。
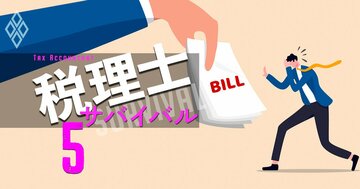
#4
大手税理士法人の一角を占める山田&パートナーズ。そのトップである三宅茂久統括代表社員は、税理士が生き残るには二つの柱を持つことが重要だと説く。同社創業者、山田淳一郎氏に早くから後継者に指名され、2008年からトップを務める三宅代表の持論を聞いた。

#3
一口に税理士と言っても千差万別。おのおのに得意とする業界や税法がある。もはや税理士の資格を持っていれば食っていける時代ではなく、税理士からすれば得意分野・業界を掲げ、自身のキャラクターを定める必要性に迫られているのだ。さまざまなタイプの税理士を図鑑形式で紹介し、税理士の生態を明らかにする。

#2
2001年の税理士法改正をきっかけに、業界内で最も早くから規模拡大にまい進し、業界最大手に上り詰めた辻・本郷税理士法人。だが最大手でさえ人材採用に苦労し、テクノロジーの進化に乗り遅れまいと環境変化にもがく現実がある。徳田孝司理事長に話を聞いた。
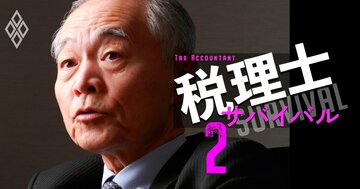
#1
顧問税理士は中小企業にとって最も身近な士業であり、“かかりつけ医”だ。昨年からのコロナ禍は、税理士のかかりつけ医としての力の差を浮き彫りにした。既にコロナ禍対応をきっかけに、顧問契約を切られる税理士も出始めている。
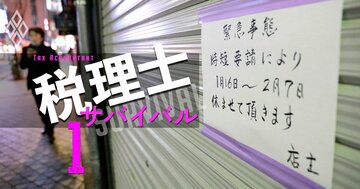
予告編
税理士サバイバル!コロナ・DX・人材難の3重苦が襲う「先生」の受難
税理士は複雑な税務をサポートしてくれる身近な「先生」だ。だが彼らは今、コロナ禍、デジタル化、人材難など環境変化の荒波にもまれながら、熾烈な生き残り競争に直面している。税理士業界の最前線をレポートするとともに、中小企業にとって付き合うべき税理士を選ぶヒントも提示する。

生命保険業界は、低金利による運用難に加え、コロナ禍に対応した営業体制の再構築といった課題に直面。さらに第一生命保険の元営業職員による金銭詐取事件で世間を騒がせている。これらの問題にどう対処するのか。「週刊ダイヤモンド」2020・2021年12月26日・1月2日新年合併特大号に掲載したインタビューの拡大版をお届けする。

#25
生命保険各社は、コロナによって以前のように顧客を訪問して営業することができなくなった。21年は新たな営業体制の確立に加え、第一生命の不祥事の影響でガバナンス強化も求められることになりそうだ。
