塙 花梨
#20
大学受験はその先のキャリアへ進むための過程でしかないが、大学合格をゴールに据えてしまい失敗するケースは少なくない。自らも東京大学卒で精神科医の和田秀樹氏は「東大生には2種類いる」と言う。社会で通用する東大生と、通用しない東大生だ。社会で通用しない東大生の共通項に通っていた予備校もあるという。

#19
東進ハイスクールの人気英語講師、安河内哲也氏はこの道35年の大ベテラン。長年にわたり第一線で活躍してきた安河内氏ならではの視点で、予備校業界の変遷や、今の子どもとその親に求められる勉強への取り組み方を、赤裸々に語ってもらった。さらに、大学入試だけでなく、社会人にも参考になる生きた英語勉強法も聞いた。

#17
子ども一人一人に合った指導、いわゆる“個別最適”を塾に求める傾向が年々強まっている。そのため、一対一で丁寧に教えてくれる個別指導は人気が高い。しかし、一口に個別指導塾と言っても、一度に授業を受ける生徒数や指導方法、時間など、特徴はバラバラだ。そこで、数多くある個別指導塾を運営形態で五つに分け、その実態を解説する。

#14
学校でも活用され中高生の勉強に定着している「スタディサプリ」や、幼児から小学生までの家庭学習を支える「スマイルゼミ」――。近年、スマホやタブレットを使ったICT学習教材の台頭が著しい。このほか、多くの大手塾で使われているAI教材「atama+」なども含め、コスパに優れる最新のICT学習教材を徹底比較する。今やこの手のアプリだけで東大や京大に合格する生徒が登場する時代なのだ。

#12
日本初の“授業をしない予備校“で知られる武田塾。武田塾の最大の特徴は、各教科で優れた市販の参考書を徹底分析して選出し、「東大ルート」「早慶ルート」など志望校別に、参考書を解く学習スケジュールを組むことだ。そこで、武田塾イチオシの英語・数学・国語3教科の最強参考書から、スケジュールの組み方と学習法まで紹介する。さらに、市販の参考書を活用した早稲田合格に向けた「学習年間スケジュール」も公開。
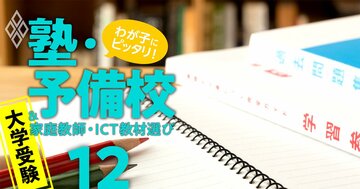
#11
中学受験塾、大学受験予備校、個別指導塾、通信教材、ICT教材など、塾・予備校業界にはあらゆるプレーヤーが存在する。そんな中、資本提携や買収で業界再編が進み、特に最近はICT教材やAI学習などの存在感も強まっている。合従連衡が続く業界全貌図と共に、各社の目下の注力事業も併せて掲載する。
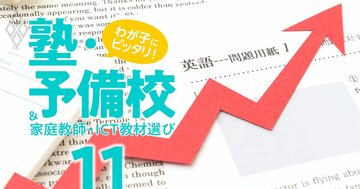
#10
昨年に発刊され話題となった『シングルマザーで息子2人を東大理Iに 頭がよくなる「ルーティン」子育て』の著者、たかせみほ氏に、省エネ&低コストな塾の活用術や子育て術を聞いた。

#9
子どもを中高一貫校に通わせても、付属校でない限り大学受験の前には塾・予備校に行くのが一般的。だが、私立中高一貫校と予備校のダブルワークは、親にとって金銭面での負担が大きい。その中で、中高一貫校の中には、通塾が不要なほどカリキュラムが充実している学校もある。「塾いらず」として知られる中高一貫校のノウハウを探った。また、学校選びの基準の一つではあるが比較しにくい中高一貫校206校の“校風”を一目でチェックできる「校風マトリクス」も掲載。

#3
大学受験塾・予備校が公表する合格実績には各校でさまざまなカウント方法がある。そこで、東京一工や早慶などの難関大に通う大学生280人にアンケートを行い、実際にどの塾・予備校が合格に役立ったのかを大調査した。【東大・京大編】【早慶編】【現役・浪人編】などに分けてランキングを掲載する

#21
偏差値が上の層からも下の層からも志願者を集める人気の私立大学群である“GMARCH”(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)を、五つの独自指標で徹底比較!人気、知名度、ブランド、歴史、どれを取っても優劣をつけるのが難しいこの6大学の最新序列は?
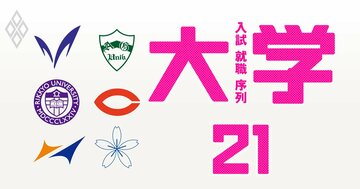
#19
理系を選択する受験生にとって、一番重要なのは「大学選び」ではなく「学科選び」だ。なぜなら同じ大学でも、どんな分野を学ぶかによって、大学院進学率や就職活動の状況、主な就職先がまったく異なるからである。主要11大学の専攻分野別の進路データを紹介していく。

#10
今、海外大学進学に注目が集まっているが、留学エージェントのプランのままに、海外大学に進学すると危険だ。米国をはじめとする海外大学には複数の種類があり、それによって、大学のレベルも方針も難易度も大きく変わるからだ。誤った大学選定をすると、留学費用だけが多額にかかり、英語力もスキルも身に付かないまま数年を過ごすことになる。一方で、海外大学の入学審査をひもとくと、国内の難関大学に行けない学力であっても入学チャンスがあることも分かる。

#9
偏差値が低くて入りやすいのに、有名企業への就職率が高い「本当に就職におトクな大学」はどこなのか?全国の大学で、有名企業400社への就職率が10%を超える101大学を対象に、就職率帯別で、偏差値の低い順にランキングを作成した。ランキングを読み解くと、女子大や工業大などの上位ランクインが目立つ結果となった。
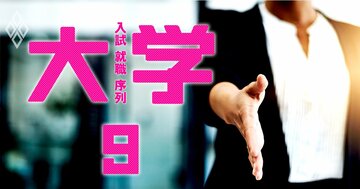
#8
コロナ禍によりますます人気を集める理系大学。そこで、理系学部のある主要62大学を対象に「大学院進学率」「偏差値」「有名企業400社への就職率」の3軸のデータで、理系大学の真の実力を読み解く。また、偏差値帯別の理系学部大学院進学ランキングも掲載。

#4
昭和女子大学は難易度では中堅ながら、年間卒業生数が1000人以上の女子大の中で、10年連続で実就職率トップを誇る。また、同大の大きな特徴が「ダブルディグリー・プログラム」という、日本と海外大学の2つの学位を5年間で取得できる超お得な制度。著書『女性の品格』(PHP新書)でも知られる昭和女子大学の坂東眞理子理事長に話を聞いた。

#2
偏差値で見て比較的入りやすい大学でも、就職率が高い大学が存在する。そうした大学の特徴は、就職支援が手厚いことだ。コロナ禍でも臨機応変に対応し、万全の体制できめ細かく学生をサポートする様子を、各大学への取材によりお伝えしていく。

#5
コロナ禍の影響で、民事裁判の多くがオンライン裁判になった。さらに、労働事件のカジュアル化が進んでおり、その背景には大手新興系法律事務所がつくってきた新しい弁護士業界のトレンドがあった。そこで、労働法務専門の向井蘭弁護士への取材を基に、労働事件がカジュアル化している背景や実態に迫った。

#4
会社を倒産危機に追い込む、驚異の未払い残業代請求。しかし、向井蘭弁護士の提唱する「完全歩合制」を導入すれば、窮地を乗り越えることができるという。『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)の著者である向井氏への取材を基に、完全歩合制の導入方法6ステップ、経営者・労働者双方のメリットについて解説する。
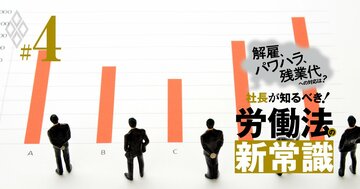
#2
昨年4月の民法改正により、「賃金請求権の消滅時効」が2年から5年(当面は3年)に延びた。これにより、今から2年後今から2年後の2023年4月以降、労働者から過去3年分の残業代を一気に請求される可能性があり、中小企業であれば倒産の危機、大企業であっても大打撃となる。一体どんな会社が窮地に陥るのか。『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)の著者である向井蘭弁護士への取材を基に、具体的なシミュレーションと、関係する重要判例を紹介していく。

#1
テレワークが進み、働かない“ぶら下がり社員”や、注意に応じない“モンスター社員”の存在が目立つようになったが、SNSでの炎上リスクもあるので、会社側も強く出るのは難しいのが現状。そんな中、会社側がリスクを負わずに対策できる意外な方法があった。『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)の著者であり、労働法務専門の向井蘭弁護士の話を基に解説する。
