塙 花梨
#6
リモートワークにより個々の仕事の効率が上がったため、会社やチームの生産性が向上するケースも見られる。だが、その裏で、以前とは違う環境下で不満やストレスを抱え、離職を考える社員も出てきている。一緒に働く者同士が、毎日顔を合わせない時代の理想のマネジメントの形とは?

#3
日本企業に定着した目標管理は、半期に1度しか確認しない“ほったらかしMBO”になる傾向があった。さらに、コロナ禍でリモートワークが進み、ただでさえあいまいだった目標設定や人事評価が、より不明瞭になる事態へ。そこで、会えない時代でも部下の成果を引き出す「新・目標設定の裏ワザ」を紹介していく。
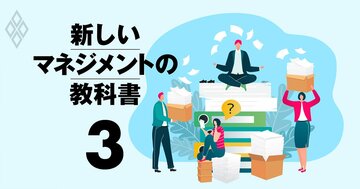
#2
コロナ禍が最後の一押しとなり、年功序列制度の崩壊に拍車が掛かった。日本の大手企業が一気に、仕事に人を配置する「ジョブ型」雇用を本格的に導入し始めたのだ。もし日本でジョブ型が定着すれば、これまでの出世の常識は180度変わる。今年度よりジョブ型を導入した富士通の最新事例も交えて、日本独自のジョブ型のメカニズムを徹底解説する。

#51
新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、家族は最期をみとることもできない――。このように、大きな災害が降りかかるたび、人々の死生観は変化してきた。宗教の垣根を越えて活躍する僧侶の松山大耕氏に、仏教から考える “死”との寄り添い方を聞いた。
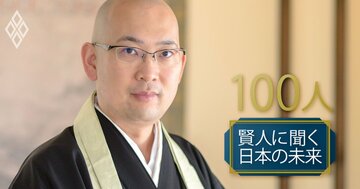
#18
知識経営の祖として知られる、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏。野中氏が提唱する組織的な知識創造の枠組み「SECIモデル」では、徹底的な対話で共感することが、知を生むとしている。コロナ禍により直接会うことが難しくなった今、SECIモデルを進める方法を取材した。
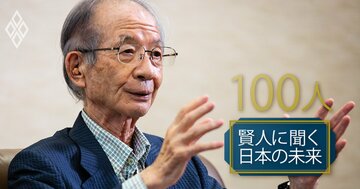
#3
2005年から続く人気番組「ゴッドタン」をはじめ、数々のバラエティー番組を手掛け、会社員ながら「オールナイトニッポン0」でラジオパーソナリティーまでこなす気鋭のテレビプロデューサー、佐久間宣行氏。コロナ禍により物理的にも心理的にも常識が一変したテレビ業界で、これから求められるコンテンツとは一体どんなものなのか。
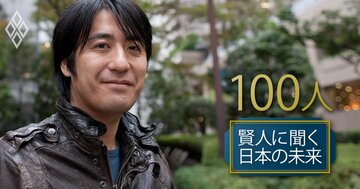
【ロジカルチェック術その3】
部下の相談に対し「全部やってみろ」「とにかく頑張れ」と根性論で返してしまう――。ダメ上司のあるあるだ。こうした事態を防ぐために、効果のある問題解決法を解説。論理思考を使って、本質的な原因を明らかにしていくことが大事。そのために使えるMECEも紹介する。

【ロジカルチェック術その2】
自宅で仕事をする機会が増え、会議やプレゼンテーションもやりにくくなった人も多いだろう。特集『3日で絶対!習得シリーズ』「ロジカルチェック術」(全3回)2日目は、そんなときに有効な資料作成術を公開。ワンスライド・ワンメッセージの法則や、水掛け論を防ぐための定量データの使い方など、紹介していく。

【ロジカルチェック術その1】
部下のプレゼンや報告に対して、的確にフィードバックできる上司になるには――。論理的思考法をうまく使うべし!仕事で起こりがちな結論の飛躍を防ぐ思考法とは?演繹法と帰納法の違いから、ピラミッドストラクチャーの作り方までを解説していく。

累計マッチ数430億を誇る世界最大級マッチングアプリ「Tinder(ティンダー)」。サービスの提供を開始した2012年、“出会い系”の世界に新しい風を吹き込んだ彼らは、18~25歳のZ世代をターゲットにしている。新型コロナウイルスの影響で人と人とが出会う方法も大きく変わりつつあるが、TinderのCEOエリー・セイドマン氏は“Z世代の恋愛の在り方”をどう予測するのか。単独インタビューを実施した。

#5
「自分でおいしいコーヒーを淹れてみたい」と思い立っても、専用の器具や淹れ方の情報が溢れていて何から始めればよいか、悩みどころだ。そこで、アジア人初のワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典氏に、簡単においしいコーヒーを淹れるコツを聞いた。
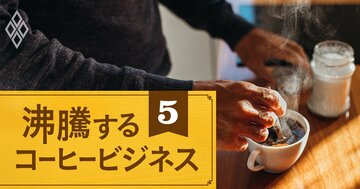
#11
自粛期間が明け、ようやく演劇公演が再開し始めた矢先、新宿の劇場で大規模なクラスターが発生。コロナ禍で活動しようとしている演劇人たちは、感染対策の難しさや金銭面でも赤字覚悟になってしまう事態に直面し、苦渋の決断に迫られている。さらに、そもそもの劇団の収支構造に目を向けると非効率な慣習が根付いていたことが分かった。そこで今回、コロナ禍における演劇業界の悲痛な現状と実態を取材した。

#10
「GO」(2001年)や「世界の中心で、愛をさけぶ」(04年)などで知られる映画監督の行定勲氏。又吉直樹氏が書いた恋愛小説を実写映画化した「劇場」が全国のスクリーンで大規模に公開される直前、緊急事態宣言により延期を余儀なくされた。しかし、この前代未聞の状況下で、リモート映画の制作や劇場公開と同時にインターネットでも配信するなど、新しいことに挑戦し続ける行定氏。その目に映る、コロナで変わる“映画の未来”とは。

#4
コロナによる巣ごもりで生活習慣が乱れている人が多い中、うまく摂取すればコーヒーは薬のような効果をもたらす。医学や薬学の専門家による監修の下、身体にも心にも効く飲み方を紹介する。

#3
あなたの手元に一杯のコーヒーが届くまで、川上から川下へ向かう間にあらゆるプレーヤーがひしめき合っている。そのコーヒーの商流を完全図解する。また、大きく三つの波に分けられる日本のコーヒー近代史を年表で振り返っていく。

#2
実は、「コーヒー」という大きなエコシステムの中で割を食っているのは生産者だ。なにしろ、コーヒーの小売市場が450億ドルもの規模になっている一方で、生産者はわずかな利益しか得ていないからだ。生産者が困窮する構図を解説する。

#4
新型コロナウイルス感染拡大のため営業休止となっていた映画館が6月より再開。徐々に活気が戻りつつあるものの、感染対策のため、座席を平常時の50%に間引きしている。そもそも近年の映画業界を振り返ってみると、原作が人気の作品やアニメシリーズなど、いわゆる大作に資金が集中する状態が長らく続いていた。このコロナ禍で新しい映画の可能性は生まれるのだろうか。

#1
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、コーヒービジネスに異変が起こっている。全体の消費が微減する可能性がある中、家で楽しむコーヒーの需要が激増。コーヒー市場の新しい明暗が浮かび上がった。

予告編
コーヒービジネス沸騰!コロナ巣ごもり消費の争奪戦が始まった
新型コロナウイルスの感染拡大により、喫茶店やカフェは数カ月間の営業自粛に追い込まれた。ところが、これにより、横ばいに推移していたコーヒー市場に思わぬ需要が発生、業界構造を変える可能性すらある。そこで、川上から川下に至るコーヒーの商流や、健康的な飲み方などを特集する。

コロナ疲れを癒す救世主?入荷3カ月待ちの「愛され」家族型ロボット
新型コロナウイルスの感染拡大とともに“自粛疲れ”が目立ち始めた今、求めてしまうのが「癒やし」だ。そんな中、犬や猫に続く癒やしの存在として注目され始めているのが、家族型ロボット「LOVOT(ラボット)」。 発売後、入荷1カ月待ちの状態が続くこのロボットには、どのような“愛されるカラクリ”があるのか。開発元であるGROOVE X代表の林要氏に話を聞いた。
