井出豪彦
2月9日、千葉県の医療法人の理事長から3000万円を脅し取ったとして、恐喝容疑で右翼団体の会長(50)と会社役員のM(51)の両容疑者が警視庁公安部に逮捕された。県内で複数の大規模病院を経営する医療法人で、一体、何が起きているのか、事件の背景について詳しく解説する。

エレベーター大手のフジテックは2月24日、同社大株主の投資ファンド「Oasis Japan Strategic Fund」の請求に基づく臨時株主総会を開催する。投資ファンド側は株主提案として、フジテックの社外取締役全員の解任や、自社が推薦する新たな社外取締役の選任などの議案を提出しており、一方、フジテックは株主提案すべてに反対を表明し、会社提案として追加の社外取締役2人の選任を求めるなど、全面対決の姿勢だ。こうした中、株主提案で社外取締役候補の筆頭に推薦されている人物に看過できない疑惑が浮上し、情勢は混とんとしつつある。

「無電柱化」(電線地中化)で活躍する製品などを製造する産業資材メーカーのカナフレックスコーポレーションが12月1日付で取引先に送付した2通の文書が、関係者の間で話題となっている。社会人野球の強豪チームでも知られる同社で何が起きているのか。
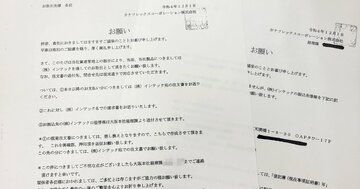
ペルー元大統領の妻が経営する都内ホテルの不動産売買を巡り、トラブルが起きていることが判明した。今後、同妻らが刑事告訴される可能性も高い。

楽天グループ傘下の楽天モバイル(東京都世田谷区)の基地局設置に関して、元社員と協力業者が結託した大掛かりな横領疑惑が取り沙汰されているが、不正に関与していたとされる物流会社の「TRAIL」(東京都港区)は、失敗に終わったあの「楽天エクスプレス」事業の幹線輸送を担っていた取引先だったことが分かった。このほど当時の楽天の社内資料を入手した。
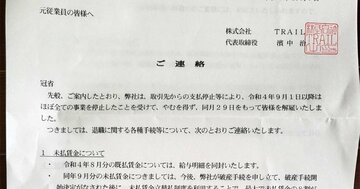
宝飾事業を手掛ける「ナガホリ」の株価が今年に入って急騰している。背景にあるのが、複数の新たな大株主の登場だ。だが、一部の市場関係者からは、株主間で連携した買い占めではないかとの声も上がっており、今後の動きが注目される。
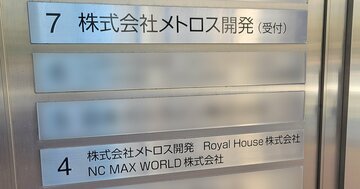
カキや魚介料理の専門店を展開する東証グロース上場のゼネラル・オイスターで今春、筆頭株主との対立が明らかになった。今年3月期まで7期連続の営業赤字と業績が苦戦する中、筆頭株主から大胆な株主提案を受け、6月末の株主総会前に一悶着(ひともんちゃく)あったが、さらに当日も株主から緊急動議が提案されるなど、ちょっとした見ものとなった。

今年4月、警察庁は新組織「サイバー警察局」を発足させ、傘下の実動部隊「サイバー特別捜査隊」も設置した。サイバー犯罪は2021年に初めて摘発件数が1万件を超えるなど深刻化しており、組織改編で対応に本腰を入れる。筆者は、これまでわが国で摘発されてこなかった「アドフラウド」と呼ばれる新手のサイバー犯罪の立件第1号がどのタイミングで出るのか注目している。

日本最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営などを行う上場ネット企業のオウケイウェイヴを巻き込んだ、巨額の投資詐欺事件が表面化した。被害額は100億円を超える可能性が高い。その詐欺スキームの全容を明らかにする。

建設・住宅業界がにわかにさわがしい。ゼネコンは相次ぎアクティビストファンドのターゲットとなり、市場原理という外圧の結果、一気に再編が進み始めた。また、一部の大手ハウスビルダーはロシアのウクライナ侵攻による影響の直撃を受けている。建設資材の高騰に見舞われ、業績の先行きにも暗雲が垂れ込めてきた。

自動車部品大手のマレリが私的整理の一種である「事業再生ADR手続き」を申請したのは3月1日だったが、実はその前日の2月28日、都内に本社を置く調剤薬局大手も事業再生ADR手続きを申し立てていたことが分かった。3月24日に第1回の債権者会議が行われる予定だ。

M&A(合併・買収)仲介最大手の日本M&Aセンターホールディングスが、中核事業会社である日本M&Aセンターで成約前の仲介業務の契約書の写しを偽造するなどして売り上げを前倒し計上する不正が過去5年で83件あったと発表した。なぜ、このような不正が長らく放置されてきたのか。

東証1部上場企業で、機械メーカーやソフトウエア開発会社などに向けて、各種操作マニュアルや運用マニュアルなどの作成支援を行うグレイステクノロジーで、とんだ粉飾決算が発覚し、上場廃止の危機に追い込まれている。その内幕を明らかにする。
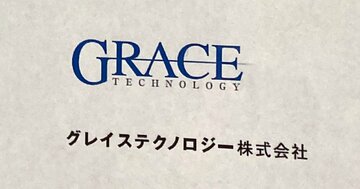
企業の倒産確率に応じた格付などを提供する、リスクモンスター(東証2部)の株価下落が止まらない。業績は右肩上がりで財務体質も健全にもかかわらず、株価が振るわない背景には何があるのか。

楽天グループが多額の予算を投じて構築してきた自前の配送網「楽天エクスプレス」事業を5月末で唐突に打ち切る決定を下した。同事業を巡っては、下請けの軽貨物運送業者との間でトラブルが起きていることや、楽天の元執行役員によるキックバックの疑惑もささやかれている。今回筆者はこれまで口を閉ざしてきた同事業元幹部の貴重な証言を得ることができた。関係者らへの取材により、事業打ち切りの裏側で一体何が起きていたのかを明らかにする。

日本テレビホールディングス傘下の太陽光発電事業会社が、倒産から1年3カ月後に突如「復活」を遂げ、事業を再開したことが判明した。異例の経営判断の狙いは何か。

政府の成長戦略会議は9月2日、今秋にとりまとめる予定の成長戦略の検討課題案を公表した。その一つが、金融機関同士の協議で債務を軽減する「私的整理」を円滑化する法整備だ。このような案が浮上した背景と、実現のための課題とは。

今年7月の全国企業倒産件数(負債1000万円以上)が、7月としては半世紀ぶりの低水準となった。新型コロナによる未曽有の危機にもかかわらず、倒産が激減する理由は何か。

パチンコやパチスロなどの遊技機器のキャビネット(木枠)などを製造していた「薮塚木材工業」(群馬県伊勢崎市、年商15億円、以下薮塚)とその親会社で木材加工を行っていた「K.テクニカ」(群馬県玉村町、年商7億円)は6月14日、東京地裁へ破産手続き開始を申し立て、同日開始決定を受けた。負債は薮塚が23億円、K.テクニカが7億円で、単純合算で30億円に達する。倒産が減っている昨今では珍しい部類の大型倒産となった。2社はなぜ倒産したのか。

このところ「ソーシャルレンディング」に関連した話題が続いている。ソーシャルレンディングとは、個人投資家に対し、ネット上で特定の資金使途を明示してファンドへの出資を募り、それを企業などに貸す仕組みだ。投資家に約束する利回りは年10%近くなることがある。債務者から担保を取る場合が多いが、元本保証はなく、投資家にとってはミドルリスク・ミドルリターンの金融商品といえる。
