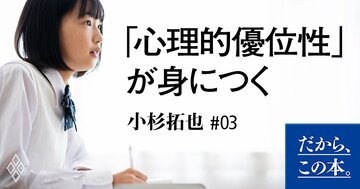ダイヤモンド社書籍編集局
【コンサルが教える】頭のいい人が「勝手に育つ」職場の“たった1つ”の特徴
「環境が人を成長させる」とよく言いますが、「頭のいい人」が育つ職場と、「社員の才能を潰してしまう職場」の違いとは、いったい何でしょうか。今回は、そんな疑問を、元デロイトのコンサルタント・安達裕哉さんにぶつける特別インタビューを実施。だれでも「頭のいい人」になれる方法を記した安達さんの著書『頭のいい人が話す前に考えていること』は、「コミュニケーションに関してはこれ一冊でいい」「もっと早く出会いたかった」と、多くのビジネスパーソンから絶賛の声が相次いでいます。今回は『頭のいい人が話す前に考えていること』の20万部突破を記念して、多くのビジネスパーソンの悩みの種である「新人の育て方」について、安達さんに教えていただこうと思います!安達さん、新人が勝手に育つ職場の特徴を1つ挙げるとしたら、なんですか……?(取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)
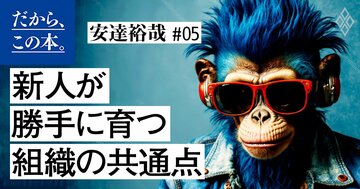
【メールの書き方で分かる】「考えている人」と「思考停止している人」の決定的な違い
誰よりも多く営業メールを送っているのに、なかなか受注に繋がらない。クライアントの返信率が悪い。一方で、すぐに新しい案件を獲得し、どんどん売上を立てる人もいます。「頭のいい人」は、いったいどんなふうにメールを送っているのでしょう。「読み終わった後、この本に出会ってなかった人生を想像するとゾッとする」と話題沸騰中の書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者である安達裕哉さんは、「頭のいい人」と「そうでない人」のメールには決定的な違いがあるといいます。今回は、コンサルで得た知見を凝縮し、だれでも「頭のいい人」になれる方法を記した一冊『頭のいい人が話す前に考えていること』の20万部突破を記念して、安達さんに特別インタビューを実施。返信率の高いメールと、低いメールの決定的な差はいったい何でしょうか。安達さんに、くわしく教えていただこうと思います!(取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)
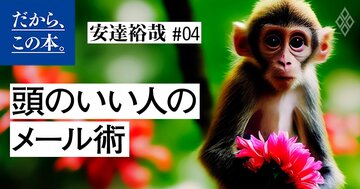
【コンサルが教える】「指示がコロコロ変わる上司」に振り回されない方法・ベスト1
「それくらい自分で考えて!」と言われたかと思えば、今度は「なんでもっと早く相談しなかったんだ!」と怒られる。どっちが正解なの? と、矛盾した上司の指示に、困惑する人も多いと思います。そこで今回は、こういった「上司とのすれ違い問題」をどう解消するべきか、元デロイトのコンサルタント・安達裕哉さんに書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』の20万部突破を記念して特別インタビューを実施します。「“軽い自己啓発本”と思って手に取った自分を反省するほど、濃い内容」などと話題沸騰中の書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』は、コンサル22年の知見を凝縮し、だれでも「頭のいい人」になれる方法を記した一冊。「指示内容がコロコロ変わる上司」には、どう対処すればいいのでしょう。安達さんに、くわしく教えていただこうと思います!(取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)
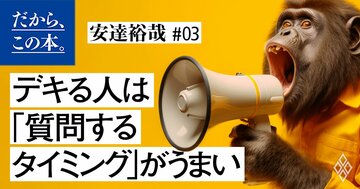
【コンサルが明かす】職場にいる「部下を潰す上司」「部下を活かす上司」の決定的な差とは?
新年度で配置換えがあり、管理職として仕事をしなくてはならなくなった……。マネジメント経験がなく、どうすれば部下に動いてもらえるのかわからない。自分の頭で考えて行動してほしい……。そう悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、こういった新米上司がぶつかる壁をどう乗り越えるべきか、「ブッ刺さりすぎて声出た!」「今年一位かも」と話題沸騰中の著書『頭のいい人が話す前に考えていること』の20万部突破を記念して元デロイトのコンサルタント・安達裕哉さんに特別インタビューを実施します。右も左もわからない管理職1年目を乗り切るコツを、安達さんに、くわしく教えていただこうと思います!(取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)
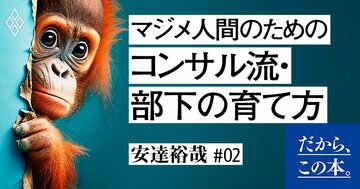
【コンサルが教える】仕事を任されたとき、二流は「納期の確認」をする。では、一流は?
入社1年目に身につけた習慣や、上司に教わった仕事のやり方は、その後の働き方、しいては人生に大きな影響を及ぼします。コンサルの知見を凝縮し「今年1位かも」「刺さりすぎて、声出た」と話題沸騰中の書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者である安達裕哉さんは、新人コンサルタント時代に、尊敬する先輩から教わった「仕事を任されたらやるべき8箇条」が、22年経ったいまでも仕事の基盤になっているそうです。今回は、だれでも「頭のいい人」になれる方法を記した一冊『頭のいい人が話す前に考えていること』の20万部突破を記念して、安達さんに特別インタビューを実施します。上司に怒られることばかりで、精神的にまいってしまうことも多い入社1年目。どんな対策をすればいいのでしょう。安達さんに、くわしく教えていただこうと思います!(取材・構成/川代紗生、撮影/疋田千里)
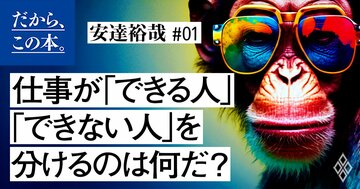
リモートでも「一体感」が失われないチームは、何をやっているのか?
「業績はいいのになぜか優秀な社員から辞めていく……」「リモートワークが増えて組織の一体感がなくなった……」「新しい価値を提供する新規事業が社内から生まれない……」「せっかくビジョンやミッションを作ったのに機能していない……」こうした悩みを抱える経営者たちからの相談を受けているのは、新刊『理念経営2.0』を上梓した佐宗邦威さんだ。本書には、人・組織の存在意義を再定義する方法論がぎっしり詰めこまれている。企業は「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」にシフトしなければ生き残れない。そこに「意義」を感じられなければ、企業からはヒト・モノ・カネがどんどん離れていくからだ。そこで今回、企業理念の策定・実装に向けたプロジェクトを数多く担当してきた佐宗さんにインタビューを実施。「チームの一体感の生み出し方」について聞いた(取材・構成/樺山美香、撮影/疋田千里)。
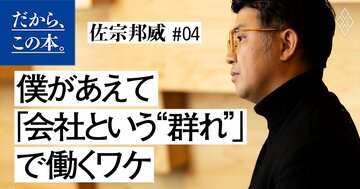
優秀な若手が「集まる会社」と「去る会社」。決定的な違いとは?
「業績はいいのになぜか優秀な社員から辞めていく……」「リモートワークが増えて組織の一体感がなくなった……」「新しい価値を提供する新規事業が社内から生まれない……」「せっかくビジョンやミッションを作ったのに機能していない……」こうした悩みを抱える経営者たちからの相談を受けているのは、新刊『理念経営2.0』を上梓した佐宗邦威さんだ。本書には、人・組織の存在意義を再定義する方法論がぎっしり詰めこまれている。企業は「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」にシフトしなければ生き残れない。そこに「意義」を感じられなければ、企業からはヒト・モノ・カネがどんどん離れていくからだ。そこで今回、企業理念の策定・実装に向けたプロジェクトを数多く担当してきた佐宗さんにインタビューを実施。「優秀な若手が集まる企業とそうでない企業との違い」について聞いた(取材・構成/樺山美香、撮影/疋田千里)。
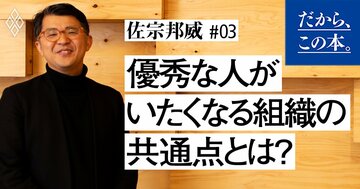
「わかりません」と言えるリーダーに人がついてくるワケ
「業績はいいのになぜか優秀な社員から辞めていく……」「リモートワークが増えて組織の一体感がなくなった……」「新しい価値を提供する新規事業が社内から生まれない……」「せっかくビジョンやミッションを作ったのに機能していない……」こうした悩みを抱える経営者たちからの相談を受けているのは、新刊『理念経営2.0』を上梓した佐宗邦威さんだ。本書には、人・組織の存在意義を再定義する方法論がぎっしり詰めこまれている。企業は「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」にシフトしなければ生き残れない。そこに「意義」を感じられなければ、企業からはヒト・モノ・カネがどんどん離れていくからだ。そこで今回、企業理念の策定・実装に向けたプロジェクトを数多く担当してきた佐宗さんにインタビューを実施。「これからの時代の企業リーダーに求められること」について聞いた(取材・構成/樺山美香、撮影/疋田千里)。
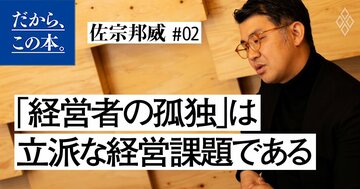
「企業理念が機能していない会社」から人が去っていく理由
「業績はいいのになぜか優秀な社員から辞めていく……」「リモートワークが増えて組織の一体感がなくなった……」「新しい価値を提供する新規事業が社内から生まれない……」「せっかくビジョンやミッションを作ったのに機能していない……」こうした悩みを抱える経営者たちからの相談を受けているのは、新刊『理念経営2.0』を上梓した佐宗邦威さんだ。本書には、人・組織の存在意義を再定義する方法論がぎっしり詰めこまれている。企業は「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」にシフトしなければ生き残れない。そこに「意義」を感じられなければ、企業からはヒト・モノ・カネがどんどん離れていくからだ。そこで今回、企業理念の策定・実装に向けたプロジェクトを数多く担当してきた佐宗さんにインタビューを実施。「これから生き残る企業の条件」について聞いた(取材・構成/樺山美香、撮影/疋田千里)。
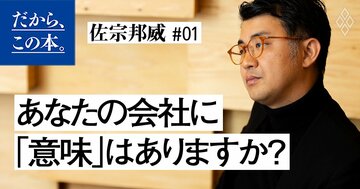
【元国税専門官が明かす】お金持ちほど「諦めが悪い」納得の理由
収入はたいして増えないのに、物価や税金が上がり支出ばかりが増えていく……無駄遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない。「老後のお金は大丈夫なんだろうか」と不安になっている人も多いのでは? そんな人が参考にしたいのが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)だ。本書は、東京国税局の元国税専門官・小林義崇氏が、相続税調査を通じて得た「“トップ3.5%の富裕層”が密かにやっていること」を体系化したもの。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、全体のたった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない“億万長者のリアル”に触れてきた小林氏は、「富裕層ほど倹約家。無駄金を使わないからこそ富裕層になれた」という事実に気づいたという。富裕層の実態を知る小林氏に特別インタビューを実施。全5回の最終回は、「お金持ちになりたいなら今すぐやめた方がいいこと」について聞いた。
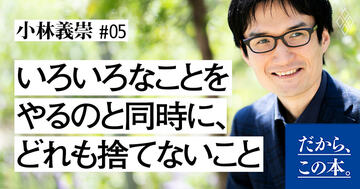
【元国税専門官が明かす】お金持ちになりたいなら今すぐやめた方がいいこと・ベスト1
収入はたいして増えないのに、物価や税金が上がり支出ばかりが増えていく……無駄遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない。「老後のお金は大丈夫なんだろうか」と不安になっている人も多いのでは? そんな人が参考にしたいのが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)だ。本書は、東京国税局の元国税専門官・小林義崇氏が、相続税調査を通じて得た「“トップ3.5%の富裕層”が密かにやっていること」を体系化したもの。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、全体のたった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない“億万長者のリアル”に触れてきた小林氏は、「富裕層ほど倹約家。無駄金を使わないからこそ富裕層になれた」という事実に気づいたという。富裕層の実態を知る小林氏に特別インタビューを実施。全5回の第4回目は、「お金持ちになりたいなら今すぐやめた方がいいこと」について聞いた。
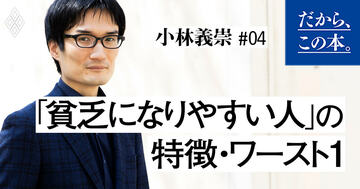
【元国税専門官が明かす】億万長者が身につける“意外な服”
収入はたいして増えないのに、物価や税金が上がり支出ばかりが増えていく……無駄遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない。「老後のお金は大丈夫なんだろうか」と不安になっている人も多いのでは? そんな人が参考にしたいのが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)だ。本書は、東京国税局の元国税専門官・小林義崇氏が、相続税調査を通じて得た「“トップ3.5%の富裕層”が密かにやっていること」を体系化したもの。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、全体のたった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない“億万長者のリアル”に触れてきた小林氏は、「富裕層ほど倹約家。無駄金を使わないからこそ富裕層になれた」という事実に気づいたという。富裕層の実態を知る小林氏に特別インタビューを実施。全5回の第3回目は、「億万長者はどうやってお金を貯めるのか?」について聞いた。

【元国税専門官が明かす】安定した国家公務員の年収を捨てフリーランスに転身した決定的理由
収入はたいして増えないのに、物価や税金が上がり支出ばかりが増えていく……無駄遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない。「老後のお金は大丈夫なんだろうか」と不安になっている人も多いのでは? そんな人が参考にしたいのが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)だ。本書は、東京国税局の元国税専門官・小林義崇氏が、相続税調査を通じて得た「“トップ3.5%の富裕層”が密かにやっていること」を体系化したもの。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、全体のたった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない“億万長者のリアル”に触れてきた小林氏は、「富裕層ほど倹約家。無駄金を使わないからこそ富裕層になれた」という事実に気づいたという。富裕層の実態を知る小林氏に特別インタビューを実施。全5回の第2回目は、「富裕層の働き方」について聞いた。
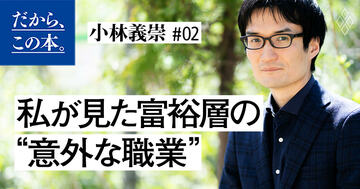
「ちょっとした言い方」だけで、損する人と得する人の差とは?
仕事ができて優秀でも、「人から好かれる人」と「人が離れていく人」がいる。同じような成果を上げていても、「順調にキャリアアップできる人」と「行き詰まる人」がいる。その違いはズバリ「気づかいの差」だ。よく気がつくのに「迷惑だったらどうしよう」「おせっかいかもしれない」と、気づかないフリをしてしまう繊細な人や内向的な人でも、無理せず「気が利く信用される人」に変われる。そう話す川原礼子さんに、「気づかいができず信用を得られない人にありがちな失敗」について聞いた。
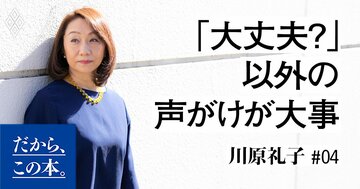
新入社員の「会社辞めます」を防ぐ、たった1つの方法
仕事ができて優秀でも、「人から好かれる人」と「人が離れていく人」がいる。同じような成果を上げていても、「順調にキャリアアップできる人」と「行き詰まる人」がいる。その違いはズバリ「気づかいの差」だ。よく気がつくのに「迷惑だったらどうしよう」「おせっかいかもしれない」と、気づかないフリをしてしまう繊細な人や内向的な人でも、無理せず「気が利く信用される人」に変われる。そう話す川原礼子さんに、「気づかいができず信用を得られない人にありがちな失敗」について聞いた。

部下への適切な声がけができない「ざんねんなリーダー」の共通点
仕事ができて優秀でも、「人から好かれる人」と「人が離れていく人」がいる。同じような成果を上げていても、「順調にキャリアアップできる人」と「行き詰まる人」がいる。その違いはズバリ「気づかいの差」だ。よく気がつくのに「迷惑だったらどうしよう」「おせっかいかもしれない」と、気づかないフリをしてしまう繊細な人や内向的な人でも、無理せず「気が利く信用される人」に変われる。そう話す川原礼子さんに、「気づかいができず信用を得られない人にありがちな失敗」について聞いた。

「気づかいの差」が「成果の差」につながる決定的な理由
仕事ができて優秀でも、「人から好かれる人」と「人が離れていく人」がいる。同じような成果を上げていても、「順調にキャリアアップできる人」と「行き詰まる人」がいる。その違いはズバリ「気づかいの差」だ。よく気がつくのに「迷惑だったらどうしよう」「おせっかいかもしれない」と、気づかないフリをしてしまう繊細な人や内向的な人でも、無理せず「気が利く信用される人」に変われる。そう話す川原礼子さんに、「気づかいができず信用を得られない人にありがちな失敗」について聞いた。

【元国税専門官が明かす】実家がお金持ちじゃないのに「富裕層になれる人」2つの共通点
収入はたいして増えないのに、物価や税金が上がり支出ばかりが増えていく……無駄遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない。「老後のお金は大丈夫なんだろうか」と不安になっている人も多いのでは? そんな人が参考にしたいのが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)だ。本書は、東京国税局の元国税専門官・小林義崇氏が、相続税調査を通じて得た「“トップ3.5%の富裕層”が密かにやっていること」を体系化したもの。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、全体のたった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない“億万長者のリアル”に触れてきた小林氏は、「富裕層ほど倹約家。無駄金を使わないからこそ富裕層になれた」という事実に気づいたという。富裕層の実態を知る小林氏に特別インタビューを実施。全5回の第1回目は、「実家がお金持ちじゃなくても富裕層になれる人の特徴」について聞いた。
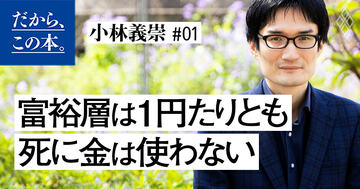
【異例の大ヒット】小学生向けの「暗算ドリル」が大人に大反響の理由とは?
2022年12月7日に発売した『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』。これは、11×11から19×19のかけ算を暗算できる「おみやげ算」という方法を紹介しているものです。2023年4月時点で早くも40.5万部を突破し、話題となっています。小学3年生以上を対象とした本書ですが、大人の「脳トレ」としても非常に人気なのだとか。「大人の読者からの評判はどういったものか」「大人にも役立つものなのか」などについて、著者である東大卒プロ算数講師の小杉拓也氏にお話を伺いました。(取材・構成/神代裕子)

中学受験生に怒涛の勢いで広がっている「11×11から19×19の暗算法」とは?
1点の差が命運を分ける、中学受験。親としても「ぜひ受かってほしい」と切実に願っていることでしょう。そんな中学受験生を持つ親の間で、話題になっている本があります。それは、『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』です。本書では、11×11から19×19の暗算ができる「おみやげ算」という方法を紹介しています。このおみやげ算を身につけることが、中学受験にどのように役立つのか。著者である東大卒プロ算数講師の小杉拓也氏に、詳しくお話を聞きました。(取材・構成/神代裕子)