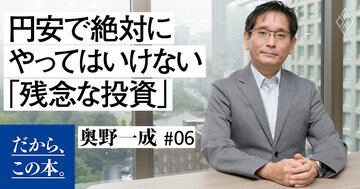ダイヤモンド社書籍編集局
1万人を接客した美容部員が教える「30代からメイクが急に似合わなくなる」の正体
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。メイク方法は何も変えていないはずなのに、なぜか違和感……。似合わなくなってきた気がするけど、その原因がわからない。そんな「アラサー以降、メイクがなんとなく変」問題、どう解決したらいいのでしょう。今回はBAパンダさんに、30代以降、メイクがなんとなく変になる理由について、聞いてみました!

日本発のアドラー心理学入門書が世界1000万部を突破した「3つの理由」
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』が世界累計1000万部を突破し、欧米でも230万部に達した。日本のノンフィクション書籍が欧米圏で翻訳されることは極めて稀だ。勇気シリーズは世界でどう読まれ、なぜこれほど広まったのか。その秘密を翻訳エージェントに訊く。
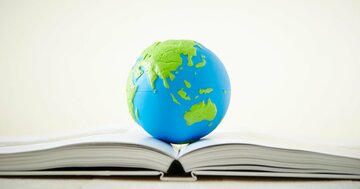
【スケジューリングがすべて】生産性が最大化する「月火水木金土日」それぞれの過ごし方
仕事に追われてあっという間に1日が終わり、1週間、1ヵ月、1年とどんどん時間が過ぎていく。けれども暇さえあればSNSやYouTubeを見てばかりで、脳疲労やストレスがなくならない。そんな毎日の繰り返しでいつか後悔するかもしれない生活をリセットするための処方箋が発売された。会社員時代に音楽プロデューサーとしてミリオンセラーを10回記録したあと39歳で退職してすべてリセットし、ニュージーランドに移住した四角大輔さんの新刊『超ミニマル主義』だ。独立後の2012年に上梓してベストセラーになったデビュー作『自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと』から10年目。移住後も世界を旅しながら事業運営、メディア連載、プロデュース業などに携わってきた四角さんが再びライフスタイルをリセットし、超シンプルで楽な働き方を実現するためのノウハウを詰め込んだ内容となっている。「最小限=ミニマル」を極めて、自分の可能性の「最大限=マックス」を引き出す。「超効率化×超集中」で成果を出し続けながら、自由で豊かな人生を手に入れる。そのために不要なモノ・コト・情報をすべて手放すライフハック術をまとめた本書から、定期的に連休をとるバカンス思考の重要性について四角さんに語ってもらった。

【池上彰】若い世代に「不都合な未来」をひっくり返すためにすべきこと
『政治のことよくわからないまま社会人になった人へ』の著者でジャーナリストの池上彰さんに、私たちが、とくに若い世代が選挙で政治に参加する意味と必要性について聞いた。
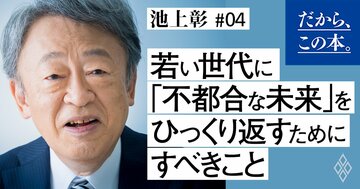
日本発のノンフィクション書籍を世界に売り込む「不可能なミッション」はなぜ達成できたのか?
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』が世界累計1000万部を突破し、欧米でも230万部に達した。日本のノンフィクション書籍が欧米圏で翻訳されることは極めて稀だ。なぜ勇気シリーズはこれほど成功できたのか。その秘密を世界に同書を広めた著作権エージェントに訊いた。

脳疲労とストレスが激減する、とっておきの「オンとオフの切り替え方」とは?
仕事に追われてあっという間に1日が終わり、1週間、1ヵ月、1年とどんどん時間が過ぎていく。けれども暇さえあればSNSやYouTubeを見てばかりで、脳疲労やストレスがなくならない。そんな毎日の繰り返しでいつか後悔するかもしれない生活をリセットするための処方箋が発売された。会社員時代に音楽プロデューサーとしてミリオンセラーを10回記録したあと39歳で退職してすべてリセットし、ニュージーランドに移住した四角大輔さんの新刊『超ミニマル主義』だ。独立後の2012年に上梓してベストセラーになったデビュー作『自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと』から10年目。移住後も世界を旅しながら事業運営、メディア連載、プロデュース業などに携わってきた四角さんが再びライフスタイルをリセットし、超シンプルで楽な働き方を実現するためのノウハウを詰め込んだ内容となっている。「最小限=ミニマル」を極めて、自分の可能性の「最大限=マックス」を引き出す。「超効率化×超集中」で成果を出し続けながら、自由で豊かな人生を手に入れる。そのために不要なモノ・コト・情報をすべて手放すライフハック術をまとめた本書から、今回は、圧倒的な成果を出す仕事術について四角さんに語ってもらった。
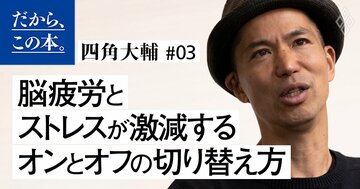
【池上彰】社内キャリアを断たれて気づいた「自分にしかない専門性」
『会社のことよくわからないまま社会人になった人へ』の著者でジャーナリストの池上彰さんに、50代で転機を迎えた自身のキャリアの話や、後悔しない就活や転職のために必要なものについて伺った。
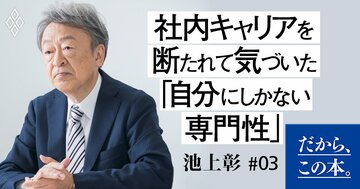
【“ネット依存”が病気の原因に…】「スマホ依存症の人」が今すぐ始めるべきこと
仕事に追われてあっという間に1日が終わり、1週間、1ヵ月、1年とどんどん時間が過ぎていく。けれども暇さえあればSNSやYouTubeを見てばかりで、脳疲労やストレスがなくならない。そんな毎日の繰り返しでいつか後悔するかもしれない生活をリセットするための処方箋が発売された。会社員時代に音楽プロデューサーとしてミリオンセラーを10回記録したあと39歳で退職してすべてリセットし、ニュージーランドに移住した四角大輔さんの新刊『超ミニマル主義』だ。独立後の2012年に上梓してベストセラーになったデビュー作『自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと』から10年目。移住後も世界を旅しながら事業運営、メディア連載、プロデュース業などに携わってきた四角さんが再びライフスタイルをリセットし、超シンプルで楽な働き方を実現するためのノウハウを詰め込んだ内容となっている。「最小限=ミニマル」を極めて、自分の可能性の「最大限=マックス」を引き出す。「超効率化×超集中」で成果を出し続けながら、自由で豊かな人生を手に入れる。そのために不要なモノ・コト・情報をすべて手放すライフハック術をまとめた本書から、今回は、圧倒的な成果を出す仕事術について四角さんに語ってもらった。
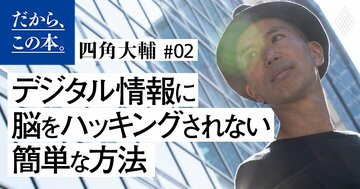
【池上彰】「お金の増やし方」を学ぶ、たった1つの方法
今さら恥ずかしくて聞けないニュースのことを、わかりやすく解説することで定評のあるジャーナリストの池上彰さんに、「経済を知らないまま」の社会人が多い理由、そして経済を知ることの重要性について話を聞いた。
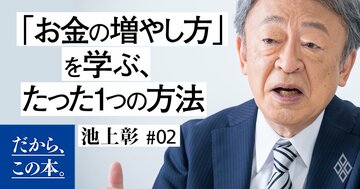
【池上彰】「学生時代にもっと勉強しておけばよかった」と後悔する社会人のための「学び直し」のコツ
今さら恥ずかしくて聞けないニュースのことを、わかりやすく解説することで定評のあるジャーナリストの池上彰さんに、いかにして社会人が学び直しをすればいいのかを伺った。
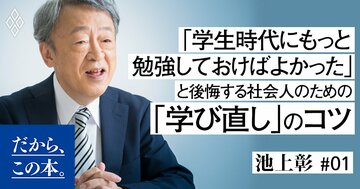
【最も“非生産的”な働き方は何?】仕事を軽くして圧倒的な成果を出すたった1つの方法
仕事に追われてあっという間に1日が終わり、1週間、1ヵ月、1年とどんどん時間が過ぎていく。けれども暇さえあればSNSやYouTubeを見てばかりで、脳疲労やストレスがなくならない。そんな毎日の繰り返しでいつか後悔するかもしれない生活をリセットするための処方箋が発売された。会社員時代に音楽プロデューサーとしてミリオンセラーを10回記録したあと39歳で退職してすべてリセットし、ニュージーランドに移住した四角大輔さんの新刊『超ミニマル主義』だ。独立後の2012年に上梓してベストセラーになったデビュー作『自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと』から10年目。移住後も世界を旅しながら事業運営、メディア連載、プロデュース業などに携わってきた四角さんが再びライフスタイルをリセットし、超シンプルで楽な働き方を実現するためのノウハウを詰め込んだ内容となっている。「最小限=ミニマル」を極めて、自分の可能性の「最大限=マックス」を引き出す。「超効率化×超集中」で成果を出し続けながら、自由で豊かな人生を手に入れる。そのために不要なモノ・コト・情報をすべて手放すライフハック術をまとめた本書から、今回は、圧倒的な成果を出す仕事術について四角さんに語ってもらった。
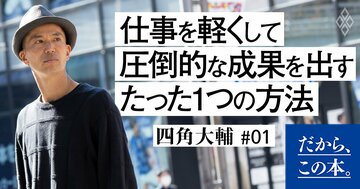
生きた時間を生み出す!どんな時短術にも勝る「判断力」の鍛え方
医療が進歩して平均寿命が延びていく中で、健康でいられる期間をのばしたいと考える人は多いだろう。しかし、体の健康と同じくらい重要な脳の健康について、どのくらいケアしているだろうか。「老化に対してつらい、苦しいという気持ちではなく、楽しみながら老化のスピードを遅らせることができればと考えている」と話すのは、『1分間瞬読ドリル』の著者である山中恵美子さんだ。本書は子どもからシニアまでが、楽しみながら脳トレができる。山中さんに、シニアの方が脳をトレーニングする重要性、『1分間瞬読ドリル』がシニアに向いている理由を聞いた。
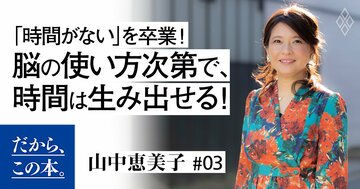
「あの人の名前、何だっけ?」がなくなる画期的メソッド
医療が進歩して平均寿命が延びていく中で、健康でいられる期間をのばしたいと考える人は多いだろう。しかし、体の健康と同じくらい重要な脳の健康について、どのくらいケアしているだろうか。「老化に対してつらい、苦しいという気持ちではなく、楽しみながら老化のスピードを遅らせることができればと考えている」と話すのは、『1分間瞬読ドリル』の著者である山中恵美子さんだ。本書は子どもからシニアまでが、楽しみながら脳トレができる。山中さんに、シニアの方が脳をトレーニングする重要性、『1分間瞬読ドリル』がシニアに向いている理由を聞いた。
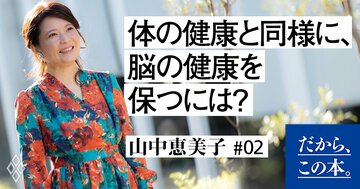
本を速く読む「瞬読」で、脳に秘められた力を伸ばす
「子どもたちの能力を最大限に伸ばしたい」という塾の経営者の想いから生まれたのが「瞬読」というメソッドだ。瞬読のスキルを身につけたことで、自分の発言に自信をもち、積極的に物事に取り組む子どもが増えているのだという。瞬読のメソッドをベースに、脳の6つの力を鍛えられるのが『1分間瞬読ドリル』だ。著者である山中恵美子さんに、瞬読が生まれた経緯、これからの時代に求められる能力について聞いた。
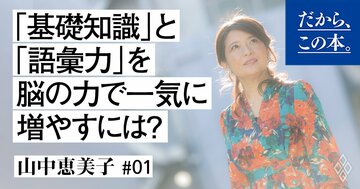
【メモの取り方でわかる】「単に悩んでるだけの人」と「深く考えている人」の違いとは?
知的生産性をあげるためにメモを活用したいと考える人は多い。ノート術やメモ術に関する書籍は数多く存在しているが、それぞれ手法は異なる。そのため、メモを活用したいと思いながらも、具体的にどんな運用をしたらよいのか悩んでしまう人も少なくないだろう。そんな方の悩みに答えてくれるのが、日本一ノートを売る会社「コクヨ株式会社」の社員、下地寛也さんの書いた『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)だ。発売から1週間たらずで重版が決まり、今、話題のビジネス書である。下地さんは今まで数多くの仕事ができる人のメモをリサーチした、いわばノートのプロフェッショナルだ。本書では、2種のノートを使い分けることで、正解のない問いに対して自分らしい答えを出す力を磨ける実践的なメモ術を紹介している。今回の記事ではアウトプットメモについて、下地さんに聞いた。
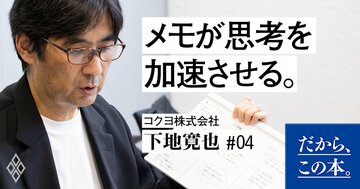
「これ、どう思う?」と聞かれて、自分の言葉で返せる人・返せない人の差
知的生産性をあげるためにメモを活用したいと考える人は多い。ノート術やメモ術に関する書籍は数多く存在しているが、それぞれ手法は異なる。そのため、メモを活用したいと思いながらも、具体的にどんな運用をしたらよいのか悩んでしまう人も少なくないだろう。そんな方の悩みに答えてくれるのが、日本一ノートを売る会社「コクヨ株式会社」の社員、下地寛也さんの書いた『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)だ。発売から1週間たらずで重版が決まり、今、話題のビジネス書である。下地さんは今まで数多くの仕事ができる人のメモをリサーチした、いわばノートのプロフェッショナルだ。本書では、2種のノートを使い分けることで、正解のない問いに対して自分らしい答えを出す力を磨ける実践的なメモ術を紹介している。今回の記事ではインプットメモについて、下地さんに聞いた。
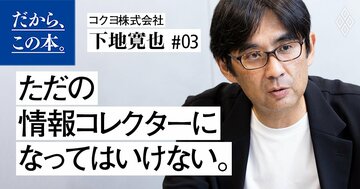
「スマホメモ」を、今すぐ「手書きメモ」に変えたほうがいい4つの理由
知的生産性をあげるためにメモを活用したいと考える人は多い。ノート術やメモ術に関する書籍は数多く存在しているが、それぞれ手法は異なる。そのため、メモを活用したいと思いながらも、具体的にどんな運用をしたらよいのか悩んでしまう人も少なくないだろう。そんな方の悩みに答えてくれるのが、日本一ノートを売る会社「コクヨ株式会社」の社員、下地寛也さんの書いた『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)だ。発売から1週間たらずで重版が決まり、今、話題のビジネス書である。下地さんは今まで数多くの仕事ができる人のメモをリサーチした、いわばノートのプロフェッショナルだ。本書では、2種のノートを使い分けることで、正解のない問いに対して自分らしい答えを出す力を磨ける実践的なメモ術を紹介している。今回の記事では、手書きメモの効用について、下地さんに聞いた。
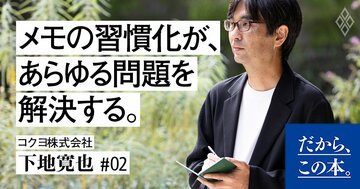
【コクヨのトップ社員が答える】ノートは1冊にまとめるべきか? キレイに書くべきか?
知的生産性をあげるためにメモを活用したいと考える人は多い。ノート術やメモ術に関する書籍は数多く存在しているが、それぞれ手法は異なる。そのため、メモを活用したいと思いながらも、具体的にどんな運用をしたらよいのか悩んでしまう人も少なくないだろう。そんな方の悩みに答えてくれるのが、日本一ノートを売る会社「コクヨ株式会社」の社員、下地寛也さんの書いた『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)だ。発売から1週間たらずで重版が決まり、今、話題のビジネス書である。下地さんは今まで数多くの仕事ができる人のメモをリサーチした、いわばノートのプロフェッショナルだ。本書では、2種のノートを使い分けることで、正解のない問いに対して自分らしい答えを出す力を磨ける実践的なメモ術を紹介している。今回の記事では、メモ術を取り入れたい人が知りたい疑問について、下地さんに聞いた。
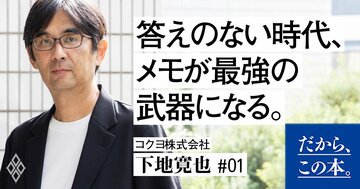
【東大卒サイエンス作家が教える】地球上の生物を支配しているたった3つの要因
地球生物の奇跡の物語をダイナミックに描きだした『超圧縮 地球生物全史』(ヘンリー・ジー著、竹内薫訳)を読むと世界の見方が変わる。読んでいて興奮が止まらないこの画期的な生物史を翻訳したのは、サイエンス作家の竹内薫さんだ。竹内さんに、本書の魅力について語ってもらった。
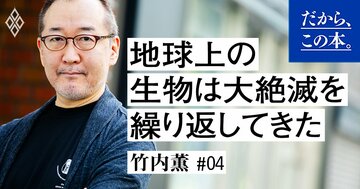
【プロ投資家が解説】円安で絶対にやってはいけない「投資のミス」ワースト1
円安だからといって、慌ててドル預金に変えても、意味がない。そう語るのは、長期厳選投資が専門のファンドマネージャーである奥野一成氏だ。主にプロの投資家から約4000億円の資産を預かり、運用実績を上げ続ける奥野氏は、日本におけるバフェット流投資のパイオニア。奥野氏の思考法を余すところなく解説した新刊『ビジネスエリートになるための 投資家の思考法』も、発売当初から話題を呼んでいる。「お金に困らない人生を送るにはどうしたらいいか?」という問いについて、さまざまな企業のケーススタディを通して考える、全ビジネスパーソン必携の書だ。YouTubeやSNSには安易な情報発信をする「自称投資家」も多く、投資初心者の混乱を招いてしまうこともある。そこで今回は、『投資家の思考法』の発売を記念し、「投資の本質」について深く掘り下げるインタビューを実施することにした。投資の疑問・お金の疑問について、奥野氏にとことん答えていただこう。