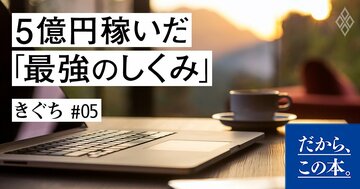ダイヤモンド社書籍編集局
うるさい「高圧的な人」を一発で黙らせるシンプルな一言
聞く力、気配り、謙虚、冷静、観察眼……「静かで控えめ」な人にスポットを当てて大きな話題となっている『「静かな人」の戦略書』。その著者に、貴重な特別インタビューを行った。騒がしく主張する人が目立ちやすい世界で、「静かな人」がその魅力を最大限に発揮する方法とは?

株で資産を増やせる人「共通する考え方」
「株で儲ける人」と「損する人」の差はどこにあるのだろうか。何をすれば、株で勝てる人になれるのか。ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげた株のスペシャリスト窪田真之氏(楽天証券経済研究所所長)に話を聞いた。
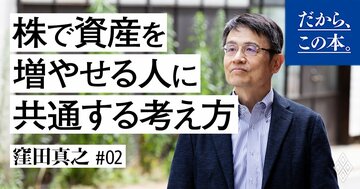
株で大損してしまう人に共通する「1つの特徴」
「株で儲ける人」と「損する人」の差はどこにあるのだろうか。何をすれば、株で勝てる人になれるのか。ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげた株のスペシャリスト窪田真之氏(楽天証券経済研究所所長)に話を聞いた。
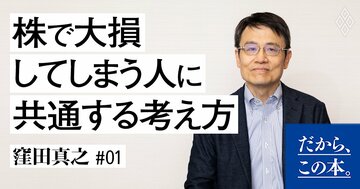
【元外交官が解説】ロシア国民が「強いリーダー」を強烈に支持するワケ
ロシア・ウクライナの戦争が起こり、世界は今、緊張感が高まり、分断へと向かっている。日本にとっても、ロシアは隣国の1つであり、外交上でも重要な国であるにもかかわらず、私たちは意外とロシアのことをわかっていない。今回は『ビジネスエリートの必須教養 「世界の民族」超入門』の著者で元外交官、世界96カ国を訪れた経験を持つ山中俊之さんに「ロシアとはいったいどんな国なのか?」を詳しく聞いた。ロシアの人々はどんなメンタリティを持っているのか。そして、どんなリーダーを求めるのか。そして、さらには今後世界はどのようになっていくのか。国際経験豊富な山中さんならではの「今後の世界の未来予想図」を語ってもらった。

【元外交官が解説】世界の「芸術や文化」が一気にわかるようになる1つの条件
グローバルに活躍する人たちが痛感するのが「常識の違い」。海外に滞在してみると、日本の常識がまったく通用せずに、戸惑うことは日常茶飯事です。今回は『ビジネスエリートの必須教養 「世界の民族」超入門』の著者で、世界96カ国を訪れた経験を持つ元外交官の山中俊之さんに「自身が体験した海外でのハプニング」を聞いてみた。テロや爆破事件から、地震に対する対応など、やはり日本の常識とはまったく違う出来事に世界では遭遇する。一歩間違えば、自分も爆破テロの犠牲者になっていたかもしれない生々しい話から、ブエノスアイレスで感動したタンゴの話題まで、バラエティに飛んだ話を聞かせてくれた。
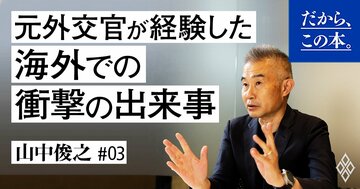
【雑談がラクになる】「ちょっとした会話」に使える話題ベスト3
聞く力、気配り、謙虚、冷静、観察眼……「静かで控えめ」な人にスポットを当てて大きな話題となっている『「静かな人」の戦略書』。その著者に、貴重な特別インタビューを行った。騒がしく主張する人が目立ちやすい世界で、「静かな人」がその魅力を最大限に発揮する方法とは?

教養を「知っているだけの人」と「使いこなす人」決定的な差
国際社会へ出ていくと「教養が大事」とよく言われる。教養がなければ、世界の人たちと世間話もできない。そんな話も耳にします。しかし、一言で「教養」と言っても、何を知り、何を語れるようになっていればいいのかイマイチよくわからない。今回は、そんな疑問を『ビジネスエリートの必須教養 「世界の民族」超入門』の著者であり、外交官としても活躍された山中俊之さんに話を聞いた。山中さんは世界96カ国に滞在した経験を持ち、さまざまな国や地域の人とも渡り合ってきた。そのなかには、自分の知識や教養が不十分で「ヒヤリ」とした経験もあると言う。そんな生々しい話も含めて、「日本人に求められる教養」について語ってもらった。
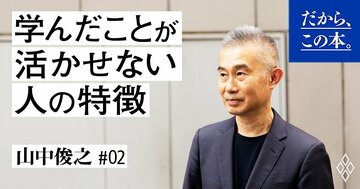
【元外交官が語る】「日本のニュース」が「世界標準の報道」からズレる理由
日本で生活していると「日本の報道」に触れることはあっても「世界の報道」に触れる機会はなかなかない。しかし、じつは世界では大きく報道されているニュースでも、日本ではほとんど報道されていないものもある。今回は『ビジネスエリートの必須教養 「世界の民族」超入門』の著者で元外交官、世界96カ国を訪れた経験を持つ山中俊之さんに「日本人に理解してもらいたい世界の時事問題ベスト3」を聞いてみた。さらに、山中さんがおすすめする「日本目線」だけでなく「世界の目線」に触れられるメディアも必見。
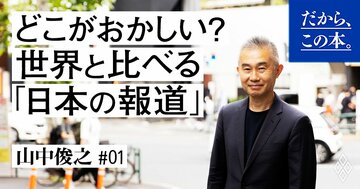
人気動物学者が語る「人類が絶滅する」3つの理由
みなさんは『わけあって絶滅しました。』という本をご存じだろうか。絶滅生物の「絶滅理由」を紹介して話題となり、累計90万部のベストセラーになった。7月には新刊となる絵本『わけあって絶滅したけど、すごんです。』が発売され、さらには漫画化、フィギュア化、大型展覧会化など、勢いが止まらない。4歳から98歳まで、幅広い読者から寄せられる読者ハガキには、大人からの感想文も目立つ。生き物が絶滅した理由に笑った人、驚いた人、同情した人などさまざまで、なかには絶滅生物と自分を重ねて「考えさせられた」といった感想も。監修者の動物学者・今泉忠明さんは、本シリーズの人気の理由を「絶滅生物をとおして、人間の在り方を見ることもできるから」だと分析する。今回は新刊の発売を記念して特別インタビューを実施。この記事で「人類が絶滅する理由」について、たっぷりと語ってもらった。

人気動物学者がおしえる「勉強が楽しくなる」本の読み方
新型コロナウイルス第7波が続くなか、自宅で過ごす夏休みを迎えた家庭も多い。子どもがYouTubeやゲームに夢中になる時間が長くなり、自宅学習の在り方に悩む親が増えている。そんな状況でぜひおすすめしたいのが、『わけあって絶滅しました。』シリーズ。累計90万部を突破し、4作目となる最新刊『わけあって絶滅したけど、すごいんです。』が7月に発売されたばかり。大阪では、初の大型展覧会となる「わけあって絶滅しました。展」(2022年9月4日まで)も開催中の、大人気作だ。4歳から98歳までの幅広い読者から寄せられた読者ハガキは1000通あまり。大きかったのが、子どもをもつ親からの反響。「子どもが生き物に興味をもって、図書館に通うようになった」「本の内容を暗記して、教えてくれる」「親子で水族館や博物館に行くようになった」といった、子どもの変化に対する驚きの声が絶えない。今回は新刊の発売を記念して特別インタビューを実施。「子どもが一番会いたい著者」ともいわれる本書の監修者、動物学者の今泉忠明さんに「勉強が楽しくなる本の読み方」について聞いた。
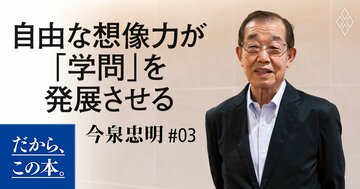
【頭はいいけど、調子に乗る】「へんないきもの」代表・人間の末路とは?
みなさんは『わけあって絶滅しました。』という本をご存じだろうか。絶滅生物の「絶滅理由」を紹介して話題となり、累計90万部のベストセラーになった。7月には新刊の絵本『わけあって絶滅したけど、すごんです。』が発売され、さらには漫画化、フィギュア化、大型展覧会化など、勢いが止まらない。4歳から98歳まで、幅広い読者から寄せられる読者ハガキには、大人からの感想文も目立つ。生き物が絶滅した理由に笑った人、驚いた人、同情した人などさまざまで、なかには絶滅生物と自分を重ねて「考えさせられた」といった感想も。監修者の動物学者・今泉忠明氏は、本シリーズの人気の理由を「絶滅生物をとおして、人間の在り方を見ることもできるから」だと分析する。今回のインタビューでは、今泉氏に「ヒトという生き物の特性」について語ってもらった。
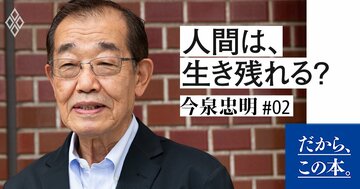
【子どもの好奇心を伸ばす】「絶滅」を学ぶと、世界の見え方が変わる3つの理由
新型コロナウイルス第7波が続くなか、自宅で過ごす夏休みを迎えた家庭も多い。子どもがYouTubeやゲームに夢中になる時間が長くなり、自宅学習の在り方に悩む方も多いのでは。そんな状況でぜひおすすめしたいのが、『わけあって絶滅しました。』シリーズ。累計90万部を突破し、4作目となる最新刊『わけあって絶滅したけど、すごいんです。』が7月に発売されたばかり。大阪では、初の大型展覧会となる「わけあって絶滅しました。展」(2022年9月4日まで)も開催中の、大人気作だ。4歳から98歳までの幅広い読者から寄せられた読者ハガキは1000通あまり。大きかったのが、子どもをもつ親からの反響。「子どもが生き物に興味をもって、図書館に通うようになった」「本の内容を暗記して、教えてくれる」「親子で水族館や博物館に行くようになった」といった、子どもの変化に対する驚きの声が絶えない。本シリーズの監修者である今泉忠明氏は、「絶滅生物は、子どもの好奇心を伸ばすのにぴったりのテーマ」だと語る。「絶滅」を知ることで起きる変化について聞いた。(取材・構成/樺山美夏、撮影/橋本千尋)
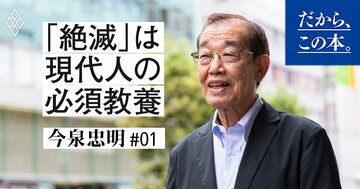
「ストレスに強い人」「弱い人」考え方の1つの違い
聞く力、気配り、謙虚、冷静、観察眼……「静かで控えめ」な人にスポットを当てて大きな話題となっている『「静かな人」の戦略書』。その著者に、貴重な特別インタビューを行った。騒がしく主張する人が目立ちやすい世界で、「静かな人」がその魅力を最大限に発揮する方法とは?
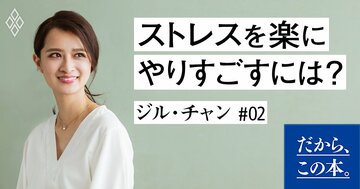
【カジサックが明かす】人気絶頂期に芸能界を失踪した僕が見つけた「心が折れやすい人」の共通点
必死に努力しているつもりが結果につながらない、周りの目を気にしてばかりで自分らしくいられない、人生のどん底をどう乗り越えたらいいのかわからない……。人気YouTuber「カジサック」に、「心が折れる直前の危険信号」について、とことん語ってもらった。
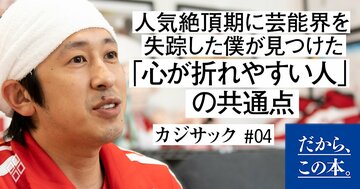
【カジサックの5人子育て】子どもの「考える力」を奪うたった一つの言葉
必死に努力しているつもりが結果につながらない、周りの目を気にしてばかりで自分らしくいられない、人生のどん底をどう乗り越えたらいいのかわからない……。人気YouTuber「カジサック」に、「5人の子どもとの触れ合い方」について、とことん語ってもらった。
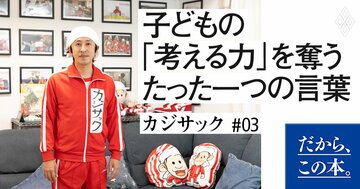
【カジサックが明かす】初対面でもつい心を開いてしまう「3つの聞き方」
必死に努力しているつもりが結果につながらない、周りの目を気にしてばかりで自分らしくいられない、人生のどん底をどう乗り越えたらいいのかわからない……。人気YouTuber「カジサック」に、「伝え方のコツ」について、とことん語ってもらった。
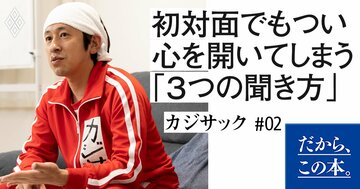
「読むのがめんどう」残念な文章の共通点
「読むのがめんどう」と思われる残念な文章。5億円ブロガーのきぐち氏に、稼ぐための文章術について聞いた。
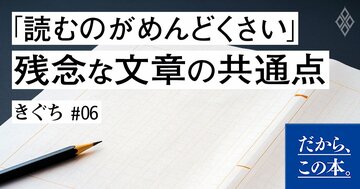
「無口でも評価される人」と「軽んじられる人」の1つの違い
聞く力、気配り、謙虚、冷静、観察眼……「静かで控えめ」な人にスポットを当てて大きな話題となっている『「静かな人」の戦略書』。その著者に、貴重な特別インタビューを行った。騒がしく主張する人が目立ちやすい世界で、「静かな人」がその魅力を最大限に発揮する方法とは?
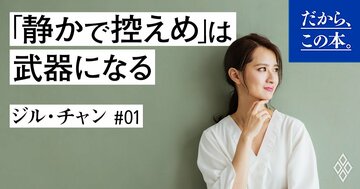
「いくら努力しても報われない環境」から抜け出すたった一つの方法
必死に努力しているつもりが結果につながらない、周りの目を気にしてばかりで自分らしくいられない、人生のどん底をどう乗り越えたらいいのかわからない……。人気YouTuber「カジサック」に、「自分に合った環境の探し方」について、とことん語ってもらった。
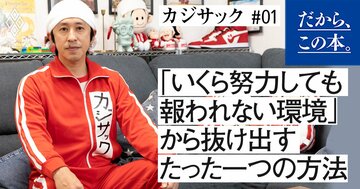
「やる気に頼らず、しくみでまわす」ブログで5億円稼いだ方法
「やる気に頼らず、しくみでまわす」5億円ブロガーのきぐち氏に「ブログで稼ぐためのしくみ」を聞いた。