ダイヤモンド社書籍編集局
つらい勉強でも楽しくなる「最強の暗示」とは?
つらい勉強でも楽しくなる「最強の暗示」とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に聞いた。
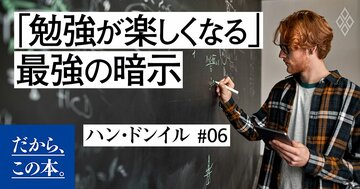
「学びは感動から始まる」古代ギリシャ人のすごい思考法
「学びは感動から始まる」古代ギリシャ人のすごい思考法とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に聞いた。
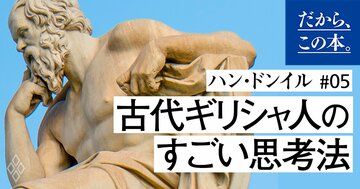
極貧生活からイタリア留学、人生を変えた「父のたった1つの教え」
極貧生活からイタリア留学、人生を変えた「父のたった1つの教え」とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に聞いた。
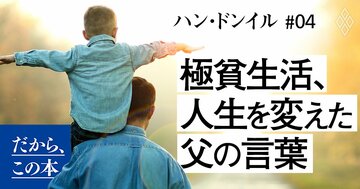
世界一難しい!? バチカン裁判所のすごい採用試験
世界一難しい!? バチカン裁判所のすごい採用試験とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に、ラテン語の魅力を聞いた。
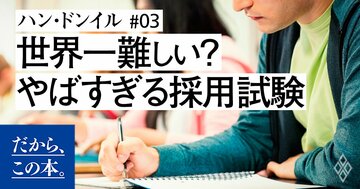
とてつもなく頭のいい人がやっている「最高の読書法」
とてつもなく頭のいい人がやっている「最高の読書法」とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に読書法を聞いた。
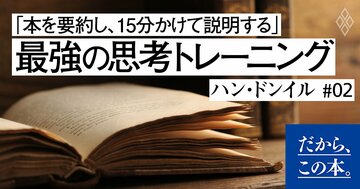
「お金があっても満たされない人」を救う3つの言葉
「お金があっても満たされない人」を救う3つの言葉。東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏に、ラテン語の魅力を聞いた。
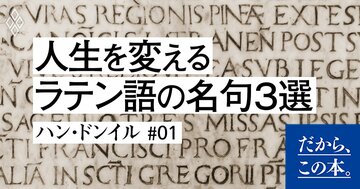
「有能なのに結果が出ない人」が軽視しているたった1つの「力」とは?
「なぜ、正論を言っても黙殺されるのか」「こんなに頑張っているのに、どうして誰も協力してくれないのか」。組織で働いていれば、こうした悩みを抱えることはよくあることです。しかし、それを嘆いても、怒っても、何も解決しません。重要なのは、組織内の「人間心理」や「組織力学」を深く洞察すること。そして、社内に味方を増やし、組織を動かす手立てを講じる必要があるのです。その方法を詳しく解説した『Deep Skill ディープ・スキル』という書籍がベストセラーとなっている。本連載では、著者・石川明さんに「ディープ・スキル」について詳しく語っていただいた。
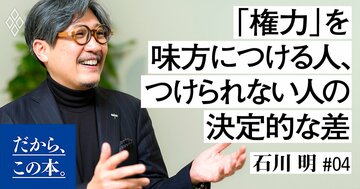
【図で解決!】「打ち合わせ」の後にモヤモヤが残らない“最強マトリックス”大公開!
「なぜ、正論を言っても黙殺されるのか」「こんなに頑張っているのに、どうして誰も協力してくれないのか」。組織で働いていれば、こうした悩みを抱えることはよくあることです。しかし、それを嘆いても、怒っても、何も解決しません。重要なのは、組織内の「人間心理」や「組織力学」を深く洞察すること。そして、社内に味方を増やし、組織を動かす手立てを講じる必要があるのです。その方法を詳しく解説した『Deep Skill ディープ・スキル』という書籍がベストセラーとなっている。本連載では、著者・石川明さんに「ディープ・スキル」について詳しく語っていただいた。
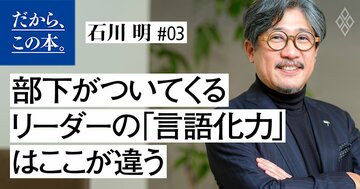
上司が職場の「心理的安全性」よりも重視すべきこと・ベスト1
「なぜ、正論を言っても黙殺されるのか」「こんなに頑張っているのに、どうして誰も協力してくれないのか」。組織で働いていれば、こうした悩みを抱えることはよくあることです。しかし、それを嘆いても、怒っても、何も解決しません。重要なのは、組織内の「人間心理」や「組織力学」を深く洞察すること。そして、社内に味方を増やし、組織を動かす手立てを講じる必要があるのです。その方法を詳しく解説した『Deep Skill ディープ・スキル』という書籍がベストセラーとなっている。本連載では、著者・石川明さんに「ディープ・スキル」について詳しく語っていただいた。
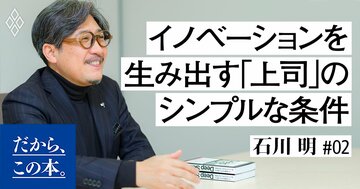
【30代後半のリーダーが共感!】「真面目でいい人」が仕事を頑張っても評価されないワケ
「なぜ、正論を言っても黙殺されるのか」「こんなに頑張っているのに、どうして誰も協力してくれないのか」。組織で働いていれば、こうした悩みを抱えることはよくあることです。しかし、それを嘆いても、怒っても、何も解決しません。重要なのは、組織内の「人間心理」や「組織力学」を深く洞察すること。そして、社内に味方を増やし、組織を動かす手立てを講じる必要があるのです。その方法を詳しく解説した『Deep Skill ディープ・スキル』という書籍がベストセラーとなっている。本連載では、著者・石川明さんに「ディープ・スキル」について詳しく語っていただいた。
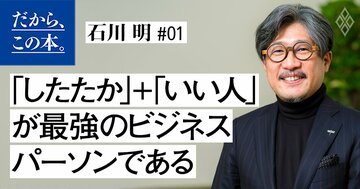
1万人を接客した美容部員が教える「アラサーからのアイプチ卒業メイク」
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。今回のテーマは、「アイプチ卒業メイク」。一重がコンプレックスで、10代の頃からアイプチを続けているものの、30代になり、そろそろナチュラルなメイクに挑戦したい気持ちが強くなってきました。とはいえ、ずっとアイプチに慣れている人が、二重を諦め、一重メイクに挑戦するのは勇気がいるもの。どうしたら、一重ならではのメイクを楽しめるようになるでしょうか? そんなライターのリアルな悩みを、BAパンダさんに直接相談し、解決してもらうことにしました。大人っぽくて艶やかな、BAパンダさん考案の一重メイク、驚きの技術が満載です!

1万人を接客した美容部員が教える「眉毛が垢抜けない」を解決する超簡単なスゴ技
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。どれだけメイクを練習してもなかなか解決しないのが、「眉毛が対称に描けない問題」。左右でバランスがとれず、悪目立ちしてしまいがちな眉毛。どのように描いたらいいのでしょうか。BAパンダさんは、技術がなくても自然できれいな眉毛に見せられるポイントが、一つだけあるといいます。ライターの悩みを、BAパンダさんに解決していただくことにしました。

1万人を接客した美容部員が教える「毎日のスキンケアの前に必ずやるべきこと」
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。メイク方法は何も変えていないはずなのに、なぜか違和感……。似合わなくなってきた気がするけど、その原因がわからない。そんな「アラサー以降、メイクがなんとなく変」問題、どう解決したらいいのでしょう。今回はBAパンダさんに「マスクを取ったときの自分の顔に違和感」という悩みについて、聞いてみました。

1万人を接客した美容部員が教える「一瞬で透明感を出すベースメイクのコツ」
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。メイク方法は何も変えていないはずなのに、なぜか違和感……。似合わなくなってきた気がするけど、その原因がわからない。そんな「アラサー以降、メイクがなんとなく変」問題、どう解決したらいいのでしょう。今回はBAパンダさんに「肌全体が一瞬できれいになるベースメイク」のコツを教えてもらいました。

1万人を接客した美容部員が教える「マスクを取った自分の顔に違和感」を解消するコツ
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。メイク方法は何も変えていないはずなのに、なぜか違和感……。似合わなくなってきた気がするけど、その原因がわからない。そんな「アラサー以降、メイクがなんとなく変」問題、どう解決したらいいのでしょう。今回はBAパンダさんに「マスクを取ったときの自分の顔に違和感」という悩みについて、聞いてみました。
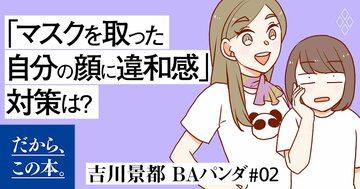
1万人を接客した美容部員が教える「30代からメイクが急に似合わなくなる」の正体
現役美容部員のBAパンダさんが、幼なじみのマンガ家吉川景都さんにメイクを教える『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった!」「まさに求めていた本!」と読者から圧倒的な共感を獲得、テレビ、ラジオ、SNSなどで話題の美容マンガです。メイク方法は何も変えていないはずなのに、なぜか違和感……。似合わなくなってきた気がするけど、その原因がわからない。そんな「アラサー以降、メイクがなんとなく変」問題、どう解決したらいいのでしょう。今回はBAパンダさんに、30代以降、メイクがなんとなく変になる理由について、聞いてみました!

日本発のアドラー心理学入門書が世界1000万部を突破した「3つの理由」
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』が世界累計1000万部を突破し、欧米でも230万部に達した。日本のノンフィクション書籍が欧米圏で翻訳されることは極めて稀だ。勇気シリーズは世界でどう読まれ、なぜこれほど広まったのか。その秘密を翻訳エージェントに訊く。
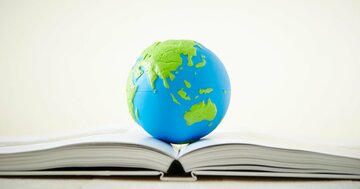
【スケジューリングがすべて】生産性が最大化する「月火水木金土日」それぞれの過ごし方
仕事に追われてあっという間に1日が終わり、1週間、1ヵ月、1年とどんどん時間が過ぎていく。けれども暇さえあればSNSやYouTubeを見てばかりで、脳疲労やストレスがなくならない。そんな毎日の繰り返しでいつか後悔するかもしれない生活をリセットするための処方箋が発売された。会社員時代に音楽プロデューサーとしてミリオンセラーを10回記録したあと39歳で退職してすべてリセットし、ニュージーランドに移住した四角大輔さんの新刊『超ミニマル主義』だ。独立後の2012年に上梓してベストセラーになったデビュー作『自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと』から10年目。移住後も世界を旅しながら事業運営、メディア連載、プロデュース業などに携わってきた四角さんが再びライフスタイルをリセットし、超シンプルで楽な働き方を実現するためのノウハウを詰め込んだ内容となっている。「最小限=ミニマル」を極めて、自分の可能性の「最大限=マックス」を引き出す。「超効率化×超集中」で成果を出し続けながら、自由で豊かな人生を手に入れる。そのために不要なモノ・コト・情報をすべて手放すライフハック術をまとめた本書から、定期的に連休をとるバカンス思考の重要性について四角さんに語ってもらった。

【池上彰】若い世代に「不都合な未来」をひっくり返すためにすべきこと
『政治のことよくわからないまま社会人になった人へ』の著者でジャーナリストの池上彰さんに、私たちが、とくに若い世代が選挙で政治に参加する意味と必要性について聞いた。
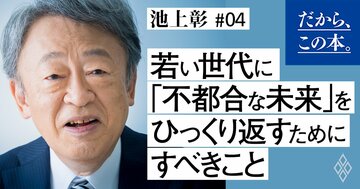
日本発のノンフィクション書籍を世界に売り込む「不可能なミッション」はなぜ達成できたのか?
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』が世界累計1000万部を突破し、欧米でも230万部に達した。日本のノンフィクション書籍が欧米圏で翻訳されることは極めて稀だ。なぜ勇気シリーズはこれほど成功できたのか。その秘密を世界に同書を広めた著作権エージェントに訊いた。
