今枝翔太郎
#6
カシオでは発売40周年を迎える時計ブランド「G-SHOCK」が経営の屋台骨となっている。プリンターやデジカメなど撤退を繰り返しているカシオでは、G-SHOCKに次ぐ「第二の稼ぎ頭」の育成が喫緊の課題だ。祖業の電卓や楽器事業は「第二の柱」になれるのか。カシオのビジネス構造が抱える課題を追う。

#5
ロレックスをはじめとする輸入高級時計の価格が高騰し、時計愛好家が「ロレックスマラソン」を繰り広げている。その一方で日本勢は腕時計の「ハイパーインフレ」に付いていけず、グローバル市場におけるプレゼンスの低下が顕著になっている。しかし業界関係者は「海外高級時計に対抗できる唯一の国産ブランドがある」と口をそろえる。玄人も認めるブランドとは何か。

#4
日系時計3社は、そろって時計事業の売上高が急回復している。ところが、各社の利益をつぶさに分析すると、セイコーは“独り負け”状態にある。しかし、業界関係者の見立てでは「将来的にセイコーは“独り勝ち”になる可能性すら秘めている」という。競合より稼げないセイコーのビジネス構造を解明するとともに、「反撃の秘策」を開陳する。

#3
シチズン時計は20年以上前に同族経営から脱却したのに対し、セイコーグループやカシオでは今もなお創業家が威光を放っているのが実態だ。老舗時計メーカー3社の歴史とブランド戦略をひもときながら、同族経営の功罪について徹底分析した。

#2
一昨年、カシオは前社長である樫尾和宏氏(現会長)による「パワハラ問題報道」で大揺れとなった。騒動の発端は、樫尾氏のパワハラ発言が収録された音声データが拡散されたこと。内部告発者は「ある意図」を持って通報に踏み切ったのだが、音声がメディアに流出してしまい、その意に反して騒動が独り歩きしてしまったのだという。パワハラ騒動の真相に迫る。

#1
電撃的なトップ交代で、時計業界に激震が走った。この4月、樫尾家が代々社長を務めてきたカシオ計算機で初の「非創業家」社長が誕生したのだ。創業メンバーである樫尾四兄弟の子息が経営幹部に名を連ねているにもかかわらず、非創業家のトップが選出されたのはなぜなのか。再び、社長のバトンが創業家へ受け継がれることはないのか。トップ人事の裏側に迫る。

予告
セイコー・シチズン・カシオ、時計御三家に迫り来る「ビジネスモデル崩壊」の危機
セイコー、シチズン、カシオ――。かつてお家騒動などで世間の耳目を集めた日本の「時計御三家」に、今度はビジネスモデル崩壊の危機が迫っている。ロレックスをはじめとする海外メーカーにはブランド力で圧倒的な差をつけられている上、スマートウォッチの台頭で異業種に市場を侵食されている。このままでは、名門3社のグローバル市場におけるプレゼンスは低下するばかりだ。プライド高き内弁慶企業が抱える「時計業界の闇」を描き切る。

日本製鉄がグループ商社の日鉄物産のTOBに踏み切った。それにより、日鉄物産は子会社化され、上場廃止が秒読みの状態だ。これが原因で、日鉄物産では退職者が相次いでいるという。

2019年度に過去最大の赤字を出した日本製鉄は、橋本英二社長の下でV字回復を成し遂げた。橋本社長は就任からまもなく丸4年を迎え、バトンタッチの時が近づいている。日本製鉄関係者らへの取材を基に、最新の役員人事を深読みし、次期社長候補を大胆に予測した。

#7
複合機大手のコニカミノルタは、2023年3月期に3期ぶりの黒字を計上する見通しだ。コニカミノルタの大幸利充社長が、赤字脱却までの苦労を語るとともに、先細りがみえている複合機事業の将来像を明らかにする。

#6
今年1月、複合機業界首位のリコーが社長交代を発表した。新社長に就任する大山晃氏は、現社長の山下良則氏が進めてきたデジタルサービス路線の“継承と加速”を標榜している。ここ数年で積み重ねた「大量の企業買収劇」に焦点を当てて、リコー新社長が担う首位固め戦略を明らかにする。

#5
米中対立が激しさを増す中、ついに中国が日本の“お家芸”である複合機に照準を定めた。まずは政府調達から日系企業を締め出すことで揺さぶりをかけ、結果的に日本が中国へ複合機技術を供与するよう促しているのだ。日系メーカーが抱える「中国三大リスク」を分かりやすく解説するとともに、各社の“脱・中国依存”戦略に迫る。

#4
富士フイルムホールディングスとキヤノンは、長らく複合機市場でしのぎを削ってきた宿命のライバルだ。複合機市場の先細りが懸念される中、新たな収益の柱を構築できているのはどちらの企業なのか。「事業の多角化進捗度」対決で判定した。

#3
一昨年、米ゼロックス・ホールディングスとたもとを分かった富士フイルムホールディングス。知名度の高い「ゼロックスブランド」を失ったダメージは大きいはずだが、目下のところ業績は絶好調だ。ゼロックスの“呪縛”から解き放たれた富士フイルムの快進撃の真価に迫る。

#2
世界の複合機市場はシェア9割を日系メーカーが握り、国内製造業の“ラストリゾート”ともいえる。業界をけん引する日系各社は、コロナ禍がいまだ収束しない中でも業績好調で、工場はフル稼働状態にあるという。この市場の特異性を明らかにするとともに、“好調”をうたう各社を待ち受ける「落とし穴」の正体に迫る。
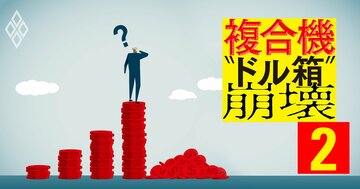
#1
リコー、キヤノン、富士フイルムホールディングスと名だたる日系企業が連なる複合機業界。ところが、オフィス需要が減退する中で市場の縮小は避けられそうになく、遠からず業界再編が行われることは必至の情勢だ。そこで業界関係者への取材や各社の複合機事業への依存度などを基に「複合機業界の再編シナリオ」を一挙公開。業績不振の米ゼロックス・ホールディングスの“買い手”や日系メーカーによる合従連衡の模様を大胆に予測する。

#9
半導体の製造には、電子回路パターンをウエハーに焼き付ける露光装置が不可欠だ。現在、この半導体露光装置市場はオランダのASMLホールディングの独壇場となっており、とりわけ最先端のEUV(極端紫外線)露光装置ではシェア100%を誇る。ところがここにきて、かつて業界をけん引した日本勢が反撃に出ようとしている。キヤノンとニコンが、それぞれ独自の路線に光明を見いだしているのだ。最先端装置を持たないキヤノンとニコンの“勝ち筋”を解説するとともに、各社に忍び寄る地政学リスクに迫る。

#6
スマートフォンのカメラやデジタルカメラに用いられるイメージセンサーで世界シェアトップをひた走るソニーグループ。イメージセンサーの需要は一段と拡大しており、ソニーが今のペースで増産を続けていけば、次期中期計画の3年間(2024~26年)で設備投資額が1兆円を突破するのは確実な情勢だ。ところが、米アップルに依存した現状のビジネスモデルは危険をはらんでいる。本記事では、各種データや関係者の話から見えてきた「アップル依存」解消の鍵に迫る。ソニーが手を組むホンダは、ソニーのイメージセンサー事業“第二の柱”となれるのだろうか?

中国の電気自動車大手、比亜迪(BYD)がこの1月末から日本の乗用車市場に参入する。今や世界トップクラスの電気自動車(EV)メーカーであるBYDは、日本でもEVバスやフォークリフトで徐々に存在感を高めつつある。今回ダイヤモンド編集部は、満を持して乗用車投入に踏み切ったBYDジャパンの劉学亮社長を直撃。日本での販売戦略を聞いた。

#59
販売価格改善が急務となっている日本の鉄鋼業界。鉄鋼大手のJFEスチールも、2022年は値上げを進めてきた。23年はさらなる値上げに踏み切るのだろうか。本稿では、JFEスチールの北野嘉久社長に23年の価格戦略を聞いた。併せて、日本鉄鋼連盟会長も務める北野氏に、業界全体の課題となっている「グリーン鋼材」の普及についても語ってもらった。
