書籍オンライン編集部
「自分であらゆる仕事を抱え込む管理職」と「部下がどんどん成果を出すリーダー」の決定的な違い
上司・管理職のバイブルとして世界で1300万部を超えるベストセラーとなった名著『1分間マネジャー』を送り出したケン・ブランチャードらが、リーダーシップについて著した『1分間リーダーシップ』。そして、その改訂新版が本記事で紹介する『新1分間リーダーシップ』だ。過去40年間にフォーチュン1000の優良企業のほとんどで、また世界中の急成長する新興企業で伝授されてきたリーダーシップのモデルとは?(文/上阪徹)

「無能すぎる管理職」がよく口にする言葉・ワースト1[見逃し配信・5月第4週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![「無能すぎる管理職」がよく口にする言葉・ワースト1[見逃し配信・5月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/4/360wm/img_6a6a6b84b1434edfc82a2547b8efb3bb157183.jpg)
【“配慮できない人”の特徴】言われた相手が「心の中でモヤモヤしている言葉」3選
気づかいは言葉づかいにも表れる。言うほうは気持ちよくても、耳にした人がモヤモヤしてしまう言葉は、避けたほうがいいだろう。そんな言葉について教えてくれているのは『気づかいの壁』だ。これまでおよそ200社、2万人のビジネスパーソンに向けてコミュニケーションスキル等の研修やセミナーを行ってきた著者、川原礼子氏は、サービスのプロではない一般のビジネスパーソンに向けて「ちょうど良い気づかい」のコツを教えてくれている。本記事では、本書の内容から、言ってしまいがちだが「言われた相手がモヤモヤする言葉」について紹介する。(構成:小川晶子)

30代以降「ぐんと成長する人」「限界がくる人」決定的な1つの差
機嫌がいい人は「ドライでいい」と知っている──。そう語るのは、70歳のプロダクトデザイナー・秋田道夫さんです。誰もが街中でみかけるLED式薄型信号機や、交通系ICカードのチャージ機、虎ノ門ヒルズのセキュリティーゲートなどの公共機器をデザインしてきた秋田さんは、人生を豊かに生きるためには、「機嫌よくいること」「情緒が安定していること」が欠かせないと語ります。そんな秋田さんの「まわりに左右されないシンプルな考え方」をまとめた書籍『機嫌のデザイン』は、発売直後に重版と話題を呼び、「いつも他人と比べてしまう」「このままでいいのか、と焦る」「いつまでたっても自信が持てない」など、仕事や人生に悩む読者から、多くの反響を呼んでいます。悩んでしまった時、どう考えればいいのでしょうか。本連載では、そんな本書から、「毎日を機嫌よく生きるためのヒント」を学びます。今回のテーマは、「小さな失敗に落ち込みすぎないための心の保ち方」についてです。(構成:川代紗生)

元楽天球団社長が「仕事のできない社員を切り捨てるのが間違い」だと気づいた深いワケ
「2:6:2の法則」をご存じだろうか。これは、組織というものは「優秀な成績を収める2割のメンバー」「普通の成績を収める6割のメンバー」「成績の悪い2割のメンバー」に分かれる傾向が強いというものだ。東北楽天ゴールデンイーグルス社長として「日本一」と「収益拡大」を達成し、現在は、宮城県塩釜市の廻鮮寿司「塩釜港」の社長にして、日本企業成長支援ファンド「PROSPER」の代表として活躍中の立花陽三氏は、初著書である『リーダーは偉くない。』の中で、「『以前は下位2割のメンバーを入れ替えるしかない』と思い詰めていたが、今となっては間違いだったと思う」と語る。考えを改めた立花氏は一体どういった対応を取ったのか。本記事では、本書の内容をもとに、成果を出せない人たちへの対応について紹介する。(構成:神代裕子)

【マンガ】1万人を接客した美容部員が教える「日焼け止め」の塗り方、目からウロコのコツ[見逃し配信・5月第3週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![【マンガ】1万人を接客した美容部員が教える「日焼け止め」の塗り方、目からウロコのコツ[見逃し配信・5月第3週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/6/6/360wm/img_2ff6880cb6225f0ef5513ac7103075ef276349.jpg)
「ありがた迷惑」と「親切な気づかい」の境界線はどこか?…プロが教える“たった1つの判断基準”
さりげなく、「ちょうど良い気づかい」のできる人にはあこがれる。しかし、「ちょうど良い気づかい」の塩梅が難しいと思ったことはないだろうか。相手のためを思ってやったことでも、「余計なおせっかい」になることもある。そんな不安を持つ人にぜひ読んでもらいたいのが『気づかいの壁』だ。これまでおよそ200社、2万人のビジネスパーソンに向けてコミュニケーションスキル等の研修やセミナーを行ってきた著者、川原礼子氏は、サービスのプロではない一般のビジネスパーソンに向けて「ちょうど良い気づかい」のコツを教えてくれている。本記事では、本書の内容をもとに、「迷惑かもしれないし」と迷ってしまって行動できない人が「気づかいできる人」になることができる考え方について紹介する。(構成:小川晶子)

【どんな言葉が欲しいの?】「重い相談」をされたとき…「やってはいけないこと」と「やるべきこと」
機嫌がいい人は「ドライでいい」と知っている──。そう語るのは、70歳のプロダクトデザイナー・秋田道夫さんです。誰もが街中でみかけるLED式薄型信号機や、交通系ICカードのチャージ機、虎ノ門ヒルズのセキュリティーゲートなどの公共機器をデザインしてきた秋田さんは、人生を豊かに生きるためには、「機嫌よくいること」「情緒が安定していること」が欠かせないと語ります。そんな秋田さんの「まわりに左右されないシンプルな考え方」をまとめた書籍『機嫌のデザイン』は、発売直後に重版と話題を呼び、「いつも他人と比べてしまう」「このままでいいのか、と焦る」「いつまでたっても自信が持てない」など、仕事や人生に悩む読者から、多くの反響を呼んでいます。悩んでしまった時、どう考えればいいのでしょうか。本連載では、そんな本書から、「毎日を機嫌よく生きるためのヒント」を学びます。今回のテーマは、「小さな失敗に落ち込みすぎないための心の保ち方」についてです。(構成:川代紗生)

優れたリーダーがやっている「当事者意識のない若手社員」を劇的に変える方法
経営に関わるポジションにいると、その他の社員との温度差を感じることがある。もっとしっかり会社のこと、経営のことを考えてほしいという願いから、社員に「経営者目線をもってほしい」と思う人もいるのではないだろうか。しかし、東北楽天ゴールデンイーグルス社長として「日本一」と「収益拡大」を達成し、現在は、宮城県塩釜市の廻鮮寿司「塩釜港」の社長にして、日本企業成長支援ファンド「PROSPER」の代表として活躍中の立花陽三氏は、初著書である『リーダーは偉くない。』の中で「社員に『経営者目線』を求めるのは“甘え”である」と語る。立花氏の真意はどういったものなのか。本記事では本書の内容をもとに、核心に迫る。(構成:神代裕子)

「体にいいサプリメント」は2つだけ!? エビデンスを徹底検証![見逃し配信スペシャル]
書籍オンライン編集部が厳選した「編集部セレクション」記事より、読者の反響が大きかった「注目記事BEST5」をご紹介します。
![「体にいいサプリメント」は2つだけ!? エビデンスを徹底検証![見逃し配信スペシャル]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/7/360wm/img_173720514b576edca3a4573a06d1a781181790.jpg)
【一発アウト】税務署が激怒する行為、ワースト1[見逃し配信・5月第2週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![【一発アウト】税務署が激怒する行為、ワースト1[見逃し配信・5月第2週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/e/360wm/img_ae42d7f4dc50eb70f24b0c8641ffa96a241528.jpg)
【運がいい人の習慣】チャンスを引き寄せる「ちょっとした気づかい」のコツ・ベスト5
同じように才能があっても、チャンスをつかんで成功し続ける人とそうでない人がいる。その差は、「気づかい」にあるのかもしれない。話題のロングセラー『気づかいの壁』の中には、「気づかいの差」が「人生の差」を生むという話がある。一つひとつは小さなことだが、積み重ねることで大きな差が生まれるのは間違いないだろう。これまでおよそ200社、2万人のビジネスパーソンに向けてコミュニケーションスキル等の研修やセミナーを行ってきた著者、川原礼子氏は、サービスのプロではない一般のビジネスパーソンに向けて「ちょうど良い気づかい」のコツを教えてくれている。本記事では、本書の内容から、なぜかチャンスをつかむ人がやっている気づかいのコツについて、5つピックアップして紹介する。(構成:小川晶子)

いつも「情緒が安定している人」が知っている「感情的にならない」ための“生き方のコツ”とは?
機嫌がいい人は「ドライでいい」と知っている──。そう語るのは、70歳のプロダクトデザイナー・秋田道夫さんです。誰もが街中でみかけるLED式薄型信号機や、交通系ICカードのチャージ機、虎ノ門ヒルズのセキュリティーゲートなどの公共機器をデザインしてきた秋田さんは、人生を豊かに生きるためには、「機嫌よくいること」「情緒が安定していること」が欠かせないと語ります。そんな秋田さんの「まわりに左右されないシンプルな考え方」をまとめた書籍『機嫌のデザイン』は、発売直後に重版と話題を呼び、「いつも他人と比べてしまう」「このままでいいのか、と焦る」「いつまでたっても自信が持てない」など、仕事や人生に悩む読者から、多くの反響を呼んでいます。悩んでしまった時、どう考えればいいのでしょうか。本連載では、そんな本書から、「毎日を機嫌よく生きるためのヒント」を学びます。今回のテーマは、「小さな失敗に落ち込みすぎないための心の保ち方」についてです。(構成:川代紗生)

金利が上がっても、住宅ローンは「変動」で/宇宙誕生から現代まで「全歴史」を早回し ほかダイヤモンド社5月の新刊案内
今月、ダイヤモンド社書籍編集局から刊行される書籍をご紹介します。
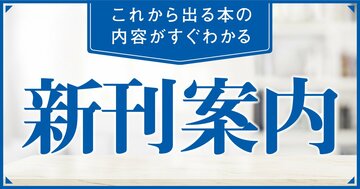
【思考力チェック!】AはBを見ている。BはCを見ている。Aは結婚していて、Cは独身である。このとき…[見逃し配信・5月第1週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![【思考力チェック!】AはBを見ている。BはCを見ている。Aは結婚していて、Cは独身である。このとき…[見逃し配信・5月第1週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/4/360wm/img_d425cca25a75b5be84944bbde615cae2167732.jpg)
「新NISAでインデックス投資」を選んだ投資家が絶対に知っておきたいこと
日経平均株価がとうとうバブル後の最高値を突破し、株式投資が大きく注目されている。個人投資家のための税制優遇制度も新たになり、株式投資を始めようと考えている人、またさらに拡大させたいという人も少なくないのではないか。だが、間違った知識で投資をすることは危険。それを教えてくれる1冊が『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』(奥野一成著)だ。社会人の教養として投資リテラシーは必須だと語る、その意味とは?(文/上阪徹)

天ぷらを食べるとき、育ちがいい人がしないこと[見逃し配信・4月第4週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![天ぷらを食べるとき、育ちがいい人がしないこと[見逃し配信・4月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/5/360wm/img_b532dbefaea96ee32981e422af21beb0417238.jpg)
大人の脳トレ本としても大人気! 2023年『小学生がたった1日で19×19まで暗算できる本』で自己肯定感まで上がるのはなぜか?
2023年、学習参考書として史上初めて年間ベストセラー第1位となった書籍『小学生がたった1日で19×19まで暗算できる本』。子どもだけでなく、高齢者まで幅広い支持を受けて、暗算ブームの火付け役にもなりました。なぜここまで読者が広がったのか、この本の魅力を担当編集のダイヤモンド社・吉田瑞希さんに聞きました。
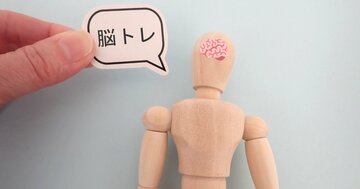
欧米人のように日本人が投資をしてこなかった歴史的な理由
日経平均株価がとうとうバブル後の最高値を突破し、株式投資が大きく注目されている。個人投資家のための税制優遇制度も新たになり、株式投資を始めようと考えている人、またさらに拡大させたいという人も少なくないのではないか。だが、間違った知識で投資をすることは危険。それを教えてくれる1冊が『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』(奥野一成著)だ。社会人の教養として投資リテラシーは必須だと語る、その意味とは?(文/上阪徹)

お寿司にしょう油をつけるとき、育ちがいい人はしないこと[見逃し配信・4月第3週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![お寿司にしょう油をつけるとき、育ちがいい人はしないこと[見逃し配信・4月第3週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/0/360wm/img_161c10631e6c96e1b5ed923f3bdd3c1f244102.jpg)