書籍オンライン編集部
会議で「自分の意見が通らなかった人」に結果を出すリーダーがかけてあげる言葉
会議で何かを決める際、出た案がどれも素晴らしくても、1つに決めなければならないことはよくある。そういった場合、自分の意見が選ばれなかった人が非協力的にならないようにする必要がある。『一流ファシリテーターの 空気を変えるすごいひと言――打ち合わせ、会議、面談、勉強会、雑談でも使える43のフレーズ』の著者で、3万人に「人と話すとき」の対話術を指導してきた人気ファシリテーション塾塾長・中島崇学氏は「わかっていますよサイン」をまめに出す必要があると語る。それは一体どのようなものか。本記事では本書の内容をもとに解説していく。(構成:神代裕子)

「生命科学本の中で過去最高」…圧倒的な知性が書いた震えるほどの名著[見逃し配信スペシャル]
書籍オンライン編集部が厳選した「編集部セレクション」記事より、読者の反響が大きかった「注目記事BEST5」をご紹介します。
![「生命科学本の中で過去最高」…圧倒的な知性が書いた震えるほどの名著[見逃し配信スペシャル]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/7/360wm/img_d7d525450dbb8ff6ebe9060d0bd8a5d2129895.jpg)
「投資で豊かになれる人」と「投資をしているのに豊かでない人」の決定的な違いとは?
日経平均株価がとうとうバブル後の最高値を突破し、株式投資が大きく注目されている。個人投資家のための税制優遇制度も新たになり、株式投資を始めようと考えている人、またさらに拡大させたいという人も少なくないのではないか。だが、間違った知識で投資をすることは危険。それを教えてくれる1冊が『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』(奥野一成著)だ。社会人の教養として投資リテラシーは必須だと語る、その意味とは?(文/上阪徹)

「今度、ごはん行こうよ」という時、育ちがいい人なら言わないこと[見逃し配信・4月第2週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![「今度、ごはん行こうよ」という時、育ちがいい人なら言わないこと[見逃し配信・4月第2週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/5/b/360wm/img_f6c59c126c70291cfb5a8e3af27e43ee305957.jpg)
【すぐ逃げて】身近にいる「相手をコントロールする人」の1つの特徴
AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「疲弊するばかりで報われない人間関係の特徴」だ。(構成:川代紗生)

会議で「意見が分かれたとき」の管理職のヤバい発言ワースト・1
会議ではお互い真剣だからこそ、主張が異なる者同士でケンカ腰になってしまうことがある。イチ参加者であればしばらく様子を見ていればいいかもしれないが、自分がファシリテーターだったとしたら、傍観しているわけにもいかない。『一流ファシリテーターの 空気を変えるすごいひと言――打ち合わせ、会議、面談、勉強会、雑談でも使える43のフレーズ』の著者で、3万人に「人と話すとき」の対話術を指導してきた人気ファシリテーション塾塾長・中島崇学氏はそんな「荒れた空気を変えるひと言がある」という。それは一体どのようなものか。本記事では本書の内容をもとに解説していく。(構成:神代裕子)

株のプロだけが知っている「投資で成功するために必要なこと」
日経平均株価がとうとうバブル後の最高値を突破し、株式投資が大きく注目されている。個人投資家のための税制優遇制度も新たになり、株式投資を始めようと考えている人、またさらに拡大させたいという人も少なくないのではないか。だが、間違った知識で投資をすることは危険。それを教えてくれる1冊が『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』(奥野一成著)だ。社会人の教養として投資リテラシーは必須だと語る、その意味とは?(文/上阪徹)

クレーム対応で「上の人を出せ!」と言われたとき、「感じのいい人」はとっさに何と言い返す?[見逃し配信・4月第1週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![クレーム対応で「上の人を出せ!」と言われたとき、「感じのいい人」はとっさに何と言い返す?[見逃し配信・4月第1週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/1/360wm/img_c408de9ee6eb53a17af973770dfab532284421.jpg)
相手にしてはいけない「他人を消耗させる人」の特徴
AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「善意が人を不快にするケース」についてだ。(構成:川代紗生)

「求心力のあるリーダー」になるには?…欠かせない「自己管理」3つのチェックポイント
部下にとって「機嫌の悪い上司」ほどめんどくさい存在はない。どんなに仕事ができる人でも、それだけでリーダーとしての資質に疑問符がつく。それほどまでに「機嫌のよさ」は大事なのだ。では、どうしたら「自分の機嫌」をコントロールできるのか。『Deep Skill ディープ・スキル』では、機嫌をマネジメントする方法として「3つのポイント」を紹介している。リーダーやマネジャーならぜひとも意識したい「3つのポイント」。どれもシンプルで、すぐに実践可能なので、ぜひこの3つを理解して「自分の機嫌」のマネジメント力をアップさせたいところ。それだけで、リーダーとしての質は一段も二段も上がるだろう。(構成:イイダテツヤ)

仕事が捗る「職場でのセルフブランディング」…3つの「得する人物像」とは?
ファシリテーターに向いている人はどんな人だろう。 おそらく、「この人とは本当に話しやすい」と思ってもらえる人だ。『一流ファシリテーターの 空気を変えるすごいひと言――打ち合わせ、会議、面談、勉強会、雑談でも使える43のフレーズ』の著者で、3万人に「人と話すとき」の対話術を指導してきた人気ファシリテーション塾塾長・中島崇学氏は、話しやすい人と思ってもらうポイントとして「好感をもってもらう」「頭がいいと思ってもらう」「味方だと思ってもらう」の3つをあげる。本記事では、会議を進めやすくするために、参加者から「認めてもらえる言葉」を紹介する。(構成:神代裕子)

限りある時間とどう向き合うか/本当に家を買っても大丈夫? ほかダイヤモンド社4月の新刊案内
今月、ダイヤモンド社書籍編集局から刊行される書籍をご紹介します。
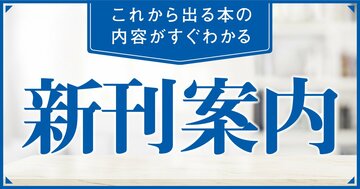
【いますぐ逃げて】近くにいると運気が下がる人の特徴、ワースト3[見逃し配信・3月第5週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![【いますぐ逃げて】近くにいると運気が下がる人の特徴、ワースト3[見逃し配信・3月第5週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/2/360wm/img_f24270f8d111551e22fedbf4a9f41ecf154940.jpg)
【ガミガミねちねち】うるさい「高圧的な相手」への賢い対応・ベスト1
AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「高圧的な上司の言葉に心が折れそうになったら?」だ。(構成:川代紗生)

何を聞けばいい?…「仕事ができる人」が人の話を聞くときに質問すること
「どうしてこの部下は指示を理解してくれないんだろう…」「なんで、そんなワケわからないことをやってしまうんだ…」と日々頭を抱えるリーダーは多いだろう。しかし、部下は部下で「言ってることがよくわからない…」「指示があいまいなくせに、後でも文句を言ってくる…」と思っている。なぜ、そんなことが起こるのか? 端的に言えば、言語化力が足りないのだ。上司はもちろん、部下の側の言語化力の問題もある。『Deep Skill ディープ・スキル』ではこうしたビジネスシーンで起こりがちな「言語化問題」について、ゴルフの「フェアウェイ」「ラフ」「OB」を用いたコミュニケーションを提案している。自分自身の言語化力を向上させたい人はもちろん、周囲の言語化力不足に悩まされている人にもぜひお勧めしたいコミュニケーション術だ。(構成:イイダテツヤ)

キャリアの専門家が語る「企業が本当に欲しい人の条件」とは?
本当にこの仕事を続けていて、自分は幸せになれるのか。そんなふうに感じている人は、実は少なくない。その一方で、天職を見つけた多くの人が、実は偶然にその仕事と出会っていたことを知る人も少ない。その偶然を起こすために、できることがある。そう唱える一冊が、計画的偶発性理論(プランドハプンスタンス理論)で著名なJ・D・クランボルツなどが著した『その幸運は偶然ではないんです! 夢の仕事をつかむ心の練習問題』だ。必要なのは、キャリアプランなどではなく、ほんの少しの勇気。さて、人生を変える方法とは?(文/上阪徹)

認知症になりやすい人のヤバい生活習慣[見逃し配信・3月第4週]
先週(金~木)の「書籍オンライン」で、特に読者の反響が大きかった「人気記事BEST5」をご紹介します。
![認知症になりやすい人のヤバい生活習慣[見逃し配信・3月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/e/3/360wm/img_e320f85dfb0705a753a2ef4bd9d158cf240561.jpg)
「本当に頭のいい人」と「知識を詰め込んでいるだけの人」の決定的な1つの違い
偏差値35から東大合格を果たした、現役東大生の西岡壱誠さんの著書『「思考」が整う東大ノート。』が話題だ。2浪しながらも成績がなかなか上がらず、崖っぷちに立たされていた西岡さんは、頭がいい人の「ノートやメモの取り方」には共通点があり、それを真似することで、誰でも質のいいインプットやアウトプットができるようになると気がついたという。勉強法を見直し、ノートの使い方をガラッと変えた結果ぐんと成績が伸び、見事合格することができた。この経験から西岡さんは、「東大生は、誰もがずば抜けた記憶力を持つわけではない。思考を整理するのがうまい人が多いのだ」と気がついた。その後、1000人以上の東大生のノートを分析し、その結果をまとめたのが『「思考」が整う東大ノート。』だ。本連載では、そんな本書から、仕事にも勉強にも役立つ、「見返さない」のに頭に入るノートの作り方を学ぶ。今回のテーマは、「丸暗記に頼らない記憶術」だ。(構成:川代紗生)

社内で「自分の味方を増やすのがうまい人」が知っていること
「優れたアイデアマン」や「組織で改革や改善を推進していく人」には共通するコミュニケーション法がある。何だかわかるだろうか? それは「すぐに人に話して、どう思う?」と聞きまくることだ。きっとあなたの組織にもそんなタイプの人がいるだろう。このコミュニケーション手法は”壁打ち”と表現されたりする。話題のベストセラー『Deep Skill ディープ・スキル』では、この”壁打ち”の価値や効果が詳しく説明されている。なぜ、優秀な人ほどすぐに”壁打ち”をするのか。ここではその理由と隠れた効果について紹介する。これを知れば、きっとあなたも「壁打ちをやってみたい」という気持ちになるはずだ。(構成:イイダテツヤ)

「自分を傷つけた人」への“復讐心”がずっと消えない精神状態の深いワケ
AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで、東京大学准教授の斎藤幸平氏が「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「自分を傷つけた人に執着してしまう理由」についてだ。(構成:川代紗生)
