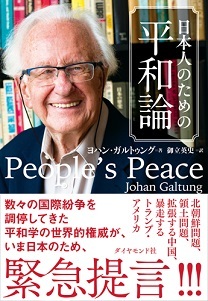好戦的国家アメリカ
米国が初めて他国に軍事介入したのは1801年(ジェファーソン大統領時代)。以来、米国は今日までに248件の軍事介入を行っている。第二次世界大戦以後に限っても、37ヵ国で2000万人以上を殺害している。世界史的に見ても突出した好戦性を有する米国には、今日の世界に蔓延する暴力と憎悪に大きな責任がある。米国の好戦性の表れとして、ガルトゥングは政権中枢の人物の発言に言及する。
ほとんどのイスラムの人々は、9・11の数日後、米国のウェズリー・クラーク元NATO最高司令官がインタビューに答えて言った有名な言葉を忘れていない。彼は米国政府の計画についてこのように述べた。「私たちは5年のうちに、7つの国を取り除く。まずイラク、そしてシリア、レバノン、リビア、ソマリア、スーダン、そして仕上げはイランだ」。
気に入らない国を取り除こうとする国──それが多くのイスラム教徒が持っている米国観なのである。(p.26-27)
日本の対米従属
日本は戦後70年以上経ったいまも、そのような好戦的国家の支配下にある。日本の政治家たちは、六本木ヘリポート(米軍用地内の赤坂プレスセンター)に降り立つ米国の軍や政府の関係者の顔色をうかがい、ワシントンの意向を忖度しながら政治を行っている。ガルトゥングは、日本には東アジアの安定のために成し得る貢献や外交政策があるのに、それができないのは対米従属に理由があると指摘する。
日本以外の主要国で、他国の軍人や外交官がこれほど簡単に首都中枢に出入りすることを許している国は世界広しといえど他には存在しない。この光景は、いまも日本が米国の占領下にあることを象徴している。(p.16)
行為の不可逆性
『日本人の平和論』は「行為の不可逆性」についての議論から始まる。どんなに正しいと思えることでも、後から間違いだったと気づくことがある。だから、何かを行うときは、行為の結果を元に戻せるかどうかが重要な判断基準となる。
人間は間違うことがあるという事実から、何をすべきか、何をすべきではないかということについての大原則が導かれる──行動するときは、その結果生じる状態を行動する前の状態に戻せるような行動を選ばなくてはならない、ということだ。修復が可能な行動を選べ、なぜならそれは間違っているかもしれないのだから、ということである。(p.13)
集団的自衛権の行使がもたらすもの
「行為の不可逆性」という観点から、ガルトゥングが最も強い危機感を抱いているのが、米国の戦争への協力姿勢を鮮明にしつつある日本に何が起こるか、ということである。
殺された側の怒りや悲しみは、必ず反撃や復讐の暴力となって米国とその同盟国に襲いかかる。それは無視することも、避けることも、退けることもできない。それがいま欧米の各地を襲っているテロの本質である。
さいわい、日本はまだあからさまな憎悪や復讐の対象にはなっておらず、日本国内ではそのようなテロは起こっていない。イスラムの人々は、日本は過去、米国と軍事行動をともにしたことがないことを知っており、それが日本に幸いしていると考えて間違いない。しかし今後、米国に付き従っていく現在の姿勢が続くなら、米国が世界で行っている間違った行動のツケが日本にも回ってくる。(p.17)
テロと国家テロ
テロリズムとは、政治的目標を達成するための暴力をともなう戦術である。政治的手段としての暴力には、(1)戦争、(2)ゲリラ戦、(3)国家テロリズム、(4)テロリズムの4つがある。
戦争は、軍服を着た兵士が、別の軍服を着た兵士と戦うことである。軍服を着用することで兵士に敵を殺す資格が与えられる。ゲリラ戦は、軍服を着用しない兵士が軍服を着用した兵士と戦うことである。国家テロリズムは通常、軍服を着た高官が軍服を着ていない民間人の上に爆弾を落とすことである。そしてテロリズムは、民間人が民間人を攻撃することである。形は違うが、すべてに共通するのは、政治目的のために暴力を使うという点だ。
私はこれら4つの暴力的手段のいずれにも賛成しないが、テロの悪ばかりを言い立てて国家テロに言及しない人々には苛立ちを覚える。いずれも無防備な民間人を標的にしている点で、テロも国家テロも違いはない。(p.178)
国際社会はテロの原因を取り除こうとせず、力で抑え込み、排除しようとしている。しかしそんなことが不可能なのは明らかである。
私が苛立ちを覚えるのは、どの国もさまざまなテロ対策を講じるのに、なぜか根底にある原因を取り除こうとしないことだ。すでに述べたように、暴力の根底にはトラウマと対立がある。私たちは何がトラウマとなっているのかを見極め、対立の原因を知る努力をする必要がある。そのためには、もしかしたら将来テロリストを輩出するかもしれない集団とも腹を割って対話し、彼らと敵対している自分たちの立場を自問することも必要である。(p.184)

1930 年、オスロ生まれ。社会学者。紛争調停人。多くの国際紛争の現場で問題解決のために働くとともに、諸学を総合した平和研究を推進した。長年にわたる貢献により「平和学の父」と呼ばれる。「積極的平和」「構造的暴力」の概念の提唱者としても知られる。自身が創設したトランセンドの代表として、平和の文化を築くために精力的に活動している。創立や創刊に関わった機関に、オスロ平和研究所(PRIO)(1959)、平和研究ジャーナル(Journal of Peace Research)(1964)、トランセンド(1993)、トランセンド平和大学(TPU)(2004)、トランセンド平和大学出版局(2008)がある。委員あるいはアドバイザーとして、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)、国連児童基金(UNICEF)、国連教育科学文化機関(UNESCO)、世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)、国連食糧農業機関(FAO)などの国連機関で、また欧州連合(EU)、経済協力開発機(OECD)、欧州評議会、北欧理事会などでも重要な役割を果たした。教育面では多くの大学で学生を指導した。客員教授として訪れた大学は世界各国で60近いが、そのなかには日本の国際基督教大学、中央大学、創価大学、立命館大学も含まれる。名誉博士、名誉教授の称号は14を数える。平和や人権の分野で、ライト・ライブリフッド賞(“もうひとつのノーベル賞”、ノルウェー・ヒューマニスト賞、ソクラテス賞(ストックホルム)、ノルウェー文学賞、DMZ(非武装地帯)平和賞(韓国)、ガンジー・キング・コミュニティ・ビルダー賞(米国)など 30 以上の賞を受賞している。 写真/榊智朗