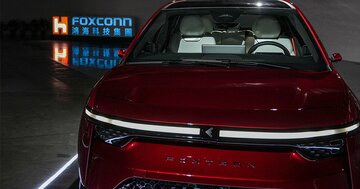1950年代以降、わが国では、企業ごとに組織されている労働組合が、春に時期を合わせて、一斉に企業との賃金引上げ交渉を行う慣行になっている。これが春季賃上げ闘争=春闘だ。90年代初頭にバブルが崩壊した後、企業業績の低迷が続いたことや、経済のグローバル化などの影響によって、労働組合が雇用の維持を優先する方針を取り始めたこともあり、一時期は「春闘は死語になりつつある」といわれた時期もあった。最近、企業収益が回復したこともあり、労働組合側も賃金引上げを要求するスタンスに戻りつつある。
かつての春闘は
労使が激しく対立した
かつて、わが国経済が高成長していた時期には、給与のベースアップ(通称ベア)やボーナスの増額、待遇の改善を要求する労働者側と、人件費負担の増加を抑えたい経営者側がかなり、ギリギリの交渉を行うことが多かった。昔、春闘の時期になると、労働側の代表者と経営側の代表者が、徹夜で団体交渉=団交を行ったという記事をよく見かけた。徹夜の交渉の結果、最終的に労働者―経営者の双方が合意に至らず、労働組合側が労働者の権利であるストライキに入ることもあった。当時の労使双方の対立関係は、かなり厳しかったといえるだろう。
そうした労使関係の背景には、当時のわが国の労働市場の事情があった。戦後、わが国は20世紀の奇跡と呼ばれる高い経済成長を達成した時期があった。今となっては懐かしい昔話だが、1960年代から70年代まで、本格的な工業化の段階に差し掛かっており、現在の中国のような高い経済成長を謳歌していたのである。その時期、最も重要な生産要素の一つは労働力だ。企業が成長するために最も重要なことは、必要な労働力を確保することであった。地方で教育を終えた若年層は、集団就職によって、都市圏の企業に有効な労働力として吸収されることが一般的だった。
企業が労働力を確保するためには高い給与を払うことが必要だが、その一方、あまりに人件費負担が増大することは、企業収益を阻害することも懸念される。必然的に、均衡点を見つけ出すプロセスが必要になる。それが、労働者側と経営者側の丁々発止の交渉ということになる。そうした事情を反映して、昔の労使双方には一定の対立関係が成立していた。また春闘というプロセスを通して、労働者も経営者も、世間一般の給与引き上げの相場を値踏みすることが必要だった。