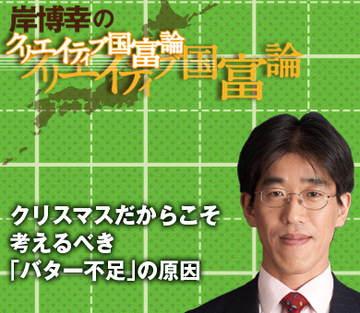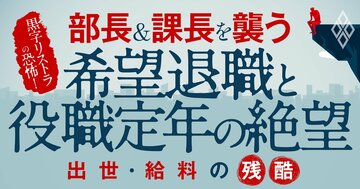米国では、家計部門の債務調整がなかなか進まない上に、財政支出も削減される中、金融業界の金持ちを攻撃するデモ(“Occupy Wall Street”)が盛り上がったように、1929年の世界恐慌以来久々に「格差」を巡る議論が盛んになっています。その議論から、日本は何を学ぶべきでしょうか。
米国での格差議論
米国では貧富の格差が拡大していることを示すデータが次々と明らかになっています。例えば、1980年と現在を比較すると、国民所得の5%、すなわち6500億ドルが中流階級から約6000世帯の最富裕層にシフトしたそうです。
また、2010年の米国の家計所得の中位値は4万9445ドル(約386万円)と、1997年とほぼ同じ水準になり、4900万人もの人が貧困ラインである年収2万4343ドル(約190万円)以下の生活をし、5100万人が“near poor”(所得が貧困ラインの50%増<3万6515ドル:約285万円>以下の水準)に位置しています。即ち、米国の人口3億人のうち1億人が、年収285万円以下という低所得に喘いでいるのです。
このように貧富の格差が拡大する中、社会正義の観点のみならず、経済への影響という観点からも、格差の拡大を懸念する声が大きくなっています。かつては経済学者の多くが、成長と社会的平等のどちらか一方の実現に力点を置いていましたが、成長と社会的平等は密接にリンクしているという考えが台頭しつつあるのです。
これは、今や労働力の質が経済の繁栄のために重要であり、それが国の教育水準に左右されることから、格差が小さい社会ほど、国民の多くが十分な教育を受けられるので、成長のために望ましいという考え方に基づいています。