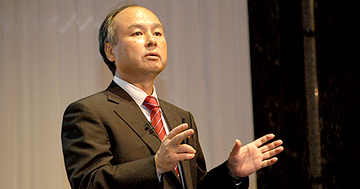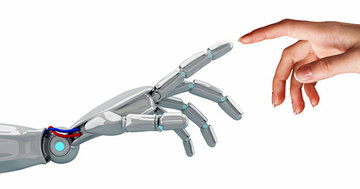ルンバやドローン、そしてpepper、再発売されたaibo。これらはすべてロボットです。AIの発達とともに、現在、注目されているロボティクス。工業分野だけでなく、サービスや介護、エンターテインメント、そして家庭でも、AIを搭載したロボットが登場しており、これらを使いこなし、そして新しいビジネスに結び付けることが期待されています。
今回は、ロボティクスの専門家である著者が、わかりやすく書いた新刊『ロボットーーそれは人類の敵か、味方か』の中から、エッセンスを抜粋して紹介します。
ロボットが今できることは、
レスキュー=救助ではない
「レスキューロボット」と聞くと、どんなものを思い浮かべるでしょうか?鉄人28号やガンダムのような人型ロボットが、瓦礫をどかして助けてくれる……。そんなイメージかもしれません。
ところが実際のレスキューロボットは、人型ではなく、まったく違う形をしています。
災害現場で実際に働くレスキューロボットに求められるのは、まず第一に「被災者を探すこと」。次に「現場に行く道をつくること」。最終的に「助けること」となります。
被災者の有無と位置を迅速に見つけ(探索作業)、救助のために必要な空間を確保、あるいは被災者が埋まっている場所まで到達し(掘削作業)、被災者を救助する(救助作業)。この3つの作業の中の、どれか一つでも担うロボットはレスキューロボットと呼ばれます。
レスキューロボットの
開発は95年以降にスタート
レスキューロボットの歴史は比較的新しく、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけとして開発がスタートしました。当初はこれら3つの作業を総合して行える自律的なロボットが想定されていました。
しかしこれまで見てきたように、ロボットができることは限られているため、想定していることとのギャップは大きなものでした。そのため、この3つの分野のどれかに目的を明確化した、単機能のロボットの開発が中心となっています。
また日本でも、海外に倣い、レスキューロボットのことを「サーチ&レスキューロボット(Search & Rescue Robot)」と表現する場合もあります。この呼び名の変化にも、「サーチ(探索)」という一番の目的を、よりはっきり示そうという意識が感じられます。
目的を明確化という意味では、新たな取り組みである「サイバー救助犬」もその流れの中にあります。犬型ロボットを一から開発するのではなく、犬がそもそも持っている機能を活かして、足りない部分をロボティクスの技術で補うという考え方です。
日本警察犬協会によると、犬が持つ嗅覚は人間の1億倍(犬の匂いに関する感度は臭気の種類によって変わる。例えば「酸臭」では1億倍、「ニンニク臭」では2000倍など)。それだけの嗅覚を持つロボットを開発するとしたら、これから先、何年かかるかわかりません。
それであれば、嗅覚や機動力は犬が本来持っている能力に任せ、視力、記録など犬では担えない部分をロボットが担当しようというのです。犬が装着するのは、カメラやGPSが搭載された軽量のロボットスーツ。人が踏み込めないような災害現場や狭い隙間などに入り込み、探査活動をします。救助隊員は、犬の見ている映像をカメラを通じて手元のタブレットで確認することができますから、例えば瓦礫の下など人が入れない場所であっても、被災者の状態やその周りの状況をリアルタイムで確認することができるのです。
生物の利用は、倫理的な問題と隣り合わせではありますが、生物とロボットという新たな展開の広がりが感じられるケースです。
日本ロボット学会理事、和歌山大学システム工学部システム工学科教授。1973年生まれ。東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻修了。2007年より千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科准教授(2013-14年、カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員)を経て現職。専門は知能機械学・機械システム(ロボティクス、メカトロニクス)、知能ロボティクス(知能ロボット、応用情報技術論)。2016年、スイスで第1回が行われた義手、義足などを使ったオリンピックである「サイバスロン2016」に「パワード車いす部門(Powered wheelchair)」で出場、世界4位。電気学会より第73回電気学術振興賞進歩賞(2017年)、在日ドイツ商工会議所よりGerman Innovation Award - Gottfried Wagener Prize(2017年)共著に『はじめてのメカトロニクス実践設計』(講談社)がある。