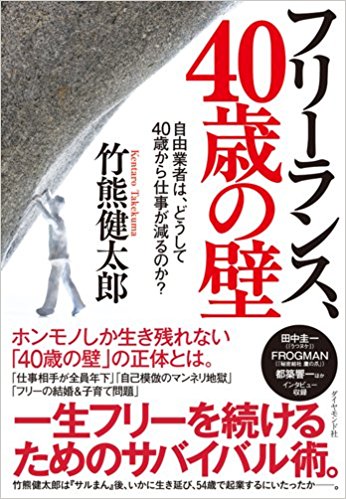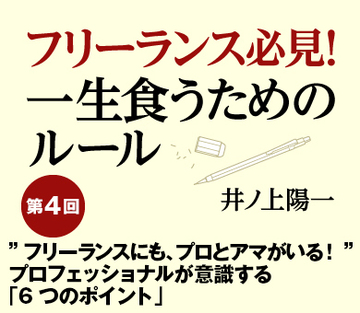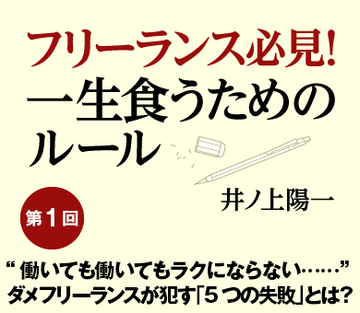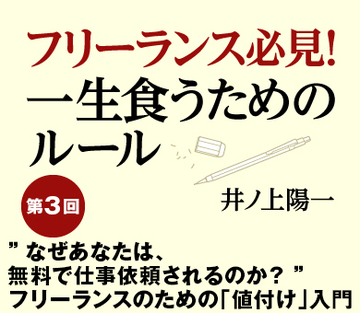アニメ研究者・評論家として氷川さんがユニークなのは、芸術家が作るアート・アニメではなく、大衆消費型のテレビアニメを真面目に批評の俎上に乗せたところだと思います。
長らくアニメーションにまつわる言説はアート・アニメが主流でした。評論家・研究者にとっては、最初から芸術として作られたそちらのほうが「語りやすかった」のです。テレビアニメは商業主義の産物で、アニメーション特有の「動き」や美術としての美しさよりもストーリーとキャラクターが主体で、大衆消費物として作られているぶん、「芸術」としては劣っているものとされ、長く真面目な批評の俎上に乗らなかったのです。
しかし「大衆消費物」として作られたものであっても、それなりの歴史の積み重ねがあり、技術の厚みも増して、これを語る言葉がないはずはありません。語られなかっただけなのです。マンガやテレビアニメは、江戸時代の浮世絵に比することができます。浮世絵は初めから「大衆消費物」として描かれ、これを芸術としてみる人はほとんどいませんでした。ヨーロッパ人が初めて浮世家を見た時、日本から輸入した陶器の保護紙としてくしゃくしゃに丸めて使われていたといいます。しかしそこに描かれた絵の美しさにヨーロッパ人は驚嘆したのでした。こうして浮世絵は立派な「芸術」として認知されることになりました。氷川竜介さんがやろうとしたのは、かつての浮世絵的な位置にあったテレビアニメを立派な表現物として同時代的な批評の対象にすることでした。
「このままだと消えてなくなる恐怖感があった。もうひとつ、歪んで伝わるのも嫌でした。『宇宙戦艦ヤマト』って、犯罪で捕まった人が作ったアニメでしょうとか、そんな風に伝わったら最悪だと。いやいや、『ヤマト』がなかったら“萌え”とか言われている現代のアニメ状況そのものがないんだよと。どんなものにも歴史があり、順序や階層があるので、的確に伝えたいと思うんです。」
もちろんアカデミックにアニメを語ろうという試みは1980年代からあったことはありました。しかし戦略的にうまくいってなかったと思う、と氷川さんは言います。
「僕だって小林秀雄的な評論は知っていますよ。」と、彼は言いました。作品を語る上で作品以外の夾雑物を入れてはいけないという、アカデミックに作品を扱ううえでのルールのことです。でもアニメや、ゲームにそれを当てはめるのは違うのではないか、という想いがあるのだと言います。
「文学は個人作業だけど、アニメのクリエイションは集団作業でしょう。それに「ビジネス」として大金で作られる宿命もある。純文学を語る上では夾雑物とされる事象も考慮しないと、アニメの真髄は語れないという想いもあります。」
会社を辞めた理由
長くセミプロとしてサラリーマン兼ライターとして二足のわらじを履いてきた氷川さんですが、2001年に18年弱勤めた会社を辞めます。先述のとおり、1997年に富野由悠季監督のアニメ『無敵超人ザンボット3』の長編評論『20年目のザンボット3』(太田出版)を上梓していました。氷川さんにとっては初の単著になりますが、これはいずれフリーになることを見越して書いたわけではなく、むしろ「会社を辞めない」ために書いたと言います。会社員と兼業でも本は書ける、ということを自分で証明するために書いたのだと。
それでもその4年後、彼は会社を辞めることにしました。
「最後の4年は課長をやっていて、それは最初の本を書いてからのことになります。課長として部下や外注さんとおつきあいをしていましたが、…(しばし無言)…まあ、要するに僕は向いていなかったということですね。管理職に。
でも、会社に不満はないですよ。世界の広さを見れたし。USBの携帯電話用標準のため、日本企業を代表する使命も果たしました。モバイル用3Gの標準化でも世界中を飛び回りましたしね。会社員としては充実していた方でしょう。でも、2000年に突然、「蛍の光」が聞こえてきたんです。頭の中で。
さすがに詳しくは話せませんが、所属部署の体制が急に大きく変わったんですね。もっと会社の業績に直結することをやらなければならない。僕のように変わった、はぐれ者をもはや許容しない圧力を急に感じるようになりました。
退社後、日本の電機系産業の多くは非難を浴びるようになりました。昔のものづくりの精神、クリエイティビティはどこに行ったんだと。でも、僕は風向きがそれ以前から変わってきたことを痛感していたんです。また、同僚や部下が鬱になったり突然死したことも大きかった。それも複数の方です。40代50代って意外と死ぬんだ、とも思いました。子どももいないし、2000年代以後、自分の変わった才能が活かされることのない気配を察しました。適材適所でいうと、自分はこの会社でもはや適材ではない、と思ったわけです。」
安定した職を辞めてフリーになる不安は、もちろんありました。氷川さんはフリーランスになるタイミングで、夫婦二人でどのくらいのお金が必要なのか、最低年収を現実的に計算したと言います。いろいろ調べて、年収480万円あればなんとかなると確信しました。その基準に対して自分の生産力を考え、一日でどのくらいの字数が書けるか、一文字はいくらになるか、を一通り計算してみたそうです。一週間のうち、どのくらいを営業に使えるかなども。
また、早いうちに原稿を書き留めておけば、それが資産や、パブリックなレファレンスになるとも考えました。氷川さんは過去に書いた原稿の一部をまとめてネットで無料公開し、毎年一冊から二冊、同人誌(ロトさんの本)を出しています。これも自分の仕事見本であり、資産だと言います。
「自分は“運がいい人”かもしれないかと、気づかされたことも大きいです。前に岡田さんに“オタク界のフォレスト・ガンプ”みたいだって言われたことがありました。ガンプはケネディ大統領が写っている写真の中になぜか居たり、歴史的に有名な場面にいつも居合わせている(笑)。僕自身もヤマトの制作現場に顔を出し、同時に円谷プロにも通った。ネットワークコミュニケーションの黎明期にはニフティに携わり、モバイルコンピューティングにも最初期から携わっていた。運よく開拓の瞬間に居合わせて後につながる変革を見ることが続いた。しかも、なぜか常に作り手に近い立場にいる受け手でもあったんですね。」
もちろん氷川さんにも、アニメの仕事は定年まで勤め上げてから始めてもよかったのではないか、という葛藤はありました。しかし物事にはタイミングというものがあります。氷川さんは、会社に残って苦手な管理職をやるよりも、人脈があり、自分に気力が残っている今のうちに、早くやるべきだ、という気がしていました。
案の定、氷川さんが会社を辞めるタイミングでDVDブームが起こり、角川書店が『ガンダムエース』を創刊し、氷川さんに仕事の流れが来ることになりました。庵野秀明監督の「ふしぎの海のナディア」DVD化に際しては、大きな仕事も担当し、そこから拡がったこともあったといいます。絶好のタイミングでフリーランスになれたのではないか、と彼は考えています。
それでも、フリーランスになってから、壁にぶつかった記憶はないのでしょうか?
「うーん。不遜かもしれませんが、会社にいた頃は、個人の力と意志だけで仕事ができないことが、とてもストレスに感じていたのでしょう。こんなの全部俺がやった方が早い、という感覚があった。組織の管理職でそれが禁句なのは承知の上ですが。フリーランスと会社員の最大の違いは、上下関係がなくフラットなことです。会社では部下は上の命令を実行するのがプレッシャーだし、上司は上司で、部下がうまくできないこと自体がストレスだったりします。でもフリーランスはお互いの領域に敬意をもち、自分で完結する。そこは非常に楽でした。ひとつの仕事を任され、お互いに前向きな提案をして、各自責任を持って仕事を全うする関係性が僕には合っていた。インターネットもそういう構造ですしね。インターネットにはニフティのような管理の中枢がない、並列処理型。会社のようにピラミッド型ではない働き方ですよね。」
(前編はここまで)
※取材は2015年5月に実施されたものです