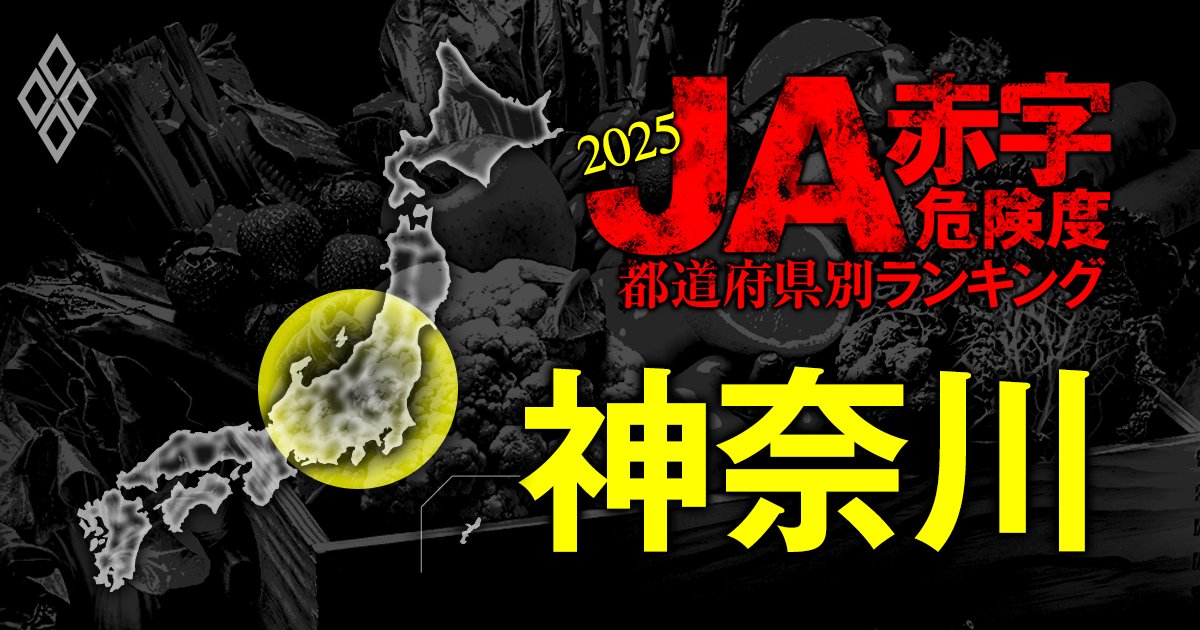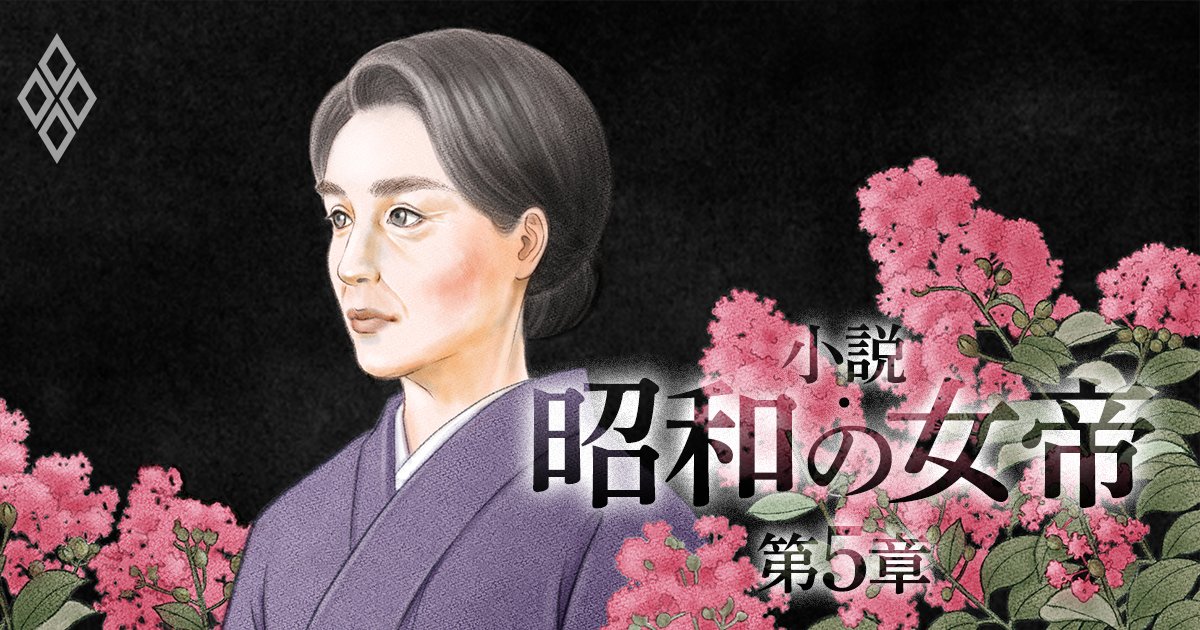江戸時代初期に、河村屋七兵衛(河村瑞賢)という商人がいた。新井白石をして、「天下に並ぶものがいない富商」と唸らせた男だ。明暦3(1657)年、明暦大火の材木買付で頭角を現したこの人物は、幕府から数々の大事業を命じられ、江戸という時代を縁の下から支えるインフラ構築事業に邁進していく。
しかし七兵衛の半生は決して平坦ではない。明暦大火で三男を、治水事業では跡取りの次男を事故で死なせてしまう。七兵衛自身も何度も死地を潜り抜け、河村屋の身代を傾かせたことも一度ならず。彼は“逆境”に立たされるたびに知恵を振り絞り並はずれた胆力で乗り切ってゆく……。
作家・伊東潤氏は『江戸を造った男』(朝日文庫)で、この河村瑞賢の波瀾万丈の生涯を描いている。2018年は、瑞賢の生誕400年となる節目の年。伊東氏が取り上げた河村瑞賢とは、いったいどんな人物だったのだろうか。
河村屋七兵衛(河村瑞賢)の名を知る人は多い。東北地方の米を江戸に廻米する航路――東回り航路・西回り航路の開拓者として、その名は多くの教科書にも掲載されている。航路開拓がなぜかくまでの功績として称揚されているのだろう。それは、前近代における道・路の開発は国土を広げることにも等しい大事業だったからだ。
七兵衛の生年とされる元和四(1618)年の3年前、大坂の陣の終焉とともに、全ての大名が徳川幕府に従属するところとなった。いわゆる元和偃武である。しかし、これだけでは今日私たちが考える意味での「江戸時代」が成立したとはいえない。各地の大名がその領国を支配し、諸大名が幕府に対し作事や軍役を提供するという間接統治は、支配の強弱に差こそあれ室町幕府や鎌倉幕府においても見られたシステムである。「中世」とは明確に異なる「近世」として江戸期の日本が語られるのは、同時期の日本が連邦国家から統一国家へと一歩踏み出したと認識されるためだ。