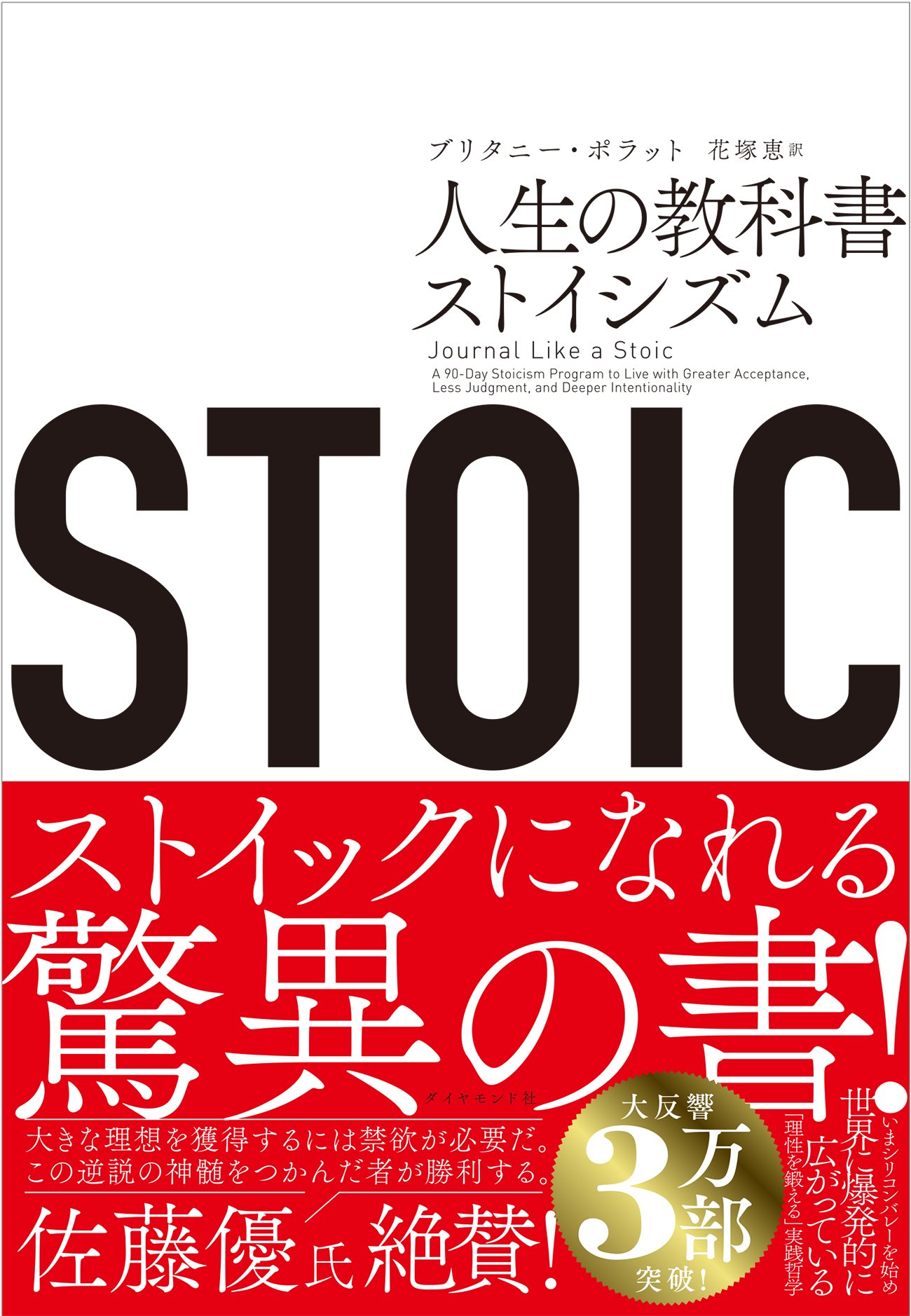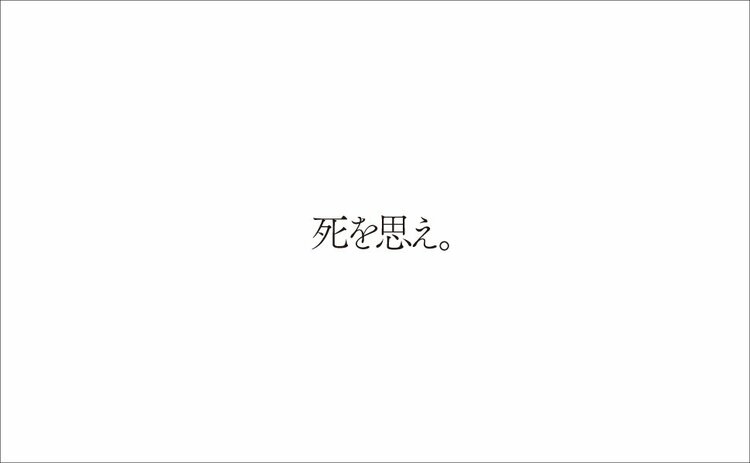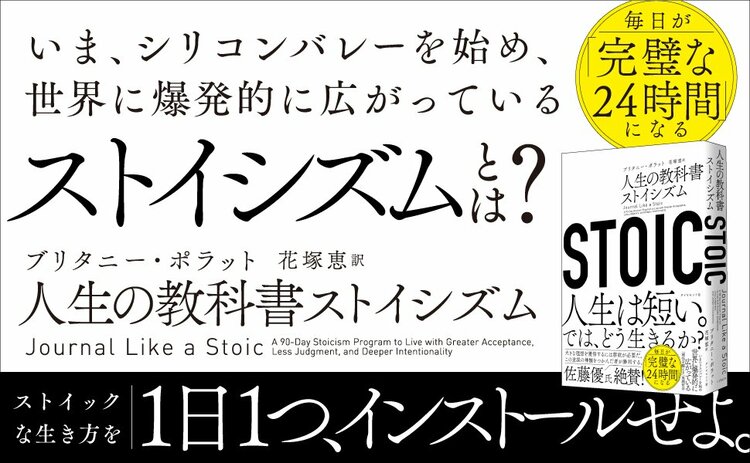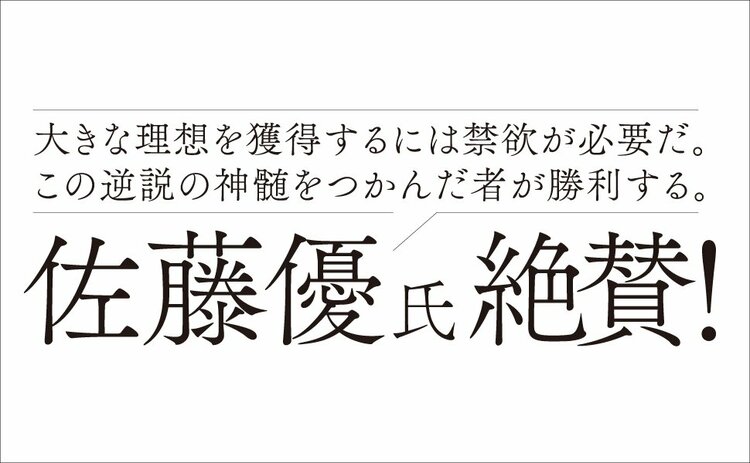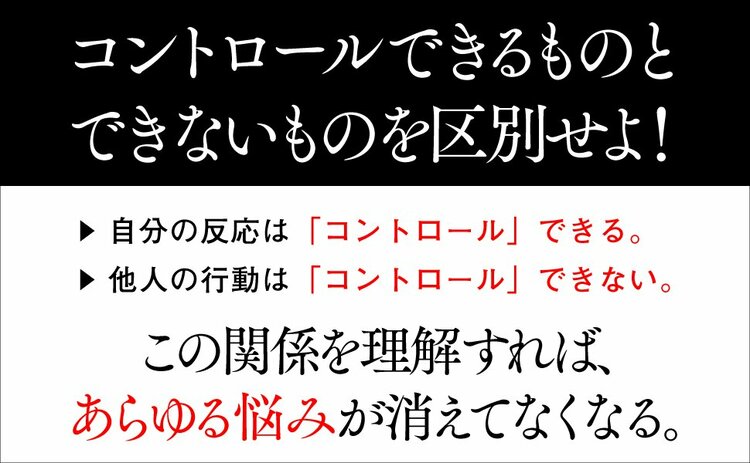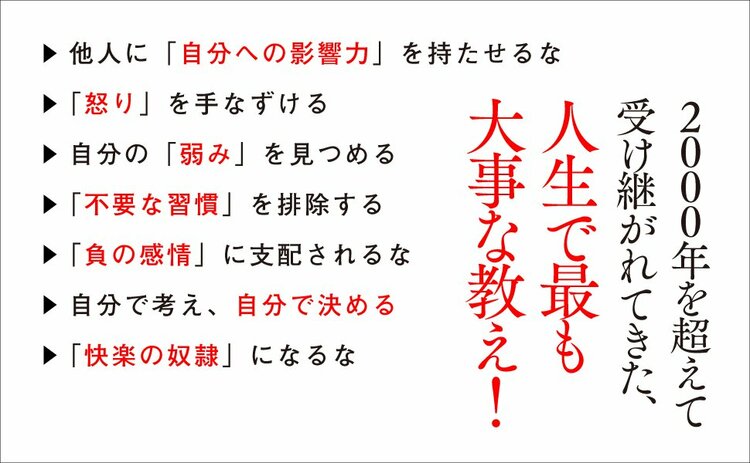いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
逆境を受け止める
木は揺らされるからこそ強くなり、しっかりと根を張るようになる。
風のさえぎられた谷で育った木はもろい。(セネカ『摂理について』)
――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より
無理な依頼があったらどうする?
ライターとしてそこそこの年数やってきた中では、逆境とも言える非常に厳しい条件のもとで行う仕事もあった。
明日までに1章分仕上げなきゃならないとか、事情により完全無報酬とか、とにかく怒っているクライアントのところへ取材に行ってほしいとか、ほとんど何も言っていない話を100倍に膨らませてほしいとか。
「無理です」
無理なのに、期待を持たせるような曖昧な返事をすると、相手にも迷惑がかかる。仕事ができる人ほど、無理なものは「無理」とはっきり伝える。
「文末指定」での奇妙な依頼
もっとも、難しいことはわかっていても、どうしてもやる必要のある仕事もある。
なかでも逆境だと感じ、逃げ出したいと思ったのは、文章についてやたらと禁止事項を設定されたときだった。たとえば文末の表現も、一定の表現しか使ってはいけないと指定されたのだ。これは私にとって非常に辛かった。
~である。
~なのだ。
~に違いない。
~という。
~だろう。
~ではないか。
こうした文末表現は、文章のリズムを作る。試しに、いま読んでいるこの文章の文末を全部変えることを想像してみてほしい。まったく違う印象のものになるはずだ。
私は文章を書くとき、自分の中にリズムがあって、それに合わせて書いているようなところがある。次はこのリズムだ、この文末になるはずだという感覚があるのだ。それをあらかじめ指定されてしまうと、書けない。
だから文末指定は本当に苦しかった。頭がおかしくなりそうだった。そもそも、指定する意味も私には理解できなかった。
しかし、オーダーに合わせて仕上げなくてはならない。自分のリズムを殺して、書いた。「逃げてしまおうかな?」そんな考えが何度も頭をよぎったが、書ききった。その結果、なんとかOKをもらうことができた。
もうこの条件で書くことはない。だが、私はこの経験によって「リズムで書く」だけではなく、文末の意図をものすごく考えるようになった。「この文末じゃないとダメなんです」と言えるように、しっかり考えて選択することが増えた。
おかげで文章力が上がったと思う。良い勉強をさせてもらった。
難しい仕事は自分を強くする
これらの経験を乗り越えてきたことは、自信につながっていると思う。多少の難しい案件にはひるまなくなっている。
哲学者セネカが言うように、木は風が吹きつけて揺らされるからこそ、たくましく育つのだろう。そう考えると、逆境ともいえる厳しい条件での仕事は、自分を強くするチャンスだ。大歓迎とは言わないまでも、見方が少し変わるかもしれない。
ただし、難しい仕事と、本当に無理な仕事は違う。「無理なものは無理」と言うのも忘れずに。
(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)