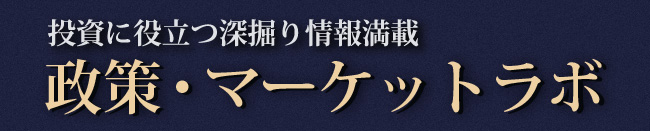物議を醸す業種別・全国一律の最低賃金案。一見無関係に思える欧州債務危機の教訓とは?Photo:AFLO
物議を醸す業種別・全国一律の最低賃金案。一見無関係に思える欧州債務危機の教訓とは?Photo:AFLO
厚生労働省の幹部が3月7日の自民党議員連盟会合で業種別に全国一律の最低賃金を導入する考えに言及したことが大きく報じられている。この点、菅義偉官房長官が同日の記者会見で「現時点で厚生労働省として具体的な検討や調整はしていない」と発言しているため、政府・与党として容認している案ではなさそうだ。
8日付の日本経済新聞も「課長が個人的な意見を説明しただけで具体的な議論は進めていない」と厚労省が火消しの情報発信に努めていることを報じている。最低賃金は都道府県ごとに定められるものであり、当然、都市部と地方の水準は同じではない。
日経新聞によれば、厚労省の担当課長は7日の会合で、外国人材の受け入れ拡大を控える14業種を念頭に「産業別に全国一律の最低賃金を設けることもあるのではないか」と発言し、その後の取材で年内にもルールを整えたいとしたという。
現時点では政府・与党との調整不足が露呈しており現実的な政策という話にはなっていないように見受けられるが、これはどう考えても悪手ではないだろうか。筆者がこの政策案を見聞きし、真っ先に思いついた事例が欧州債務危機だ。
地方の企業が失うのは
賃金を介した調整機能
「経済活動の区域は異なり、各地域の生産性も異なるが、通貨は単一で為替による競争力の改善は不可能」という前提がいかに機能しないかという問題について、欧州債務危機以上のケーススタディーは近年ないだろう。
ユーロ圏は「国ごとに生産性は異なるが通貨(金融政策)は同一なので為替(や金利)による競争力改善は不可能。しかも、安定成長協定(SGP)により財政政策での景気下支えも不可能」という構造を内包している。いくらイタリアやギリシャが不況に陥っても自国の中央銀行が金利を下げて通貨安・輸出増という効果を狙うことはできないのである。
2013年以降、欧州債務危機が収束し始めたのは通貨安や拡張財政でショックを緩和することのできない南欧諸国が物価・賃金を介して血のにじむような各種リストラを断行した結果でもある。