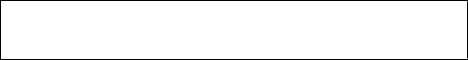昨年末、千葉大学附属病院から申請されていたNKT細胞を用いた免疫療法(Chiba-NKT)が進行再発非小細胞肺がんを適応として先進医療の承認を受けた。
承認に先立ち、安全性と有効性を評価する「高度医療評価会議」で交わされた意見書には「本治療法が多くのがん患者さんに届くことを期待」「早期薬事承認を目指すため、すでにある標準治療と比較したほうがよいのでは」と好感触のコメントが並んでいる。
NKT細胞は1986年、当時千葉大医学部教授だった谷口克氏(現理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター長)が発見したもの。免疫は生まれつき備わっている「自然免疫系」と、病原菌など異物に反応して発動する「獲得免疫系」に大別される。免疫が効果的に働くには両者の連携が欠かせないのだが、NKT細胞は双方の特徴を併せ持ち、橋渡し役として働くことがわかっている。
がん免疫を例にすると、ごく微細な生まれたてのがん細胞に対しては「自然免疫系」の代表格であるナチュラルキラー細胞とともに立ち向かい、相手の勢力が増すと、より攻撃的な「獲得免疫系」のCTL(細胞殺傷性T細胞)を動員し、総力戦に持ち込む役割を果たす。まさに免疫系の要なのだ。治療では患者自身のNKT細胞を体外で活性化し、点滴で戻す方法が取られる。進行再発非小細胞肺がん患者23例を対象にした臨床試験では、生存期間17.4ヵ月、このうち免疫の総動員を促すインターフェロンγ(IFNγ)という物質が増えた10例では29.3ヵ月だった。
非小細胞肺がんは日本人の肺がんの8割を占め、切除不能・進行再発がんの5年生存率は15~20%、抗がん剤による標準治療の平均生存期間は7.8ヵ月とされる。つまり、臨床試験を見る限りNKT細胞療法では標準療法の2.2倍、IFNγの産生を増強しやすい体質なら3.8倍の生存延長効果が期待できる。長らく代替療法と同列に扱われてきた免疫細胞療法だが、ようやく標準治療と勝負できる真打ちが登場したわけだ。
千葉大の計画書では薬事承認のメドは2020~21年。玉石混交の免疫細胞療法を淘汰する意味において、厳正な臨床試験は必須だが、心情的には1日も早く実臨床に登場してほしい。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)