シリーズ累計600万部を突破する『嫌われる勇気』を筆頭に、これまで100冊近い書籍の構成執筆を手がけてきたライター・古賀史健さん。ライターとはなにか? いい文章とは?──考えて考えてことばを尽くした『取材・執筆・推敲』が話題を呼んでいる。3年の月日をかけて書き上げたこの本のコンセプトは、「次代のライターを育てる」学校の教科書。世に送り出したいま、どんな学校をつくろうとしているのか? ライターとしてどこへ向かうのか?「これから」の起点には「自分を変える勇気」があった。(取材・構成/徳 瑠里香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
もう一つの教科書
「1000枚のフィードバック」
(【前編】より続く)
──フィードバックをメインにしたライターの学校とは、具体的にどんな場になるのでしょう?
古賀史健(以下、古賀):約半年間、全8回の授業をするんですが、毎回課題を提出してもらって、僕がフィードバックをします。課題に対する朱入れ添削と総評を一人ひとりに伝える。課題は、インタビュー原稿からエッセイ、論述形式までさまざまなスタイルのものを用意しているんですが、たとえばインタビュー原稿では、録音した取材音源自体も提出してもらおうと思っていて。その音源を全員分、僕が聴くんですよ。
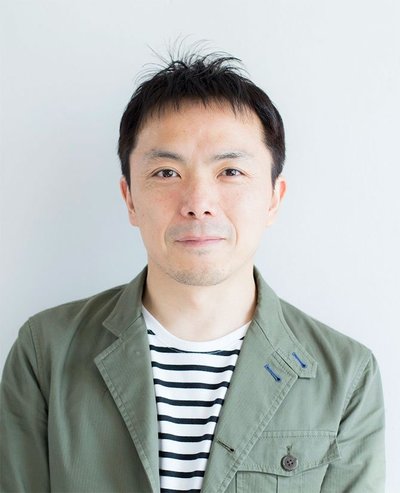 古賀史健(こが・ふみたけ)
古賀史健(こが・ふみたけ)ライター
1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著)、『ミライの授業』(瀧本哲史著)、『ゼロ』(堀江貴文著)など。編著書の累計部数は1100万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。次代のライターを育成し、たしかな技術のバトンを引き継ぐことに心血を注いでいる。その一環として2021年7月よりライターのための学校「batons writing college」を開校する。
──ふへえええ!?
古賀:取材音源を聴いて、文字起こし原稿も読んで、「取材そのもの」へのフィードバックをする。「ここで質問をしていたらもっと話が膨らんだのに」とか「ここはスルーしちゃだめだよ」って。
──ほうえええ。…ってさっきから驚きすぎて変な声が(笑)。「取材への朱入れ」なんて、はじめて聞きました。
古賀:そんな面倒くさいことほかに誰がやるんだって感じですよね(笑)。でも、たとえ編集者さんがインタビューに同席しても、取材へのフィードバックってもらえないじゃないですか。あるいは誰かが書いたインタビュー原稿であっても、完成品を見るだけでは、その人がどう取材しているのか、ほんとうのところはわからない。取材って、ブラックボックスのなかに隠されたままだから。誰がどんな取材をしているのかもわからないし、自分がいい取材者なのかについても、評価が難しいんですよね。
──取材は、原稿以上に、人から学ぶことも指摘をもらうこともできないですね。
古賀:もちろん「原稿そのもの」にもフィードバックをしますよ。受講生には、取材音源、文字起こし、完成原稿の3つを提出してもらう。僕は、取材音源を聴いて、文字起こしに取材の添削を入れて、完成原稿の添削をして、総評を書く。添削については、直しの赤、提案の青、コメントの緑と、三色のペンを使って、みっちり丁寧に指摘を入れていきます。
──なんと、贅沢な。「取材そのもの」はもちろん、「原稿そのもの」にもそんなに真剣で濃密なフィードバックをもらったことはないです。古賀さんはこの学校でそこまで徹底したフィードバックを……
古賀:やる。なので学校名は「batons writing college」なんですが、コンセプトは「1000枚のフィードバック」。
──1000枚とは?
古賀:一期につき募集する生徒さんは30人。一対一で僕が添削と総評をした原稿は全員で共有します。自分以外にも、あの人がこんな文章を書いた、それに対してこういう朱が入った、というのがわかる。仮に一人4枚として、毎回120枚、それが全8回なので、学校を修了するころには「1000枚のフィードバック」ができるんです。
──ちょっと待ってください。1000枚って……分厚いこの本を2冊重ねても足りないほどの厚みになりますよ? A4用紙がみっちり埋まるほどの朱入れを1000枚積み上げるって……途方もない。古賀さん、腱鞘炎になりますよ?
古賀:ね。僕自身、はじめての試みなので、その作業量がどれほどのものなのか、ちょっと怯えています(笑)。とてもたのしみではあるんですが。
──仮に1時間のインタビューを30人分、聴くだけでも30時間。そこに朱を入れていく……それだけでも相当な時間と労力がかかりますよね。それが全8回……「1000枚のフィードバック」は、それ自体が一生ものの教科書になりますね。
古賀:そう。この学校に通った人たちだけの特別な教科書になる。僕の本が「はじまりの教科書」で、フィードバックは「おわりの教科書」。2冊の教科書で学んでもらいます。
たしかな技術のバトンを渡す覚悟
──授業自体は、古賀さんが『取材・執筆・推敲』に沿ってレクチャーされるんですか?
古賀:そうですね。ただ、いわゆる学校の授業みたいな、一方的に僕がしゃべるだけの講義にはしません。僕の考えは、もうほとんどこの本に書いていますしね。本を読んで「予習」ができていることを前提に、「復習」としての説明はしますが、受講生には僕に「取材」をするつもりで授業に参加してもらいます。なので、疑問点をなくす質疑応答の時間もたっぷりとります。そうそう、ある方がこの本について「自信があるのに、自慢はない」と評してくれたんですよ。普通はベテランが書くと「あのときはこうだった」と、過去の仕事についての自慢が入るのに、って。
──はあ、たしかに。この本には古賀さんが手がけてきた具体的な仕事の話は書かれてないですもんね。
古賀:そうなんです。だから今回の学校では、実例として僕がやってきた仕事やそこで考えたことにも触れつつ、応用的な内容にも踏み込んでいきたいと思っています。
──今回、学校に通えるのは課題作文によって選考される30人。作文を読むうえで、期待するポイントはありますか?
古賀:僕が一番読みたいのは「情報の希少性」。無難に整っている及第点の原稿よりは、「ここでしか読めない」ものを読みたい。その人が普段どんな取材者として生きているか、その視点を知りたいですね。
──なるほど。ちなみに学校は、今後も定期的に開かれるのでしょうか?
古賀:とりあえずは、今年の7月から半年間。その後は、オリンピックイヤーに1回くらいかな。というのも、僕は学校をやるこの半年間、ほかの仕事はしないくらい本気でやるつもりなので。
──「1000枚のフィードバック」には、それほどの覚悟がうかがえます。
古賀:この本もそうなんですけど、1冊の本をつくるときって、「命を削る」と言うと大袈裟だけど、ほんとうにそれくらいへろへろになっちゃう。僕が学校をやるなら本と同じくらいの労力を使わないと意味がないと思っていて。なにかの片手間に、サイドビジネス的に学校をやるという選択肢は、僕にはないのでね。
じゃあ本をつくるのと同じくらいの労力ってなんだろう?って考えたときに浮かんだのが「1000枚のフィードバック」。このやり方なら、たしかな技術のバトンを渡せる、と。僕は誰よりも本気の、実践的なガチガチの朱を入れますから。って自分でも話しててちょっと怖いけど(笑)。そんな面倒くさいことをやりたい、やろうと思うのは僕くらいしかいないんじゃないでしょうか。
──そう思います。そんな学校、ほかにどこにもない、と。参加する側にも本気度が問われる。ライターにとっては、本当に貴重なチャンスですね。通いたい。
古賀:僕も行きたいですから。若い人が僕の本を読み込んで学校に通ったら、その濃密な半年間は、忘れられない体験になると思うんですよ。課題を出して朱入れされるのは胃がキリキリするような日々かもしれないけど、一生ものの技術が磨かれるし、ライバルや仲間にも出会える。僕にもそういう存在が何人かいて、彼らのいい仕事を見ると励みにも刺激にもなるんですよね。「オレはなにをやってるんだ」って。これからフリーランスでライターをやっていく人たちにとって、この学校での体験と出会いは、生涯の宝になるはずです。



