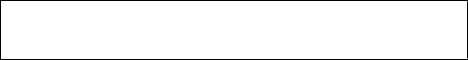12月10日終値の日経平均株価は9533円だったが、翌日の「日本経済新聞」を見ると、この株価で、日経平均構成銘柄の平均PBR(株価純資産倍率)がちょうど1倍となる(純資産は前期末基準)。東証1部上場全銘柄の平均PBRは0.97倍とわずかに1倍を下回るが、こちらもほぼ1倍だ。
PBR1倍というと、「株価の下値めどだ」と言われることが多かった。「下値めど」というのは、株価が下落した場合、そのあたりが「底」になるという意味だ。
今でも、そのように書く入門書はあるが、現実は、「平均」が1倍なのだ。PBR1倍を割り込む株価の会社が多数ある。
PBR1倍が株価の下限になるという考え方の背景には「解散価値説」がある。会社を清算する場合の1株当たりの価値は、帳簿上1株純資産だから、株価がこれよりも大きく下がった場合、この会社の株式を買い占めて会社を清算するともうかることになる。だから、株価はPBR1倍を大きくは割り込まないはずだということになる。
しかし、現実問題としては、社員を多く雇用している会社を廃業するのは社会的にも大変だし、その場合の社員への退職金などのコストは、現時点の帳簿には十分反映していないことが多い。素朴な「解散価値」の考え方だけで、PBR1倍を「下値めど」と考えることはできない。
なお、同様の考え方が、株価が高いときにもあったことは興味深い。日本の株価バブルがピークに向かう前年の1988年に、ある大学教授が、株式の時価と企業が保有する資産の時価とを比べる「Qレシオ」という指標を考案して、日本の株価は高過ぎないと論陣を張った。株価と同様に地価が高騰しており、企業が保有する主に土地の時価を計算すると、日本の株価は「まだまだ高くない」と見えたのだ(間違いだったが)。
Qレシオの間違いは、土地も含めて企業が保有する資産の価値がどう決まるのかを考えていない点にあった。地価は、基本的に、その土地を利用して将来得ることができる価値を、現在時点に引き直して評価することによって決まる。
バブル時代は、将来企業が得ることができるであろう利益に対して、最終的には、そこから決まらざるを得ない地価と株価の両方が過大評価されていたのだ。これでは、Qレシオは、株価が高くないことの判断基準になり得ない。