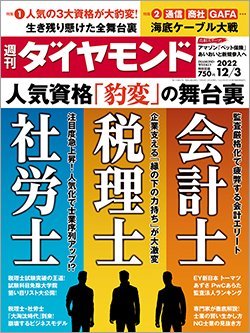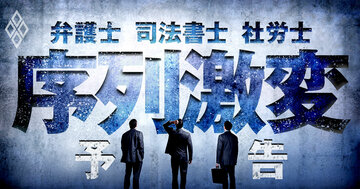異変の背景にあるものとは?
生き残りへ豹変する監査法人
行政処分急増と監査法人交代の激増――。この二つの異変の背景には監査厳格化と、それを発端とした監査報酬の値上げがある。
この10年、上場企業の大規模な不正会計事件が相次いだ。05年のカネボウ、11年のオリンパス、15年の東芝など、監査法人が不正を看過した事件は枚挙にいとまがない。
そこで金融庁や証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会は、上場会社に対する監査の厳格化を一気に進めた。その結果、次々に新しい監査手法が導入され、監査工数が格段に増加。監査の現場では「やらなければならないことが毎年のように増える」(中堅監査法人所属の公認会計士)状況となった。
だが、有価証券報告書の開示期限がそれに伴って延びるわけではない。期限までに監査を終わらせるために、現場にはより多くの会計士を投入しなければならず、コストが増大する。そのコスト上昇分を顧客に請求せざるを得ない状況となっているのだ。
監査を受ける上場会社にとってそれは、監査法人が“豹変”し、唐突に高額な監査報酬を要求してきたと映るはずだ。監査法人から、値上げ分の新たなサービスがあるわけではないからだ。
従って、値上げを打診された上場企業と監査法人の中には、合意できないケースが多数出てくる。こうして、監査法人交代数は過去最多を更新することになったわけだ。
監査報酬の値上げを飲めない上場企業は、より監査報酬が安い中小監査法人へと流れる。実際、EY新日本、あずさ、トーマツ、PwCあらたの四大監査法人は22年、計140社もの上場会社の監査を減らした一方、中小が109社増加させている。
だが、中小の監査法人の中には、上場企業の監査経験が乏しく、また十分な会計士が揃っていないケースがある。ゆえに、年々厳格化・高度化される監査手法についていけない中小監査法人が出始める。その結果、監査品質が一定のレベルに達することができず、行政処分数の急増に至るのだ。
会計士や監査法人にとっては、たとえ豹変と言われようとも、上場企業へ監査報酬の値上げを要請し、多くの会計士と時間をかけて厳格化する監査に対応しなければ、行政処分を受けてしまう可能性もある。値上げは、会計士あるいは監査法人として生き残るための選択ともいえるのだ。