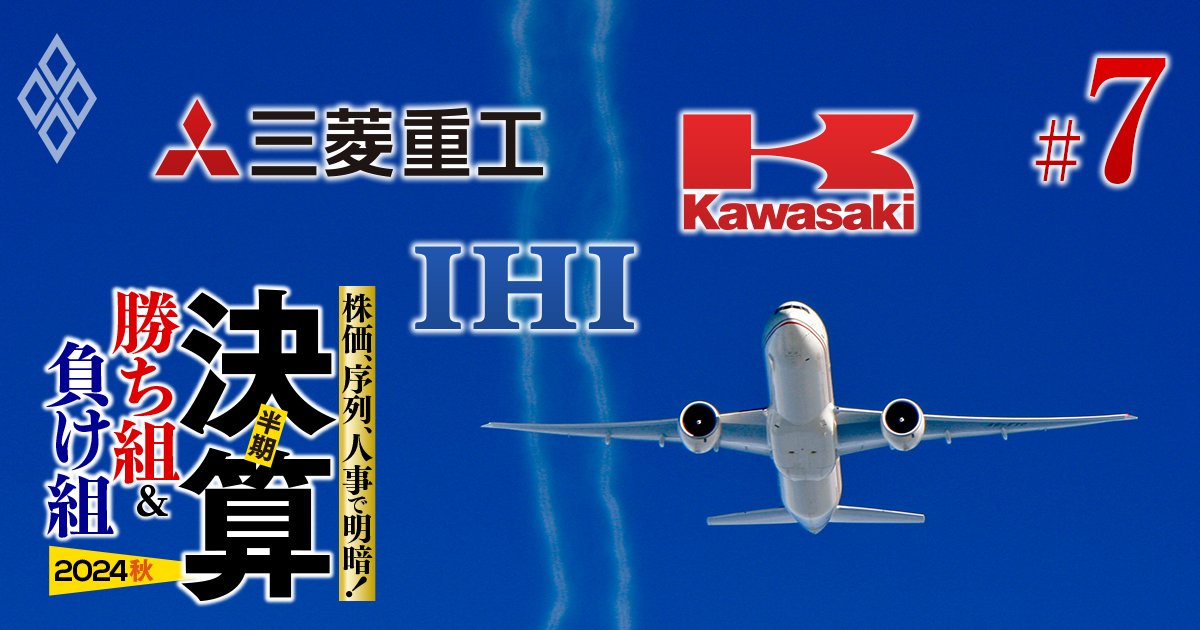戦後のスト観の
転換点となった70年代
現代の若者は、乗客に迷惑をかける労組にも、実力行使に訴える乗客にも感情移入できないと言うだろう。もちろん当時もそのような批判はあった。だが1973年といえば終戦から28年、学生運動の嵐が吹き荒れた1968年から5年であり、「闘争」慣れした人が多かったことは無視できない。それだけ社会が目まぐるしく変わり、自らの手で権利を勝ち取らなければならない時代だったのだ。
騒乱を受けて国労・動労は一時、順法闘争を中止した。両事件は「増長した国労・動労」が「乗客の乱」に恐れおののいた、というところまでしか語られないことが多いが、闘争がこれで終わったわけではない。むしろ本番はここからだった。
動労は1日あけて26日に順法闘争を再開。国労は27日に私鉄と同時に「交通ゼネスト」に踏み切り、国電や新幹線を含む国鉄全線区、私鉄各線が全面的にストップした。
ゼネストとは労組の枠を超えて行われるゼネラル・ストライキのことで、前年4月27日に国労、動労に加えて私鉄大手10社(東武、京成、京王、名鉄、阪急、阪神、南海、京阪、西鉄、営団)、中小私鉄、バスなど約200労組で実施し、効果を上げていた。1973年春闘も交通ゼネストに入った直後、5桁のベアで妥結する勝利に終わった。
そう「闘争」といえば国労・動労ばかり言及されるが、私鉄も同様にストライキを行っており、ともに成功を収めていたのである。乗客は私鉄のストでも国鉄と同程度に迷惑を被っていたはずだが、当時の人々にとってストとは単純に割り切れるものではなかった。
国際経済労働研究所『労働調査時報』は1973年春闘の総括として「現実に国民全般のイライラ感が労働者のストに自らの代弁をもとめたことは事実であろう。したがって順法ストというイライラを相乗させる形態には一般市民は賛同しなかった」と記している。つまりスカっとするストは賛成だが、イライラするストには共感できない、ということだ。
筆者は労働運動史の素人なので何とも言えないが、この時点で1950、60年代のスト観とは変わっていたのだろう。1973年の闘争で棚上げされたスト権の奪還を目指して、国労・動労は1975年に「スト権スト」に打って出る。
順法闘争ではなく一週間以上にわたってストライキを実施し、全国の旅客・貨物輸送が大混乱したが、上尾事件や首都圏国電騒乱事件で見られたような激烈な反発はなかった。ただ国鉄への関心が低下するだけの結果に終わり、「スト権スト」は敗北した。これは1973年という時代がちょうど時代の転換点だったことを示しているのだろうか。