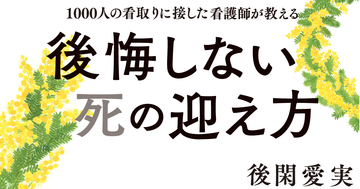「死」の専門家はどこにいるのか
たられば:「死」って全員が必ず通る道なのに、わからなすぎですよね。「病」にはお医者さんというプロフェッショナルがいる。
それなら自分の死についても、自分より詳しい人がどこかにいてほしい、いるはずじゃないかと思ってしまう。かかりつけ医でも、緩和ケア医でも、お坊さんでもいい。「僕はどうやって人生を終えるんですか」と聞きたくてたまらない。この不安を解消したいというのが、僕がこのセッションに参加し続けている理由の1つでもあります。
西智弘(以下、西):医者は生老病死の「病」の専門家とおっしゃいました。確かに疾病そのものについては、私たち医者は専門家です。でも「病(やまい)」全体、疾病によって患者が味わう苦しみや体験までカバーできるかと言われると、まだ不十分ですし、医者にはどうしようもできない部分があると思います。
だからこそターミナルケアでも、宗教的なものの関与の必要性が議論されるようになったのでしょう。
教理と習俗、どっちも大事
浅生:昇洋さんは僧侶として死や病(やまい)に向き合いつつ、科学者として病院で認知行動療法等も施されていますよね。そのあたり折り合いは、うまくつけられているのでしょうか。
吉村:難しい問題ですね。認知行動療法は、生きている人の状態をどう改善していくかを追求する学問です。そして実は仏教学が問題にしているのも、生きている人へのアプローチです。仏教学では、死について問うことはナンセンスとされます。「死んだらどうなるのですか」と尋ねた人に対し、お釈迦さまは「無記」と答えられた。考えても意味がないのだから、触れるなというのが、仏教学の基本的な立場です。
その一方で、仏教は亡くなった方の葬送という文化的役割を担っています。葬儀にかかわり、お位牌にはご戒名の後に「霊位」と書いたりする。お釈迦さまがナンセンスだと一蹴した霊の存在を、実情として取り入れているわけです。しかも、そこにエビデンスがあるのかと言われると、非常に怪しい(笑)。両者にどう整合性をつけていくのか、常に問い続けるべきだと思っています。
例えば、日本にはご先祖さまが戻ってこられる「お盆」という習俗があります。もともと仏教にはなかったものですが、次第に取り入れられ、仏教行事となっていった。そのためご先祖さまの捉え方も、宗派によって全く違います。
霊の存在を全肯定する宗派もあれば、完全否定する宗派もある。私たち曹洞宗では、△です(笑)。教理的にはあるとは言えないけれど、習俗的に存在するから、蔑ろにはできないねという立場です。
浅生:その風習に慣れ親しんだ、生きている人を大事にしよう、ということなんですね。
吉村:はい。ただ、霊を否定している宗派が、他の宗派を蔑ろにしているかというと、そうでもない。それぞれの思想は完結しているので、お互い立場を了解した上で関係性を結んでいる。曹洞宗の僧侶である私としては、ひとまず現実を受け入れることを基本姿勢にしてやっているところです。