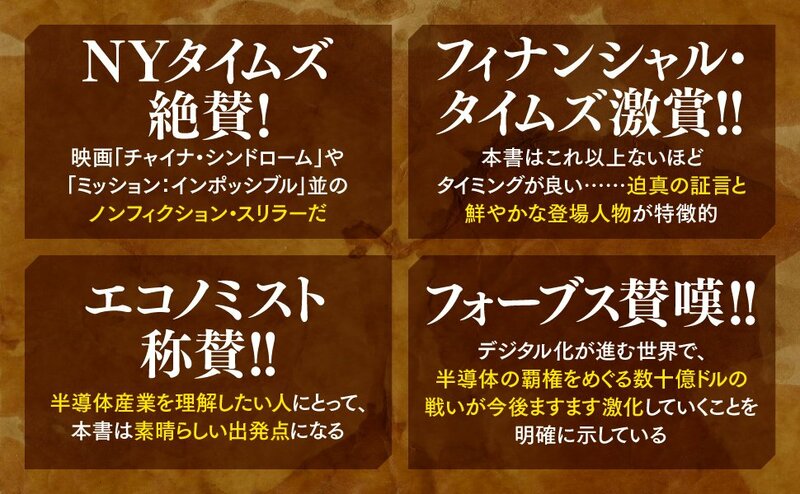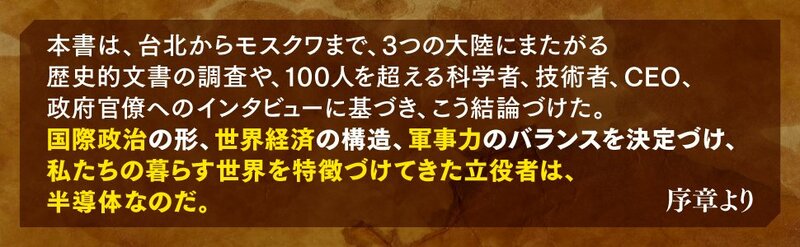NYタイムズが「映画『チャイナ・シンドローム』や『ミッション:インポッシブル』並のノンフィクション・スリラーだ」と絶賛! エコノミストが「半導体産業を理解したい人にとって本書は素晴らしい出発点になる」と激賞!! フィナンシャル・タイムズ ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー2022を受賞した超話題作、Chip Warがついに日本に上陸する。
にわかに不足が叫ばれているように、半導体はもはや汎用品ではない。著者のクリス・ミラーが指摘しているように、「半導体の数は限られており、その製造過程は目が回るほど複雑で、恐ろしいほどコストがかかる」のだ。「生産はいくつかの決定的な急所にまるまるかかって」おり、たとえばiPhoneで使われているあるプロセッサは、世界中を見回しても、「たったひとつの企業のたったひとつの建物」でしか生産できない。
もはや石油を超える世界最重要資源である半導体をめぐって、世界各国はどのような思惑を持っているのか? 今回上梓される翻訳書、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』にて、半導体をめぐる地政学的力学、発展の歴史、技術の本質が明かされている。発売を記念し、本書の一部を特別に公開する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
終戦の混乱を生き抜いたサムスン創業者
李秉喆(イビョンチョル)は、どんなものでも売り物にしてしまう商魂たくましい男だった。ジャック・R・シンプロット〔マイクロン・テクノロジー出資者〕のわずか1年後、1910年に生まれた彼は、1938年3月に母国の韓国で事業を始めた。
当時の韓国といえば、中国と交戦中ですぐにアメリカとも交戦することになる大日本帝国の一部であった。彼の最初の商品である韓国産の干物や野菜は、中国北部へと出荷され、日本軍の腹を満たした。当時の韓国はこれといった産業も技術もない貧しい辺境の地だったが、彼はそのころから「強大で末永く続く」企業をつくりたいと夢見ていた[1]。
彼はのちに、アメリカの半導体産業と韓国国家というふたつの有力な仲間を得て、サムスンを半導体帝国へと変貌させることになる。シリコンバレーの日本打倒戦略の鍵を握っていたのが、アジアで安価な供給源を見つけることだった。彼はサムスンならその役割を容易に果たせる、と考えた。
韓国は自国より強力なライバル国のあいだを渡り歩くのに慣れていた。李がサムスンを創設してから7年後、日本がアメリカに敗戦した1945年に、サムスンはつぶされていたとしてもおかしくはなかった。
しかし、彼は巧みに方向転換を行ない、干物を売り歩いていたときと同じくらい手際よく政治的なパトロンを取り替えた。彼は戦後、朝鮮半島の南半分を占領したアメリカ人たちと関係を築き、サムスンのような巨大企業グループを解体したがっていた韓国の政治家たちを払いのけた。
北朝鮮の共産主義政府が韓国に侵攻してきたときでさえ、彼は資産を守りきった。ただ、北朝鮮が一時的にソウルを占領した際には、共産党の高官が彼のシボレーを押収し、占領下にある首都を走り回ったそうだ[2]。
李は戦時下にもかかわらず、韓国の複雑な政治を巧みに乗りこなし、自身の企業帝国を拡大していった。1961年に軍事政権が権力を握ると〔同年5月16日に朴正煕(パクチョンヒ)らが起こした軍事クーデターのこと〕、将軍たちは彼から所有する銀行を奪い取ったが、彼のほかの企業は無傷で残った。
というのも、彼はサムスンが国家の利益のために営業していて、その国家の利益というのはサムスンが世界レベルの企業になれるかどうかにかかっている、と主張したのだ。実際、李家の家訓の冒頭には、「事業を通じて国家に奉仕する」との文言がある[3]。
こうして、干物や野菜から、砂糖、繊維、肥料、建設、銀行、保険などさまざまな分野に多角化を進めた彼は、1960年代から1970年代にかけての韓国の高度経済成長を、自身が国家に奉仕している証拠だととらえた。
一方、彼が1960年までに韓国一の富豪にのし上がった点に着目した彼の批判者たちは、それを国家(と金に目がくらんだ政治家たち)が彼に奉仕している証拠ととらえた。
日米間の苛烈なDRAM競争が
サムスンの半導体進出のきっかけに
李は、1970年代終盤から1980年代初頭にかけて東芝や富士通といった企業がDRAM市場のシェアを奪うのを見て、半導体産業に割って入りたい、と前々から夢見ていた。韓国はすでに、アメリカ製や日本製のチップの組立やパッケージングの重要な外部委託先となっていた。
さらに、1966年にアメリカ政府の資金援助で韓国科学技術研究所が設立され、アメリカの一流大学を卒業する韓国人や、アメリカで教育を受けた教授陣から韓国で教育を受ける韓国人がどんどん増えていった。
しかし、いくら熟練の労働者たちがいるにせよ、企業が基本的な組立から最先端の半導体製造へといきなり舵を切るのは、そう簡単なことではなかった。実際、サムスンは以前、単純な半導体事業に手を出したことがあったが、利益を上げるのにも、先進技術を生み出すのにも苦労していた[4]。
しかし、1980年代初頭、李は潮目の変化を感じた。1980年代のシリコンバレーと日本の苛酷なDRAM競争が、突破口を切り開いたのだ。一方で、韓国政府もまた、半導体を優先事項のひとつとしてとらえていた。
サムスンの未来に考えを巡らせていた彼は、1982年春、カリフォルニア州へと飛び、ヒューレット・パッカード(HP)の工場を見学する。同社の技術力には驚嘆するばかりだった。HPがパロアルトのガレージからテクノロジー業界の巨獣へと成長できるなら、まちがいなく干物と野菜売りのサムスンにも同じことができるはずだ。「すべては半導体のおかげだ」とあるHPの従業員は彼に告げた。
李はIBMのコンピュータ工場も見学したが、写真撮影可と聞いて衝撃を受けた。「あなた方の工場は企業秘密だらけのはずでは?」と彼は工場を案内してくれたIBM従業員に訊いた。すると、「見ただけじゃ、再現できませんから」とその従業員は自信満々で答えた[5]。しかし、シリコンバレーの成功を再現することこそが、彼の目指す目標だった。
そのためには、何百万、何千万、何億ドルという設備投資が必要だったが、成功する保証はなかった。李にとってさえ、それは大きな賭けだった。彼は何ヵ月と迷った。失敗すれば、彼の企業帝国全体が傾きかねない。
しかし、韓国政府は資金援助の意欲を示し、半導体産業の構築に4億ドルを出資することを約束していた。となれば、韓国の銀行も政府の方向性に従い、追加の融資をしてくれるだろう。つまり、日本と同様、韓国のテクノロジー企業は、ガレージからではなく、低金利な銀行融資や政府の支援を受けられる巨大複合企業から生まれたといっていい。
なぜインテルはサムスンを支援したのか
こうして、1983年2月、緊張で眠れない夜を過ごした彼は、とうとう意を決して電話を取り、サムスンのエレクトロニクス部門の責任者に告げた。「サムスンは半導体製造に乗り出す」。彼は会社の未来を半導体に託したのだ。そのために、最低でも1億ドルを投じる覚悟はできていた[6]。
確かに、李は抜け目のない起業家だったし、韓国政府の強烈な後ろ盾も得ていた。それでも、半導体事業へのサムスンの一世一代の賭けは、シリコンバレーの支援なしではとうてい成功しなかっただろう。
一方のシリコンバレーは、すっかり日用品(コモディティ)化したDRAMではなく、より付加価値の高い製品にアメリカの研究開発活動を集約させつつ、韓国国内でより安価な供給源を見つけることこそが、メモリ・チップ分野で日本との国際的な競争に勝つための最善策だと考えた。
つまり、アメリカの半導体メーカーは、韓国の新興企業を潜在的なパートナーとみなしていたのだ。「韓国メーカーが躍進」すれば、「コストを度外視してでもとにかく安く売ろう」とする日本の戦略は、世界のDRAM生産を独占するのに有効ではなくなるだろう、とロバート・ノイスはアンディ・グローブに語った。韓国メーカーに価格で負けるからだ。その結果は日本の半導体メーカーの「首を絞める」だろう、とノイスは予測した[7]。
したがって、インテルが韓国のDRAMメーカーの台頭を応援するのは自然な成り行きだった。こうして、インテルは1980年代にサムスンとの合弁事業契約を結んだシリコンバレー企業のひとつとなり、サムスン製のチップをインテル・ブランドのもとで販売することになった。韓国の半導体産業を支援すれば、シリコンバレーに対する日本の脅威が間接的に和らぐと踏んだのである。
さらに、韓国のコストや賃金は日本より大幅に低かったので、たとえ韓国企業の製造工程が超効率的な日本企業ほど完璧に緻密でなくても、サムスンのような韓国企業が市場シェアを獲得できるチャンスはあった。
1 Geoffrey Cain, Samsung Rising(Currency Press, 2020), p. 33.
2 Cain, Samsung Rising, pp. 33-41.
3 Dong-Sung Cho and John A. Mathews, Tiger Technology(Cambridge University Press, 2007), pp. 105-106; Cain, Samsung Rising, pp. 40, 41, 46. 李の財産については、“Half a Century of Rise and Fall of the Korean Chaebol in Terms of Income and Stock Price,” Yohap News Agency, November 7, 2006, https://www.yna.co.kr/view/AKR20110708154800008を参照。
4 Si-on Park, Like Lee Byung-chul, p. 71; Cho and Mathews, Tiger Technology, p. 112; Daniel Nenni and Don Dingee, Mobile Unleashed(Semi Wiki, 2015); Kim Dong-Won and Stuart W. Leslie, “Winning Markets or Winning Nobel Prizes? KAIST and the Challenges of Late Industrialization,” Osiris 13(1998): 167-170; Donald L. Benedict, KunMo Chung, Franklin A. Long, Thomas L. Martin, and Frederick E. Terman, “Survey Report on the Establishment of the Korea Advanced Institute of Science,” prepared for US Agency for International Development, December 1970, http://large.stanford.edu/history/kaist/docs/terman/summary/. サムスンの初期の苦労については、Hankook Semiconductorを参照。Samsung Newsroom, “Semiconductor Will Be My Last Business,” Samsung, March 30, 2010, https://news.samsung.com/kr/91.
5 Park Si-on, Like Lee Byung-chul, pp. 399, 436.
6 Myung Oh and James F. Larson, Digital Development in Korea: Building an Information Society(Routledge, 2011), p. 54; Park Si-on, Like Lee Byung-chul, p. 386; Cho and Mathews, Tiger Technology, pp. 105, 119, 125; Lee Jae-goo, “Why Should We Do the Semiconductor Industry,” tr. Soyoung Oh, ZDNET Korea, Mar 15, 1983, https://zdnet.co.kr/view/?no=20110328005714.
7 Tedlow, Andy Grove, p. 218[邦訳:テドロー『アンディ・グローブ』上巻332ページ]; Robert W. Crandall and Kenneth Flamm, Changing the Rules(Brookings Institution Press, 1989), p. 315; Susan Chira, “Korea’s Chip Makers Race to Catch Up,” New York Times, July 15, 1985; “Company News: Intel Chip Pact,” New York Times, June 26, 1987.
(本記事は、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』から一部を転載しています)