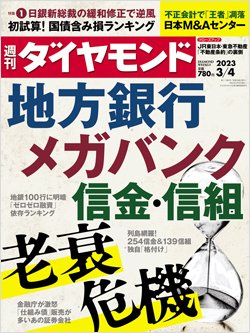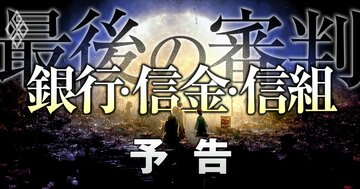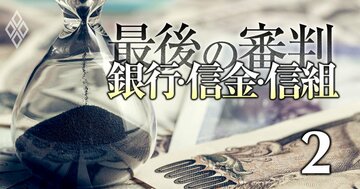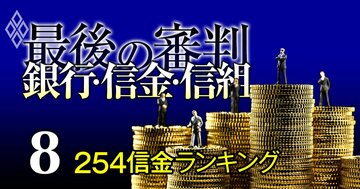金利「据え置き競争」の我慢比べ
2%上昇で地銀31行が資本の健全性保てず
金融庁は今、仕組み債だけでなく、逆ざやが深刻化しかねない外国債券のモニタリングも強化している。ただし、業績をむしばみ得ると地銀が懸念している要因は他にもあるのだ。
では地銀は具体的に、収益悪化要因として何を懸念しているのか。ダイヤモンド編集部が実施したアンケートで7割以上の地銀が挙げたのが「地域経済の悪化」だ。
自由回答では、物価上昇や原材料高、エネルギー価格の高騰などによる取引先の経営悪化を懸念する声が多く寄せられた。各国の保護主義化やロシアのウクライナ侵攻、円安が中小企業の経営にもたらす打撃は大きい。もともと地方では人口減少などによる地盤沈下が課題だが、そのスピードがさらに速まる恐れがある。
また、金利上昇の可能性が高まっていることも地銀を悩ませる要因となっているようだ。ある地銀幹部によれば、「金利競争の激化」も金利上昇と無関係ではないという。
地銀がこの10年に繰り広げた壮絶な金利競争の流れは簡単には変わらず、「これからは『金利据え置き競争』という我慢比べが始まる」(同)という。実際、金利上昇局面では、他行から低金利での借り換えを促すなどして貸出金の増加を狙う地銀が相当数、出てくるはずだと見る向きは多い。前述したように、今は中小企業の経営が厳しい時局でもあり、攻勢を仕掛ける地銀が出てもおかしくない。
一般的に銀行は、金利が上がれば貸し出し収益が増加し、もうかるとされている。しかし、現実はそんなに甘くないということだ。
さらに甘くない現実として地銀に立ちはだかるのが、2位に挙げられた「金利上昇による日本国債の含み損拡大」だ。国債の価格は金利と逆相関関係にあるため、金利が上がれば国債の価格は下落し、保有債券の評価損を抱える。
地銀が「国内基準」を採用している限り、含み損はいくら増えても自己資本から差し引かれることはない。しかし銀行全体のリスク量が高まれば、本業の貸し出しに保守的にならざるを得なくなる。日本資産運用基盤グループ投資運用ソリューション部の石田淳部長は「含み損の拡大に伴いリスクテーク力が低下し、投融資の機会が失われる」と懸念する。外債と違い、逆ざやになることがまずないからといって、「満期まで抱えれば問題ない」とは本来、言い切れない。
ダイヤモンド編集部が、金利が上昇した場合の国債と地方債の評価損を試算したところ、「金利2%上昇、健全性を保つために必要な自己資本比率7%」のシナリオベースでマイナスに陥る地銀は31行に上った。
「金利が上がっても、向こう5年はむしろつらい」。そうぼやく地銀業界は、収益向上策として王道の「取引先支援」を掲げるものの、従来型ではままならない可能性が高い。
老衰危機に瀕する地銀に今、数々のリスクが襲い掛かろうとしている。