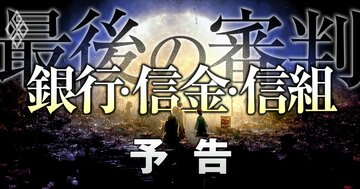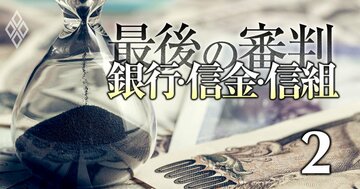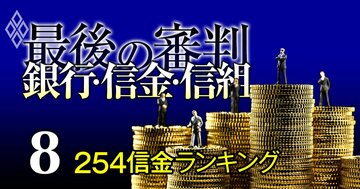『週刊ダイヤモンド』3月4日号の第1特集は「地方銀行 メガバンク 信金・信組 老衰危機」です。日本銀行の次期総裁に、経済学者で元日銀審議委員の植田和男氏が起用される見通しで、金利上昇期待も高まっています。しかし金融機関にとって追い風ばかりではありません。「老衰危機」にある金融機関は、時代の荒波を乗り越えることができるのか――。地方銀行、メガバンク、信金・信組の今に迫ります。(ダイヤモンド編集部副編集長 重石岳史)
金融庁のモニタリングで始まった
"老衰"地銀を襲う苦難の数々
「悪いことを悪いと言うのがわれわれの仕事じゃないですか」――。
金融機関のモニタリングを行う総合政策局モニタリング部門の屋敷利紀審議官は、ダイヤモンド編集部のインタビューにそう述べた。
 地銀は具体的に、収益悪化要因として何を懸念しているのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
地銀は具体的に、収益悪化要因として何を懸念しているのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
屋敷審議官が言う「悪いこと」の一つが、仕組み債の販売だ。仕組み債は、債券でありながらデリバティブの要素を含んだ複雑でハイリスクな金融商品だ。金融機関が受け取る手数料は高いものの、顧客へのリスクが大き過ぎる商品としてかねてより問題視されていた。
金融庁は昨年8月に公表した金融行政方針で、仕組み債の販売で「顧客本位の業務運営」ができていない恐れがあると指摘し、特に地方銀行グループ傘下の証券会社の販売体制についてモニタリングを行うと明らかにした。その宣言通り、同年10月には常陽銀行(茨城県)、足利銀行(栃木県)、第四北越銀行(新潟県)、七十七銀行(宮城県)、同11~12月には群馬銀行、広島銀行、静岡銀行、今年1月には横浜銀行(神奈川県)などに立て続けにヒアリングが入ったもようだ。
モニタリングでは仕組み債に限らず、リテールビジネスの在り方から問う壮大なテーマが設定された。ヒアリング項目は大きく四つ。(1)リテール戦略の全体像と、経営としての考え方、(2)顧客本位の業務運営の追求方法、(3)営業現場の実情、(4)管理、内部監査部門における顧客本位の業務運営の検証体制――である。
具体的には、「地域で果たすべき役割とリテールビジネスとの関係性についてどう考えているか」から、「各金融商品の販売を会議体でどう決定したか」「1行員当たりの営業件数や販売額はどのくらいか」といったことまで詳細に詰められ、「体制整備が甘い地銀は、こっぴどく絞られた」(地銀幹部)という。
だが、地銀の苦難はそれだけでは終わらなかった。