では、どのように対処するのが適切なのだろうか。何より重要なのは「積極的な情報開示姿勢」である。炎上騒動を目の当たりにしたネットユーザーやマスメディアが関心を抱く事項に対して先手を打って答え、彼らの要望に応えることで、「真摯な対応がなされた」と認識されればよいだろう。その段階で正確な情報提供がおこなわれ、組織として実態をきちんと伝えようとする誠実な意思を示さねばならない。細かく指摘するならば、以下の各要素に対して情報提供ができることが望ましい。
・何が起こったのか?→確認できた事実を伝える
・なぜそれが起こったのか?→原因を究明した結果を伝える
・どこに責任があるのか?→責任の所在を明らかにする
・損害・損失は?→損害・損失を明らかにし、講じている拡大防止措置を伝える
・今後の見込みは?→再発防止のための取組を伝える
「コンプライアンス」のあるべき姿
炎上等で世の中を騒がせてしまった会社が、世間から「コンプライアンス意識が足りない!」等と非難されることがある。よく耳にする言葉ではあるが、実際どのような意味を持つのだろうか。
「コンプライアンス」を直訳すると「法令遵守」との意味になるが、昨今では単に法律を守ればよいというわけではなく、社内規定やマニュアルといった所属組織内の規律、そして倫理観や社会的規範など、法的に規定されているわけではない道徳やマナー的なものまで含めた社会のルールに沿えており、公正明大であること、といったニュアンスが含まれるようだ。縛りが強い順に、次のとおりとなる。
・国民が守るべきルール
国会で制定された法律、国の行政機関で制定される政令、府令、省令といった、法的拘束力のある法令全般。地方公共団体の条例、規則なども含まれる
・所属組織のメンバーが守るべきルール
就業規則、社内規定、業務マニュアルなど、所属組織のメンバーが遵守しなければならない取り決め全般
・人として配慮すべきルール
倫理観、道徳観、社会的規範やマナー、公序良俗意識、誠実さなど、法令や規則で定められたものではないが、社会から求められるルール全般
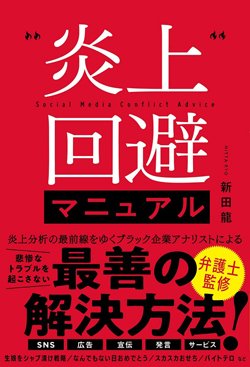 『炎上回避マニュアル』(徳間書店)
『炎上回避マニュアル』(徳間書店)新田龍 著
とくに3つ目の要素は、違反したからといって特段の罰則があるわけではない。しかしこれからの時代、単に法律を守るのみならず、「社会的規範や倫理的ルールを意識し、遵守したうえでビジネスをおこなっていく」との姿勢を示すことは、企業が社会的責任を果たすうえで根幹となる要素であり、消費者や取引先からの信頼を獲得するためには必須であるといえよう。
実際、要素として挙げたうちのひとつ「誠実さ」については、近年ビジネスシーンにおける重要度も日々増している。おもに欧米企業で、経営方針や社員が持つべき価値観として頻繁に使われるようになった「インテグリティ(integrity)」との用語があるが、こちらなどまさに「誠実」「真摯」「高潔」といった概念を意味する言葉だ。近年では特に、組織を率いるリーダーやマネジメント層に求められる重要な資質と認識されている。「マネジメントの父」と称されるピーター・ドラッカー氏は、「インテグリティこそが組織のリーダーやマネジメントを担う人材にとって決定的に重要な資質である」と述べているし、「世界一の投資家」と言われるウォーレン・バフェット氏も、人を雇うときに求める3つの資質に「インテグリティ」「知性」「活力」を挙げているほどだ。企業において「誠実さ」は、健全な組織を運営し、公正なビジネスによって成果を上げるために欠かせない要素である以上、誠実であることを行動規範として明確に示しておく必要があるだろう。
昨今はとりわけ、問題発言と絡めて組織の不祥事が数多く報道され、モラル意識の低い企業の悪行が目立つように感じられる。しかしこれは、「以前よりも違法行為をする人や会社が増えたから」ではない。(それどころか、刑法犯の認知件数は現在19年連続で減少中で、平成27年以降は毎年、戦後最少を更新し続けている※)むしろ、我が国の社会や経済の構造が「公正であること」をより重視するように変化してきており、その変化に対応できないまま、モラル意識やコンプライアンスに無頓着な人や組織が、ネット上やメディア上で炙り出されやすくなった、と認識するほうが正確であろう。
※法務省「令和3年版犯罪白書」参照、2022年執筆時点のもの







