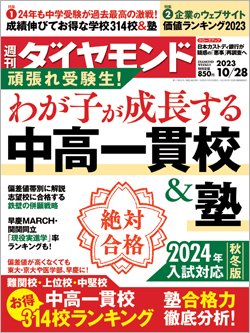首都圏の中受ブームのけん引役は東京都、中でも都心部だ。森上教育研究所の森上展安代表は「特に湾岸エリアに子どもが増えたことが、東京の中学受験熱の要因。加えて近年は都心回帰で優秀層の家庭が都心に集まっている。一方、コロナ禍で東京の優秀層が神奈川県の上位校を回避する動きがあったが、24年入試は一服するだろう」と分析する。
またSAPIX(サピックス)の広野雅明教育事業本部本部長は、「大学入試を考えた場合、高校入試を挟まない中高一貫校の方が、英語4技能を伸ばすにせよ、海外留学をするにせよ、非常に有利だと考える家庭が、特に都心部で増えていることが昨今の受験者数の増加の一因」と言う。
 東の最強私立男子校、開成は2024年入試からインターナショナルスクールの子どもも受験可能に
東の最強私立男子校、開成は2024年入試からインターナショナルスクールの子どもも受験可能に
より具体的な24年入試の動向を見てみよう。
「今年のポイントは中堅校や伝統女子校の人気が上がっていること」と首都圏模試センターの北一成教育研究所長は解説する。
一方、難関校はどうか。広野氏は「筑駒(筑波大学附属駒場)が24年入試から通学区域を拡大することが一つ。また東京都の私学協会が今年、帰国生入試について、通常の入試日より早い日程で入試を行う場合のルールを設けたが、この動きに付随して開成の募集要項が変更され、これまで受験資格がなかったインターナショナルスクールなどの子どもが24年入試から受験できることも志願者動向のポイントになる」と話す。
また、首都圏では9月末から10月初旬にかけて複数のカトリック系学校が上智大学と高大連携協定を締結。また、香蘭女学校は立教大との系属校推薦における枠を拡大して実質、附属校的になったとも言われる。当然、これらの動きは志願者動向に影響を与える。
関西圏を牽引するのは大阪だ。アップの井上隆弘執行役員は「公立小学校の生徒数が増えている大阪市天王寺区、中央区、北区、西区と、吹田市の千里中央駅周辺が大阪府の中学受験熱を高めている」と解説する。
注目校としては「灘(神戸市)など最難関校や難関校は23年入試に引き続いて人気を集め、関関同立の付属校も安定的な人気を維持するとみられる」(井上氏)という。
ただし、わが子のライバルともいえる志願者の増減に一喜一憂しないことも大切だ。
「昨今の傾向として、志願者の増減が実際の難易度に影響するケースは少なくなっている。難易度が上がるのは合格率80%ラインの志願者が増えたとき。受験生を持つ親は、志望者の増減ではなく塾の偏差値表を信じてほしい」と岩崎氏は念を押す。
親世代の中学受験と違い、家族一丸で臨むのが令和の中学受験の特徴だ。わが子が積み上げてきた成果を発揮するためにも、直前期の親のサポートや、情報の取捨選択が重要になっている。
広野氏は「親の心構えとして、仮に偏差値60の実力の子どもでも、常にその実力を出せるとは限らない。良いときと悪いときで偏差値10は違ってくると認識してほしい。加えてテクニカルの部分では、第1志望がどうしても行きたい学校ならば、合格率40%であってもチャレンジする気持ちが重要。偏差値表の数字は合格率80%ラインなので、これよりも4~5ポイント下であっても合格する可能性はある」とする。
泣いても笑っても、あと100日──。ここまで来たら、周囲に惑わされず、わが子を信じる以外にない。