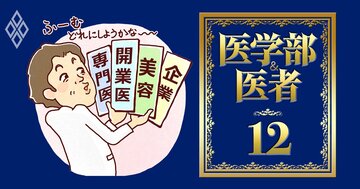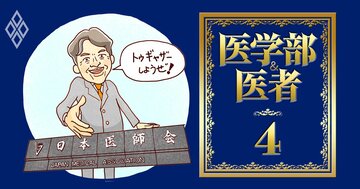写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
視野を広げるきっかけとなる書籍をビジネスパーソン向けに厳選し、ダイジェストにして配信する「SERENDIP(セレンディップ)」。この連載では、経営層・管理層の新たな発想のきっかけになる書籍を、SERENDIP編集部のチーフ・エディターである吉川清史が豊富な読書量と取材経験などからレビューします。今回取り上げるのは、私たちの生活に身近な存在であるにもかかわらず、その裏話を聞く機会が少ない「開業医」が実体験を語っている一冊です。
病気で大学病院を辞した医師が
「開業」に至るまで
新型コロナウイルスの感染法上の位置付けが、今年5月にインフルエンザと同等の「5類」に移行して以降、街は以前のにぎわいを取り戻した。マスク姿の通行人もだいぶ少なくなった。
とはいえ、コロナの流行が収まったわけではない。インフルエンザの感染拡大も続いている。「医療従事者」の皆さんはまだまだ気が休まる状況ではないようだ。
この医療従事者という言葉は、コロナ禍にまつわる報道を機に定着したと思われる。コロナの専門病棟で奮闘する医師・看護師たちが思い浮かぶかもしれないが、多くの人々にとって身近なのは、いわゆる「まちのクリニック」の医師ではないだろうか。
本記事の筆者は、かれこれ1年以上定期的にクリニックに通っている。最初のきっかけは、仕事の疲れであちこち具合が悪くなったことだ。症状がなくなった後も、血液検査をしてもらい、気になるところを診てもらったりしている。胃痛で病院に駆け込み、生まれて初めて内視鏡検査をしてもらったこともある。
何度も通っているので、クリニックの待合室に入ると妙な安心感があったりもする。院長とその奥さんが医師で、二人とも診察をする、典型的な家族経営のクリニックだ。他にもスタッフが何人もいるが、アットホームな雰囲気に心地よさがあるのだ。
だが、多くのスタッフを抱え、設備も充実しているこのクリニックを運営していくのは並大抵ではないだろう。開業後はどれくらい稼げているのか。どんな理由で独立・開業したのだろうか。疑問は尽きないが、診察で聞くわけにはいかない。
そんな、ちょっと気になるけれども意外と知らない「クリニック開業」にまつわるエピソードが満載なのが、今回紹介する『患者が知らない開業医の本音』だ。
本書では、重病で大学病院を辞した小児外科医の著者が、クリニックを開設するまでの経緯、開業医になってからの奮闘ぶり、独立して初めてわかったことなどを、ユーモアを交えて語り尽くしている。
著者の松永正訓医師は1961年東京都生まれ。千葉大学附属病院にて小児がんの治療・研究に携わった後、2006年に「松永クリニック小児科・小児外科」(千葉県千葉市)を開業した。